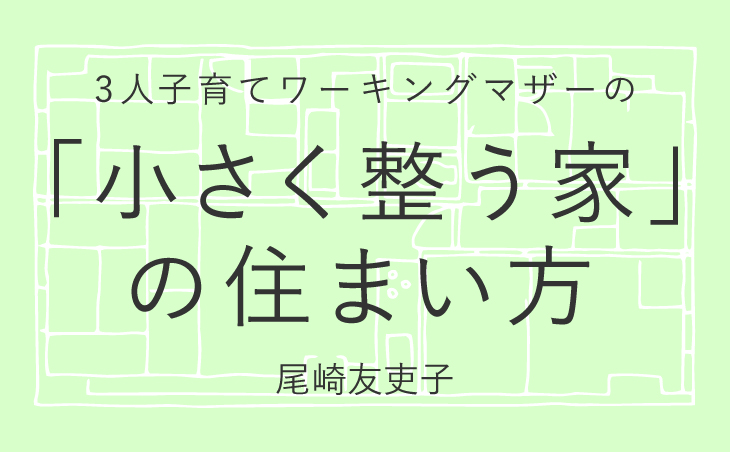第1回
鋤田正義(写真家)
母に買ってもらった二眼レフカメラ (1)
2017.04.18更新
【 この連載は… 】ものづくりに携わる人生の先輩16名の“大切なもの”を通し、それぞれの生き方や価値観を「物語」としてつづった『あの人の宝物』(大平一枝著)が刊行されました。豊かさとはなにか、人生の“これから”を考える人へ。生き方のヒントを見つけてください。
「目次」はこちら

その場に居合わせなければわからない
本質が必ずある
鋤田正義さんは、デヴィッド・ボウイがメジャーブレイクする寸前の一九七二年から彼を撮り続けた。昨今、日本でもデヴィッド・ボウイの大回顧展が開かれ、街角のビルボードや新聞、雑誌には鋤田さんが撮った彼の顔写真があふれている。ボウイだけではない。メンバーが赤い人民服姿で雀卓を囲むイエロー・マジック・オーケストラの『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』、ミカと加藤和彦が青空を飛ぶサディスティック・ミカ・バンドの『黒船』をはじめ、あの写真もこのジャケットもと枚挙にいとまがない。
鋤田さんが写真を撮り始めた七〇年代から今日まで、いかに長い間、無意識のうちに私たちは、彼の撮ったアーティスト写真に触れてきたことか。究極的に言うと、日本は鋤田さんの写真から、グラムロックを知り、テクノを知り、パンクを知ったのだ。
その巨星が目の前でコーヒーを飲んでいる。「昨日の夜、布団の中で思いついたんだよ、宝物って強いて言うならこれかなあってね」。目を細め、まるで長い付き合いの友のように、楽しそうに鋤田さんは語り出した。世代や肩書きや経験をひょいと軽やかに飛び越え、相手が緊張する前に心のなかにするりと入ってくる。目線をあえて低くするのでもない。地位や肩書きという記号でなく、心で会話しようやとでも言うような、まっすぐな気持ちがびしびしと伝わってきた。
インタビューは終始一貫して、本音の連続だった。大学に進めなかったため学生運動を外から見ていた過去が、長い間コンプレックスだったこと。佐世保のエンタープライズや長崎の被爆者、福岡のボタ山を撮ったが、どうもしっくりこなかったことなど、遠い記憶をひとつずつ心の奥からとり出し、丁寧に見せてくれた。緊張していた私だったが、一気に彼の物語に引き込まれた。そして気づいたら、その喫茶店で一緒に笑ったり、涙を流したりしていた。
きっとこんなふうに、単身ロンドンに渡ったときも、言葉や肩書きをすっ飛ばして、するりと誰の心にも入っていったのだろう。有名無名、金持ちか否か、東洋人か西洋人かなんて関係ない。鋤田さんは「その場にいる大事さ」という言葉を何度も使った。同じ空気、見るもの、感じることを共有することが大事なんだよ、と。だから撮影も、たとえばこのような小さな取材でさえも、同じ熱量で、すべて直球、真剣勝負なのだろう。
“時を刻んだカメラ”で撮った生涯ベストワン
九州の炭鉱町の、根っからの映画青年だった。父は戦死し、母は炭鉱用具を卸売りする小さな店を営み、生計を立てた。四人きょうだいの次男。裕福ではなかったが、母は、学業に専念させるため、店番以外のアルバイトは許さなかった。鋤田さんは、高校生のころ、アラン・レネ監督、マルグリット・デュラス脚本『二十四時間の情事』を見たのをきっかけに、映画に夢中になる。
「地元の映画館は、来るのが遅いから、早く見たくて博多まで自転車を漕いで行くの。往復百キロあるんだよ。映画のためなら全然苦じゃなかった。ジェームス・ディーン、マーロン・ブランド、ポール・ニューマンを輩出した、アクターズスタジオに憧れてね。一時は熱に浮かされ、そこに入りたいなんて思ったもんだよ。熱に浮かされる時期って誰にでもある。あれ、大事だね。あとで、デヴィッド・ボウイと話したときルイス・ブリュエル監督のフランス映画『アンダルシアの犬』のあのシーンが好き! っていう話で盛り上がったんだ。彼もその映画が大好きって言ってた」
いささか唐突だが、たとえばいま、あなたは大好きなもののために自転車で百キロ漕げるだろうか? 言い換えればこれは、それほど好きなものがあるかという問いでもある。好きなものは誰にもあるだろう。けれども自転車を漕がなくても、たとえば見たいものはインターネットで、自宅ですぐに見られる。鋤田さんの話を聞いていると、その生の百キロが「好き」を醸成していたのだなあと思う。それは心の肥やしとなって長い間熟成され、いつかなにかに昇華される。たとえば、後に二十世紀最大のアーティスト(イギリス誌で、デヴィッド・ボウイは「二十世紀でもっとも影響力のあるアーティスト」に選ばれている)と意気投合したり、寺山修司*の映画の撮影を担当するなど、自分が映像を撮る側になったり。目を輝かせて少年のころ好きだった映画を語る鋤田さんを見て、好きのエネルギーの尊さを思った。
ある夏、砂利道で自転車で転び、膝を血だらけにして夜遅くに帰宅した。母は、博多への往復を知ってか知らでか、理由を聞かなかった。
「というより、そのとき母親がどう言ったか、あまり記憶がないんだよね。育ててもらうだけで充分。そういう時代だった」
母もまた、四人の子を育て、店を切り盛りするのに精一杯だったということかもしれない。そうやって自由にさせてもらったのが、また良かった。
映画スターのブロマイドを発端に、写真にも興味を募らせた。映画雑誌と写真雑誌は、立ち読みで貪るように読んだ。高校三年の折、母からリコーフレックスの二眼レフカメラを初めて買ってもらった。
「熱望していたのを知っていたのだろうと思うけれど、家計の状況も知っていたので自分からは欲しいとは言わなかった。そのときもどうもらったのか、不思議とあまり記憶がないんだよね。ヨーロッパで花形だったローライフレックスよりローコストな国産品として、爆発的にヒットしていた。当時六千八百円くらい。といっても、当時の六千八百円は安くはないけどね」
一九五六年のことだが、その二年前の教員の初任給が七千八百円と、『値段の明治大正昭和風俗史』(朝日新聞社)に記載されている。後年、四十歳を過ぎたころ、姉から「あれは、お母さんがお金を借りて買ったのよ」と初めて聞いた。
「里帰りで不意にそれを知って、ガーンときて、俺も初めて母に仕送りを始めたの。ところが亡くなった後、兄から“一円も使ってなかった”って聞いて、またガーンとなった」
働きずくめの母だったと、淡々と思い出を語る。その彼が「もうこんな写真は撮れない。生涯のベストワン」と語る作品がある。カメラを買ってもらった年に撮った母の横顔。モノクロのその写真を見たとき、私の目から勝手に涙が溢れ出し、収拾がつかずに困った。なんて気高くて美しく、愛のこもった懐かしくて新しい雄弁な写真だろう!
「炭坑節を踊る夏祭りの日。編み笠がきれいだなって思って、縁側にいた母に“撮るよ”って正面と横顔と二枚だけ撮ったの。このカメラは十二枚しか撮れないからフィルムは貴重でね。二カットだけ」
数年前、広告雑誌上で十数名の写真家が参加した企画に、鋤田さんも参加した。彼は不意に高校時代に撮ったこの写真を思い出し、なんとか実家でフィルムを探し出した。編笠に隠れた母の横顔。誰もが、見えない笠の向こうに自分の母を想像する。凛としてやさしく控えめで、慈しみ深い昭和の母がそこにいる。依頼者から指定されたお題は「愛」だった。
(後半に続く)
* 寺山修司 歌人、劇作家(一九三五‐八三年) 。歌集に『血と麦』、戯曲に『血は立ったまま眠っている』などがある。

 写真 本多康司
写真 本多康司鋤田正義(すきた・まさよし)
1838年、福岡県生まれ。日本写真専門学校卒業。世界にロックの新しい風が吹き始めていた70年、フリーの写真家に。T・レックス、デヴィッド・ボウイ、イギー・ポップらを撮影し、いちはやく日本に紹介。創刊間もない『平凡パンチ』や『anan』誌上で発表した。映画『書を捨てよ町へ出よう』の撮影、イエロー・マジック・オーケストラ、サディスティック・ミカ・バンドの名盤ジャケットをはじめ、近年では黒猫チェルシー、高橋優、再結成のザ・イエロー・モンキー、MIYAVIなどを撮影。CM映像では、サントリーウーロン茶シリーズ、大塚製薬のカロリーメイト、大和ハウス役所広司シリーズなど。デヴィッド・ボウイとの共著『Speed of Life』(イギリス・ジェネシス出版)がある。
【単行本好評発売中!】
この本を購入する