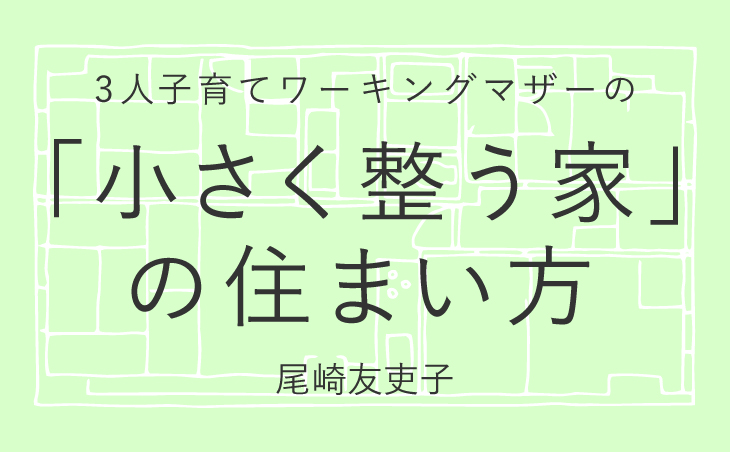第2回
鋤田正義(写真家)
母に買ってもらった二眼レフカメラ(2)
2017.04.27更新
【 この連載は… 】ものづくりに携わる人生の先輩16名の“大切なもの”を通し、それぞれの生き方や価値観を「物語」としてつづった『あの人の宝物』(大平一枝著)が刊行されました。豊かさとはなにか、人生の“これから”を考える人へ。生き方のヒントを見つけてください。
「目次」はこちら

コンプレックスが育てたチャレンジの精神
大学受験に失敗し、長崎市で一年間の浪人生活を経験した。このころ、将来は写真で行くと決意。進学を止め、大阪の日本写真映像専門学校に入学した。写真家、棚橋紫水氏の弟子を経て大阪の広告代理店の写真部に就職。働きながら自分の作品を撮りだす。休日をまとめては長崎に通い、エンタープライズなどを撮った。米軍の航空母艦で、原子力空母といわれ、佐世保入港をめぐって、核持ち込み反対を訴える学生や市民の運動が激化していたからだ。
「でもね、どんなにがんばっても当時は地方にいるというだけで“地方作家”と言われてしまうんです。いつまでたってもアマチュアでしかない。憧れていたのは東松照明や細江英公らがつくっていた写真家集団VIVO。暗室マンに森山大道さんがいて。ザラザラで、独特のコントラストとトーンの作品を撮っていて影響を受けた。真似して撮ったりしてね。そのころの作品としては、長崎の被爆者をテーマとしていました」
大阪での仕事に限界を感じ、二十七歳で上京。主にメンズ・ファッションブランドの広告を手がける代理店に入った。浅井愼平や宇野亜喜良、操上和美などクリエイターが出入りする原宿のセントラル・アパートにオフィスがあり、ファッションやデザインのジャンルでの交友関係が広がる。
一九七〇年、三十二歳でフリーランスになり、同時に結婚もした。前年、ウッドストック・フェスティバル(*)があり、世界にロックの新しい風が吹き始めた時代でもある。鋤田さんは、妻を置いてニューヨークに渡った。 「ウッドストックのことを新聞で見て、四十万人もの人が集まって平和を歌っているのかと驚いてね、自分の目でその後を見たかったし、ニューヨークを撮りたかった」
ところが、そこに熱狂はなかった。祭りのあとのようなざらついた空気の中で、麻薬や売春に興じるヒッピーらの虚ろな目を見た。鋤田さんの心は少しも動かなかった。
帰国後は、『芸術新潮』や『平凡パンチ』『anan』で、ウッドストックを機に生まれたカウンターカルチャーにまつわる写真の仕事が増えていった。
次に目を向けたのはイギリスだ。マーク・ボラン率いるグラムロックの先駆者T・レックスを撮りたいと考えた。ロンドンは、ファッションと音楽の距離が近い。『anan』を発行していた当時の平凡出版(現・マガジンハウス)は、サブカルチャーという新しい文化を若い人に伝えようという気概に満ちていた。その波を本能でキャッチしていた鋤田さんは自腹でロンドンに渡った。「ギャラはないけれど、通訳とスタイリングをやってくれないか」と同行を依頼したのはスタイリストの草分け、高橋靖子さんだ。彼女はすでに山本寛斎のファッションショーをロンドンで成功させていた。
ほとんどアポなしの状態で、靖子さんと、T ・レックスのマネージャーにポートフォリオを売り込みに行き、その場でフォトセッションの許諾を得る。イギリスで絶大な人気を誇る超多忙なバンドのマネージャーの即決にも驚かされるが、その後の話にも驚愕する。初めてのセッションで撮った一枚は、二週間後、イギリスの音楽タブロイド紙『メロディ・メーカー』の表紙になり、ロンドン中のキオスクに並んだ。
当時、ロック・ミュージシャンの写真といえばつくり込んだカメラ目線のものが多いなか、髪を逆撫でにしたマーク・ボランがギターを弾きながら恍惚の表情を見せる。ドキュメンタリー的な手法で、一瞬のリアリティあふれる幸福なショットを捉えたその作品は、後のアーティスト写真の撮影に大きな影響を与えた。
デヴィッド・ボウイとのフォトセッションも同様に成功。その後の鋤田さんの活躍はいまさら私が書くまでもない。
何度聞いても、成功の秘訣など彼の口から出てこない。才能や情熱、運、時代を読むことや先見の明とも違う。ここまで導いた根底にある大切なもの。──それはきっとコンプレックスだ。
「エンタープライズを見ても、ああ船だなあ、と。ぼた山や被爆者を撮ってもどこか心が動かなかった。報道写真を撮る自分に限界を感じていたのです。“その場に居ること”って大事だと思う。僕は大学に行っていないから、あの時代を代表する学生運動の空気を知らないの。全共闘も全学連も知らない。同時代に生きているのにその場に立ち会っていないというコンプレックスがずっとあった。うん、そうだ。こう話しながら思い出してきたよ。僕はどこにも所属していないっていうコンプレックスがあったんだな。だから王道から外れたカウンターカルチャーに惹かれたんだ」
ウッドストックは一年遅れだった。しかしボウイも、『anan』も寺山修司もYMOも、その場に居合わせた。編み笠の母を縁側で撮ったあの瞬間のように、いまを切りとることに身命を賭する。だから爆発的な力を発揮できる。結婚してから単身自腹で海外に渡ったのも、時代の空気を吸っているアーティストたちのいまを切りとるため。誰かの歩いた後ではなく、自分も一緒に寄り添いながら撮る。体をそこに持っていき、同じ空気を吸いながら、撮りながら、自分の所属する場所を自分で築いてきたのだ。
「若いころは意識しなくてもすぐのめり込んだり、集中できたんだけど、いまはそういかない。意識しないと、集中できないんだよね」と自嘲する。
その集中のかけがえのなさは、十八歳のとき、縁側でリコーフレックスを通して学んだ。
「人生をひとまわりしてきたいま、目に見える宝物はこれかなあって思うよ」
目に見えない宝は、がむしゃらに刻んできたときの中にある。誰かの歩いた後でも、だれかがまとめてくれた記事の中でもなく、自分の足で切り拓いた道の中に。
* ウッドストック・フェスティバル 一九六九年に三日間かけて行われ、三十組以上のアーティストが出演、入場者は四十万人、アメリカのロック史上に残るイベント。ベトナム反戦運動に呼応した野外フェスの原点。
鋤田正義的、心のひきだし
一
なんでもあり
日本はファッションやコマーシャルやドキュメンタリーや、ジャンルを記号で分けたがる。でも、なんでもありでいいし、そのほうがおもしろい。ジャンルより、視点や考え方が大事。写真は、「目」が必要。自分はドキュメンタリー的な目で撮る。生き方も自由でありたい。
二
寝るより
楽はなかりけり
母がよく言っていた言葉。それほど働きずくめの人生だった、と。人生を重ねて初めて理解できる言葉がある。生前感謝を伝えられなかったけれど、その思いは大事にし続けたい。
三
その場に居る大事さ
若い子がフェスに行くのもそう。たとえば音楽はデジタルなものでいくらでも聴けるけれど、フェスに体を運んで、生の音を実際に聴かなければわからない物事の本質がかならずある。その手間や時間を惜しまないで。
 写真 本多康司
写真 本多康司鋤田正義(すきた・まさよし)
1838年、福岡県生まれ。日本写真専門学校卒業。世界にロックの新しい風が吹き始めていた70年、フリーの写真家に。T・レックス、デヴィッド・ボウイ、イギー・ポップらを撮影し、いちはやく日本に紹介。創刊間もない『平凡パンチ』や『anan』誌上で発表した。映画『書を捨てよ町へ出よう』の撮影、イエロー・マジック・オーケストラ、サディスティック・ミカ・バンドの名盤ジャケットをはじめ、近年では黒猫チェルシー、高橋優、再結成のザ・イエロー・モンキー、MIYAVIなどを撮影。CM映像では、サントリーウーロン茶シリーズ、大塚製薬のカロリーメイト、大和ハウス役所広司シリーズなど。デヴィッド・ボウイとの共著『Speed of Life』(イギリス・ジェネシス出版)がある。
【単行本好評発売中!】
この本を購入する