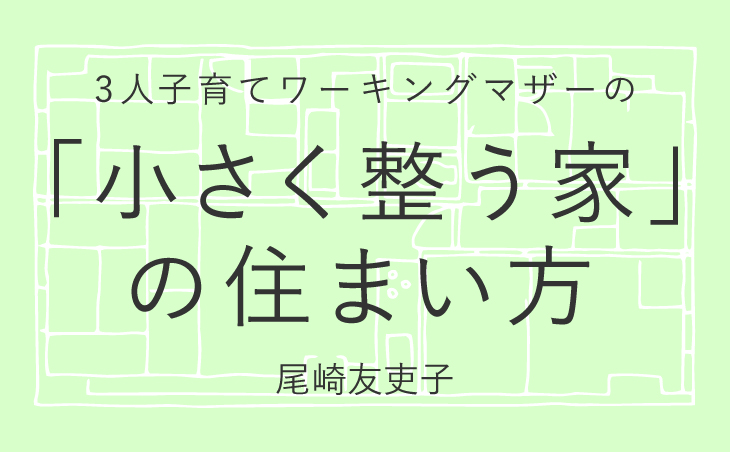第3回
春風亭一之輔(落語家)
初めてもらった給金袋 (1)
2017.05.02更新
【 この連載は… 】ものづくりに携わる人生の先輩16名の“大切なもの”を通し、それぞれの生き方や価値観を「物語」としてつづった『あの人の宝物』(大平一枝著)が刊行されました。豊かさとはなにか、人生の“これから”を考える人へ。生き方のヒントを見つけてください。
「目次」はこちら

熱狂の内と外を自由に行き来しながら
高みを目指す
新しい時代の人だ。志ん生や志ん朝を知らない私のような初心者でも、こういう芸を天才というのだろうと理屈でなくわかる。でありながら、通もきっちり虜にする。また見たいと、噺が終わった途端、次の高座の予定を検索したくなる。このわかりやすさが新しい。芸とは、とか、楽しみ方の流儀とか、古典か新作かといったうんちくや鑑賞者の熟達した経験や知識などなにもいらない。一席聴くだけで、簡単に、シンプルでライブ感溢れる落語という文化の虜になれる。軽々と時空をひとまたぎして、八っつぁん、熊さんのいる路地裏の長屋に導かれる。そういう落語家はほんのひと握りしかいないと、あとから知った。近年のこの世界で、傑出した存在なのだということも。
春風亭一之輔さんはどんな水を向けても飄々として、自分のペースを崩さず、ひどく肩の力が抜けている。苦労や夢や目標や、あるいは落語界の次代の担い手と期待されることへのプレッシャーなど、こちらがねらっている答えを知ってか知らずか、するりとかわす。しかし、取材場所を変え、質問を変え、あの手この手を尽くしている途中のこんな言葉から、意外な心のバランスのとり方を知った。
「小さい子どもが三人いるから、家事を分担しないとまわっていかないんです。高座のある日も、普通に家族の洗濯物を干していきます。時間があれば子どもを風呂に入れたり。家事は嫌いじゃない。すごく好きなわけでもないけれど、そういう日々の暮らしのことやルーティンをやったほうが落ち着く。やってないと落ち着かないとも言えるかな」
どんな熱気の中心にいようと、あるいは周囲から持ち上げられようと、上から自分を俯瞰しているような独特の冷静さがある。なにもかもがフラット。高座のあとの後援者との宴席の彼も見たことがあるが、座席の端で、所在なげにしている人のそばに座り、さっきまで熱狂の中心にいたとは思えない穏やかな風情で、淡々と言葉を交わしながら酒を飲んでいた。温度がそこだけ、二、三度低そうにさえ見えた。
「過剰なことが苦手」と語る。だからよけいに、芸の狂気にも似た成熟が際立って見える。
ウケも失敗も、たったひとりで引き受ける。厳しいところで勝負しているはずの芸人の矜恃は、たとえば前述の言葉のように、予想外にさりげない、じつになんでもないところにあった。そこも含めて新しい時代の落語家だと思うのだ。
緩和と集中。へんてこな世界との遭遇
「あのときの辛さを思えばなんでもできるといまでも思う」と言う、ラグビー部を退部した高校一年の三月。終業式が終わった土曜日の午後、ひとり電車に乗って埼玉から浅草まで出てブラブラしていた。金もない。やることもない。たまたま高校のあった春日部から、東武伊勢崎線一本で行ける大きな街が浅草だった。
「手持ち無沙汰でぶらぶらしていたら、浅草演芸ホールののぼりが見えました。千三百円で昼から入って、夜の九時までいられるという。映画より安いじゃん! と。ちょうどおばちゃんたちの団体が吸い込まれていくところで、中に入ると意外に埋まってる。制服姿は僕ひとりで、ものすごく浮きまくっていました」
落語が始まっているのに、ざわざわ客席がうるさいことにまず驚いた。
「食べたり飲んだり。菓子の袋を落としたり、空き缶を誰かが蹴っちゃってカラカラ鳴ったり。落ち着かない空間だなあ~と思いました。でも、演者は全く気にしていない。一席十五分でさっさと終わっちゃう。こんなんでいいのか? へんてこな、まずいところに来ちゃったなって思いました」
入れ代わり立ち代わり、二十組ほど芸人が出る。昼の部が終わり、休憩になったときは少々辛かったらしい。
「夜の部で、またゼロからか! と。でも、お金払っちゃったし、最後までいようと決めていました。昼と違って夜はひとり客のおじいさんが来たり、仕事帰りのサラリーマンとか若い人が増えるんですね。同じ空間でも客が変わると空気も変わる。昼と夜の雰囲気の違いにも驚かされました」
トリが近づくにつれ、さっきまで落ち着きのなかった観客がだんだん集中して、前のめりになっていった。一之輔さんも知らず知らずの間に楽しくなっていた。そして、いよいよトリに。
「春風亭柳昇師匠が新作落語をしていました。いちばんウケてて、さっきまでガサガサしていた人たちが、わーっと拍手して、こんなに声を合わせて笑っている。緩さと集中と。いままで見たことのない世界で、これはおもしろいところを見たなと思いました」
それから月に一度通うようになった。ラグビーは団体競技だ。ミスをするとチーム全員に迷惑をかける。落語はひとりで、ダメでもうまくいっても自分がかぶればいい。それが楽だし、自分の波長にも合っているような気がしていた。だが、通っていくうちにそうとも言いきれないぞとも、わかってきた。
「寄席は、お客さんもとりこんだ団体プレイなんだって気づきました。ほっとひと息つけるような噺をする人もいれば、押し芸の人、引いた感じのおじいさんもいる。演目にも緩急があるんですね。それから昼と夜、その日の天気や湿度でも笑いはぜんぜん変わる。お客さんによっても変わる。僕はいまでも、お客さんや会場の雰囲気に合わせる方なのですが、そういう生ものみたいな落語の世界にどんどん惹かれていったんです」
その後、高校で二十年途絶えていた落語研究部を復活させた。部室で埃をかぶっていた落語の本やテープを端から見て聴いて覚えた。聴かせる相手は、それほど落語に興味がないまま引き込んだ友人一名。浪人時代も新宿や池袋の寄席に足を伸ばし、独演会にも通った。
浪人が決まったとき、一度、両親の前で「落語家になろうかな」と言ったことがある。サラリーマンの父と、内職をする母に姉三人。反抗期もなく、勉強を強いられたことも、厳しく叱り飛ばされたこともない。一之輔さん曰く「ごく普通の両親」に、さすがにそのときは諭された。
「両親とも最初、きょとんとしてました。で、大学に落ちたからと簡単に逃げ道にするな、ちゃんと大学は出ろ、と。そら、そうだなーと思いましたね」
翌年、多くの芸人や落語家を輩出している落研がある日大芸術学部に入学した。
「きっとラグビーを最後まで続けていたら、落語には巡り合わなかった。ラグビーという団体競技をしていたから、ひとりで全部背負う落語との相性の良さに気づけた。あの終業式の日、浅草演芸ホールに行ってなかったら? ええ、いま、こうしてないと思います」
卒業後は、迷わず春風亭一朝に入門した。
見習い、前座、二ツ目、真打ち。落語にははっきりとした階級がある。一之輔さんは取材場所に、前座のとき、最後にもらった寄席の給金の袋と、二ツ目になって最初にもらった寄席の給金の袋を、宝物として持参した。どちらも未開封だが金額はわかっている。前者は二〇〇四年十月二十九日と三十日の二日分で、三千四百円。後者は同年十一月一日と二日の二日分、五千四百円。
「家の机の引き出しに入れています。こんな機会でもないと、見ないんですけれどね。開ける機会を逸して、いまに至ります」
十六歳から追い続けてきた初心という志が、その茶封筒にはきっちり詰まっている。
(後半に続く)
 写真 本多康司
写真 本多康司春風亭一之輔(しゅんぷうてい・いちのすけ)
1978年、千葉県生まれ。日本大学芸術学部在学中は落研に所属。卒業後、春風亭一門に入門。2004年、二ツ目となり多くの新人賞を総なめにしたのち12年、21人抜きの抜擢で真打ち昇進。同年から2年連続国立演芸場花形演芸大賞を受賞。落語家の起用は志ん朝以来といわれる雑誌『SWITCH』の表紙をはじめ、ラジオ、TV番組のレギュラー、ミュージシャンのMVにゲスト出演、ユニクロのCMなど、落語界では傑出する存在に。
【単行本好評発売中!】
この本を購入する