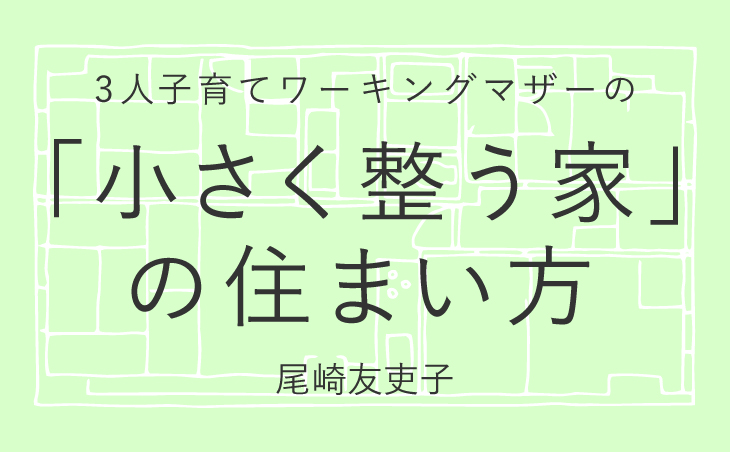第1回
まえがき
2017.07.27更新
長年ブックデザイナーとして活動し映画やデザインの評論でも知られる著者が、グローバル化する政治経済や情報環境、災害や紛争などによって激しく揺さぶられる現代社会を、デザイナーならではの視点からするどく捉えます。
「目次」はこちら
自分の基点は、高校3年生での3か月の入院生活にあると思う。その年の夏、体育の授業でグラウンドを走っていて、それまでは遅れるはずのなかった同級生に追い抜かれる。右足の膝の下に腫れがあった。肉ではなく骨が膨らんでいた。母にともなわれて、立川市内では定評のある整形医院に行った。医師は、レントゲン写真を撮ったあとで病院への紹介状を書き、即刻の入院を勧めた。剣道のせいかと考えた。剣道では、技を放ったあと、かならず右足で床面に着地するからだ。
病院は、家からさほど遠くない小平市にあった。最初の診断は骨嚢腫だったと記憶する。患部の骨を削り、そこに骨盤の骨を移植する手術をした。しかし、移植した骨が定着しない。膿が湧出して骨が浮いてしまうのだ。再手術をして患部の削り直しをした。平日は毎朝、院長の回診があり、看護師に包帯をほどきガーゼをはがしてもらって患部を診察されるのだが、傷口がふさがらない。1段階ずつ強い抗生物質に切り替えていく作業が繰り返される。そういくつも薬品に選択肢があるわけではなく、どうなるのだろうと気を揉んだ。良性ではなく悪性の腫瘍が疑われた。同級生がおおぜいで見舞いに来てくれ、寄せ書きを手渡された。
病室は2人部屋で、どんな事情でかはわからないが、両足を失った青年と同室だった。長期入院中の彼は、寝返りを打つのがままならないのか、床ずれに悩まされていた。日当たりのよい病室で、時間はたっぷりあるのに、受験勉強どころではなかった。本もろくに読めなかったように覚えている。傷口のようすにしか意識が向かなかった。回診時だけが〈現在〉だったと言ってよい。ときおり、同室の青年とレコード鑑賞をしたりした。
いま思いだしても不思議なのだが、ある日、膿が滲みだしている患部を看ながら院長が、「退院しましょう」と宣言した。どこに退院できる予兆があったのか。退院までに数日の猶予があったのではないか。退院後に必要になるからと、松葉杖が貸与され、練習するよう言われた。入院して3か月が経ち、11月になっていた。院長からは、足を使う職業にはなるべく就かないように、とのアドバイスを受けていた。
じょじょに歩行の距離を伸ばし、松葉杖を突いて近所の書店に行った。久しぶりの書店で、このときの気持ちはどのようだったのか。毎日のように訪れる母から差し入れられた本ではなく、自分で選べる本を前にして、うれしくなかったはずはないが、感情は抜け落ち、本屋の小さな店内の暗さだけが記憶にある。明るい病室と暗い本屋との対比に打たれたのかもしれない。書物が暗さをもってそこにあった。
退院してどのくらいで傷口がふさがったのか。結局、症状は良性と悪性の中間だったのだろう。膝の下と削りとった骨盤は凹んだままだった。復帰した高校での成績は壊滅的だった。好きなことをやるしかない。写真も好きだったが、足を使うカメラマンへの志望は排除した。目ざすのはデザインだと決めた。
4年後に足の病気が再発した。前は1968年で、メキシコ・オリンピックが開かれ、こんどは72年でミュンヘン・オリンピックの年だった。4年をひとつの単位として生きていくしかない、と思わされた。さいわい、その後の再発はないが、長いこと立っていると、右足がしびれてくる。座骨神経痛で右足の痛みに苦しんだのが2012年で、やはりロンドン・オリンピックが開催されていた。オリンピックは鬼門だ。
好きなことをやるしかない。それは、自分のなかの動機を出し惜しみしない、ということだろう。出し惜しみしないつもりのデザインや文章が、離れたところからは小さく見える。にもかかわらず、「出し惜しみしない」との基準を立てなければ、その小ささや狭さを量れない。本書の短文が、どれほど時代の軋む音を聞けているのか。この本を、あの日の書店の暗がりにそっと置いてみる。
2017年6月 「共謀罪」成立の日に
鈴木一誌
【単行本好評発売中!】全国書店もしくはネット書店にてご購入ください。