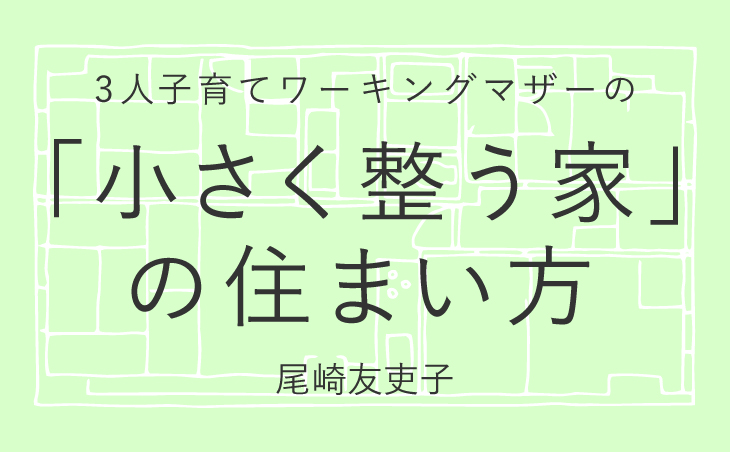第3回
かしこい消費者
2017.08.03更新
長年ブックデザイナーとして活動し映画やデザインの評論でも知られる著者が、グローバル化する政治経済や情報環境、災害や紛争などによって激しく揺さぶられる現代社会を、デザイナーならではの視点からするどく捉えます。
「目次」はこちら
1990年代から、コンピュータがブックデザインの世界に浸透しはじめ、21世紀に入ったあたりで、現場のデジタル化は、ほぼ100パーセントに達した。簡単に言えば、手作業中心に作業時間が経過していったのに対し、いまではモニタを見ている時間がほとんどを占める。その経緯のなかで、変わった点はいろいろとあるが、もっとも気になるのは、プレゼンテーションのありかただ。
話を単行本の装丁に絞ろう。わたしのばあい、手作業の時代では、「こんな装丁にしたい」との案をモノクロで提示し、出版社のオッケーをとっていた。そのモノクロ案は、具体的には、あるべき文字や図版をコピーで拡大・縮小し、つぎはぎした原寸大のダミーだった。白黒でしかないダミーを編集者に見せながら、どんな色味にするつもりかを手短に話し、それでプレゼンテーションは終了だった。あとは、合格なのか不合格かの返事を待てばよい。編集者の一存で決めることもあれば、出版社内で装丁会議が開かれるばあいもある。どうあれ、白黒のダミーを前にして「できあがりがどうなるのか」を想像しなければならない。いわば、デザイナーのプレゼンの可否を判定するのには、そうとうな経験とカンとが必要だったはずで、よほどの大型企画でないかぎり、上層部が意見を挟むことはなかったし、挟みにくい領域だった。
プレゼンが通ると、それを製版用の版下に置き換える工程に進む。台紙、マイラーベース、トレーシングペーパーなどを駆使して、何層にもなる複雑な版下をつくり、さまざまな色鉛筆で製版や色の指定を書きこむ。この指定を読み解いて出来上がりを想像するのは、さらに高度な想像力が要請された。印刷会社の腕利きの営業担当になると、版下を一目見ただけで、難易度がわかった、とも聞く。松竹梅とある製版ラインのどれを使わなければ、要求される品質に届かないか、の判断である。
現在はどうか。色つきで、かつ複数案のプレゼンを求められることが多い。なにせコンピュータだから、ヴァリエーションをつくりカラープリンターで出力するのは容易だ。こうして、ほぼ仕上がりに近いカラーのプレゼンが、クライアントの眼前にいくつも並ぶ。あらゆる部署の人間が、自身の好みに支えられてさまざまに感想を言う。白黒のダミーでは必要だった想像力は退場し、〈チョイス〉だけが焦点化される。レストランの店先で蝋細工のサンプルを眺めながら、どれにしようかと思案している目付きである。
複数案のプレゼンでもの足らず、「タイトル文字がゴシック体のものも見てみたい」などと要請されるときもある。自身が想像力を放棄したのを棚に上げて、平然と発せられる「見てみたい」には、ムッとする。多くの専門家が、素人の「見てみたい」発言に怒っているのではないか。「見てみたい」には、際限がないのだ。
プレゼンテーションのあり方の変容は、消費者の変化とつながっている。消費者をユーザーと言い換えてもいい。カラーのプレゼンをチョイスするだけの編集者は、編集者なのではなく消費者なのだと思う。チョイスという絶対的な権限をもつ神の地位に立つ。あるブックデザインのしごとで、担当編集者が「いいものはわかりますから」というのを聞いて、おどろいた。いいものをわかってもらわなければ困るけれど、デザインと編集の出会いにおいて、編集者の既成概念や価値観が揺らぐケースもあるはずだ。自身とのズレをこそ、他者に求めるべきだと感じる。
〈かしこい消費者〉であろうとするべきなのか。かしこい消費者の背後に、「いいものはわかりますから」という自負が張りついている気配がある。そもそも、ひとは消費者であってはいけないと思う。むろん、ひとは消費者でなければ生きていけない。消費者でありながら消費者であることをヤンワリと拒む生き方を探したい。「いいものはわかる」自負をもちながらも、自己の基準を疑う視線はもてないものか。衆議院選挙が近い。わたしたちは、消費者ではない人間として投票ができるかが問われよう。
(初出『市民の意見』第110号 2008・10)
【単行本好評発売中!】全国書店もしくはネット書店にてご購入ください。