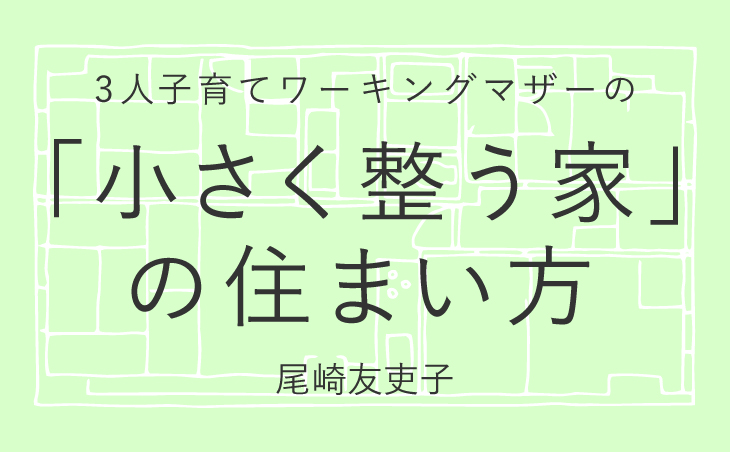第4回
映画を観ていたころ
2017.08.07更新
長年ブックデザイナーとして活動し映画やデザインの評論でも知られる著者が、グローバル化する政治経済や情報環境、災害や紛争などによって激しく揺さぶられる現代社会を、デザイナーならではの視点からするどく捉えます。
「目次」はこちら
20歳代から30歳代にかけて、憑かれたように、年間数百本の映画を観つづけた。1970年代がおもだったろうか。休日は、深夜もふくめて、コカ・コーラでアンパンを胃袋に流しこみながら、映画館と古本屋を飛び石づたいにハシゴしていた。当時は、封切映画館でも2本立てが当たり前だったので、オールナイト興行で5本、新作を2軒こなせば、1週間に9本を観ることになり、年間鑑賞数が400本を超える勘定だ。上映中に入館し映画の途中から見始めるのは平気だったし、つまらなければ途中で出る決断も早かった。
インターネットはおろか、『ぴあ』のような情報誌もなく、どこの映画館でなにを上映しているかは、『東京新聞』の金曜日夕刊に載る広告が頼りだった。マキノ雅弘監督の名作「次郎長三国志」シリーズ全9本を見なければと必死の時期があり、その第5作『殴込み甲州路』(1953年)の文字を新聞広告で見つけ、勇んで川崎まで出かけていったところ、『甲州路殴り込み』(マキノ雅弘監督、1965年)という、べつの次郎長もので落胆した記憶がある。
当時は、ビデオといった便利な記録媒体もなく、映画を観る行為は1回限りの出会いだった。いちど観ただけで映画批評を書けるくらいに、セリフや身振りなどの細部を記憶しなければならなかった。映画館を出るやいなやメモを取るクセもついた。記憶のとどめかたや情報の整理術は、このころの映画体験がもとになってつくられたのかもしれない。学術的ではなく、きわめて娯楽映画的なのだ。
スクリーンに接する回数は、400本が300本へ、300本が200本へとじょじょに減り、いまでは年間せいぜい50本くらいだが、数多くの映画を観るなかで、身に染みてわかったことがある。「当たりは、10本に1本くらいしかない」。1本の当たりに出あうためには、10本を観なければならない。さらに、傑作と断言できるような1本に遭遇するには100本を観る覚悟が必要だ。確率の問題ではない。10本、100本と観つづけることで、自分にとっての当たりを見つけられるようなのだ。
昨今、ことに若いひとたちの映画の見方は、失望するのを怖れているかのようだ。映画ばかりではなく、本選びでも、失敗を避けようと、世評をまず調べる。結果、評判のよい映画や本だけに客が集中する、いわゆる「1本かぶり」の現象が起こる。買い物全般にも言えることだろう。失敗を避けようとするのは、わたしをふくめて年配者も同様なのだが、若いひとこそ、下品、グロテスク、愚作と指弾された作品から、自分にとっての当たりを見つけなければならないのではないか。当たりの体系が自分をかたちづくるからだ。
「1本のために10本を観る」との原則は、「10本のうち9本はゴミだ」とも言い直せよう。「10本のうち9本はゴミだ」との心得は、観客=ユーザー=消費者として獲得されたものだが、その断言は、作り手のがわにも反転する。デザイナーである自分がつくりだす「10本のうち9本はゴミ」かもしれないと。自分で立てた観客の原則が、わたしを貫くのだ。
多くの成人は、消費者であると同時になにごとかの作り手や送り手でもある。ひとは、サービスを受けとる反面、サービスを提供する局面をもつ。純粋な消費者などどこにもいない。「10本のうち9本はゴミ」との視点は、ユーザーの立場を声高に主張するのではなく、作り手に立ちうる自分を見直す視点でもある。駄作には駄作と言わざるをえないが、他者を斬る刃は、自身をも切る。ゴミを生みださないよう、丹念なしごとをするほかない。
(初出『市民の意見』第128号 2011・10)
【単行本好評発売中!】全国書店もしくはネット書店にてご購入ください。