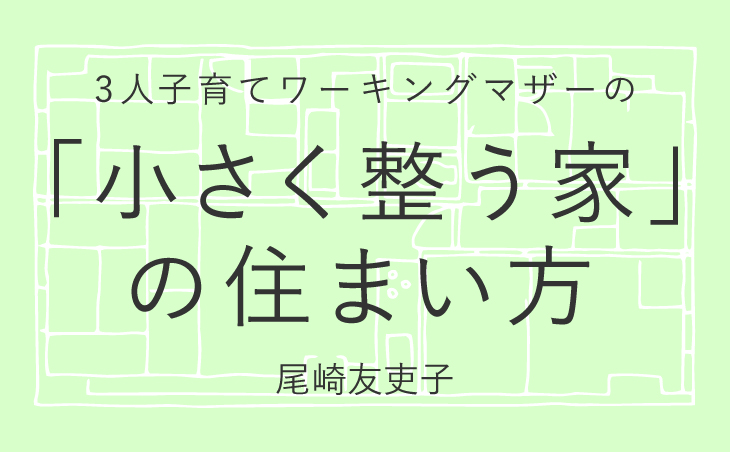第5回
パソコンの終焉
2017.08.10更新
長年ブックデザイナーとして活動し映画やデザインの評論でも知られる著者が、グローバル化する政治経済や情報環境、災害や紛争などによって激しく揺さぶられる現代社会を、デザイナーならではの視点からするどく捉えます。
「目次」はこちら
平凡社の編集者だった二宮隆洋さんが、2012年4月に亡くなった。60歳だった。「中世思想原典集成」や「ヴァールブルク・コレクション」、「エラノス叢書」など、1980年代から90年代にかけて、およそ200冊の翻訳人文書を世に送りだした。
さいきん、現役の優秀な編集者の訃報にたびたび接する。編集者は、ただちには補充できない。編集者の優秀さを定義するのも困難だ。編集者ひとりずつが編みだした優秀さなのだろう。その死は、過労のせいもあるだろう。編集者を喪失するたびに、出版界はだいじょうぶなのかと心配になる。
先日、「二宮さんを偲ぶ会」が開かれ、二宮さんの仕事の全容をあらためて知った。ことに、2000年代の活動ぶりがわかり、「手もとに揃えておかないといけない」と思ったのが、中央公論新社版『哲学の歴史』全13巻(2007─08年)だ。さっそくアマゾンで、すでに所有していた4巻と11巻をのぞくほかの巻を注文した。全巻が揃ってホッとしたころ、アマゾンからメールがくる。「4巻と11巻を買いませんか」。つまりアマゾンは、わたしが『哲学の歴史』をほぼ全巻揃えたのを知った。そのうえで、注文されていない4巻と11巻を勧めてきたのだ。
新刊と古書を取り交ぜながら数回に分けてオーダーされたデータを縒りあわせて、「4巻と11巻だけを注文していない」事実を浮上させ、さらに、「全13巻のうち11冊を注文したのだから、全巻を揃えたいはずだ」との予測を働かせ、先回りしてくる。
このとき抱いた気持ちは、いささか複雑だ。「よけいなお世話だ」とは思いつつ、自分のすがたを鏡で見ている気になった。わたしの検索や注文の履歴を知るアマゾンとのやりとりは、たしかに「自分好みにパーソナライズ」されている。
だれもが、「目の前を流れていく膨大な情報を整理しきれない」と感じている。編集者で評論家の津野海太郎は、論文「紙の危機と電子本の役割」(『希望の灯』ボイジャー、2012年)で、「1850年に世界で出版された本のかずは5万点。それが100年後の1950年には25万点にふえ、2000年には100万点です。いまはもうそれを大きく超えてるんじゃないですか」と書き、そのうえで、「紙によって支えられてきた繁栄が、紙の力を越えて自壊しかけている」と記す。「紙によって支えられてきた繁栄」とは、大量の文書に支えられている官僚主義をも指す。
話を紙の本にかぎるとして、アマゾンとのやりとりは、情報の「パーソナライズ」をアマゾンに委ねている事態にほかならない。委託の背面には、「本の氾濫に対処できない」とのユーザーの思いがある。「グーグルに代表される検索エンジンの価値は、(中略)「情報量の減少」にこそ存在している」(東浩紀『一般意志2・0 ルソー、フロイト、グーグル』講談社、2011年)。
1990年ころ、アップルコンピュータが机上に到来した。マシンそれ自体は使い道をなんら指示してくれない、空っぽの器だった。使途を自分で考え、ソフトをインストールし、「個人化」していくほかなかった。パーソナルコンピュータ、いわゆるパソコンとの出会いである。新しいマシンが届くたびに、動かすのに1週間くらいかかっていたと記憶する。現在の「パーソナライズ」が、パソコン時代の個人化とまったくちがうのは、個人化を検索エンジンのフィルタリング、いわば他者に委ねている点だ。「膨大な個人情報」を「ビッグデータ」と呼ぶならば、それを扱う巨大な市場がすでに鳴動している。個人の放棄である。パソコンの終焉にほかならない。
本なしでは生きていけないとする津野は、「その一方で私は、本というものを、いつ消えてなくなるかもしれない、はかない存在としても感じている」(同前)と告げる。本を読む個人がいなくなるとき、本は消えるのかもしれない。二宮さんは、あるインタビューに応じて、こう話している。「旧弊な悪しきアカデミズムはどんどん壊していく必要がありますし」、「敬意に値するアカデミズムは創りあげていかないといけない」、「解体と再建というのを同時にやらないといけない」(「二、三千人の基礎的な読者がいるかぎり、私の仕事は続けられる」『ちょっといっさつ』第22号、大阪市大生協・書評委員会、1994年)。個人が解体されるスピードは速い。再建は間に合うのだろうか。
(初出『atプラス』第13号 2012・8)
【単行本好評発売中!】全国書店もしくはネット書店にてご購入ください。