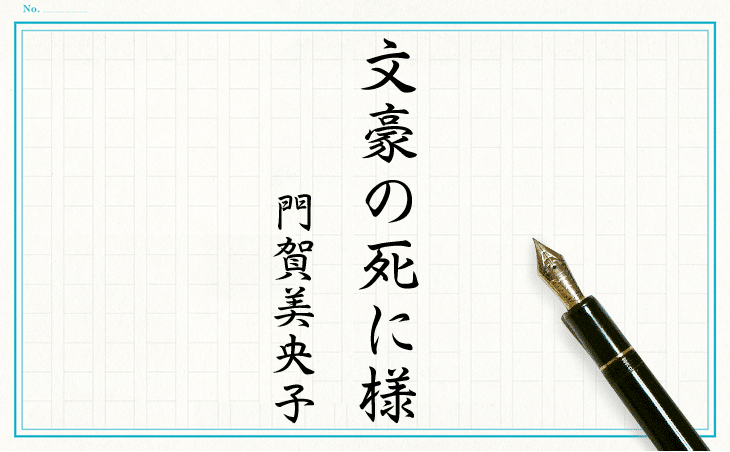第1回
二葉亭四迷 ―元祖意識高い系が迎えた孤独な死
2019.01.25更新
『文豪』という言葉にどんな印象がありますか? ここ数年、文豪をモチーフにしたゲームやアニメの影響による『文豪ブーム』で、文豪の人柄に関心が高まっています。この連載では、文豪の末期、すなわち『死』に注目をします。芸術家は追い立てられるように生きて薄命な印象がありますが、文豪はどうなのでしょうか。『死』を見つめることは『生』を見つめること。それぞれの『死』から、多様な生き方を見ていきます。
「目次」はこちら
二葉亭四迷(ふたばてい・しめい)
小説家・翻訳家・ジャーナリスト。元治元(1864)年、江戸生まれ。明治41(1909)年、ベンガル湾洋上にて病死。享年45。代表作は『浮草』『平凡』。
二葉亭四迷と聞けばまずは「言文一致(注1)」が連想される。だが、それ以上の情報についてはどうだろう。
ほとんどの教科書は、明治期における言文一致運動の先駆者と位置づける程度で、代表作『浮雲』の冒頭がちょろっとでも紹介されていたら御の字である。
ところが、その冒頭がいけない。
千早振る神無月ももはや跡二日の余波となッた二十八日の午後三時頃に、神田見附の内より、塗渡とわたる蟻、散る蜘蛛の子とうようよぞよぞよ沸出いでて来るのは、孰も顋を気にし給たまう方々。
え、これ、江戸期の戯作とどう違うの? と首をかしげたくなる名調子で、これで言文一致でございっていわれてもなあ、と思わないだろうか。
思ったなら、次の文章を読んでみてほしい。
私は、まア、スケプティスト(注2)(懐疑派)だ。第一ロジックという事が馬鹿々々しい。Law of thoughtは人間の頭に上る思想をアジャストするだけで、その人間のリアル・ライフとどれだけの関係があるか。心理学上、人間は思想だけじゃない。メンタル・エナジーの現われ方には情もあれば知も意もある。(中略)伴し「Why?」という観念が出て来ると、私はそれに依頼されなくなる。心理学上のコンシャスネス(注3)(識覚)について云って見ても、識覚に上らぬ働き(アンダー、コンシャス、ウォーク)がいくらあるかしれぬ。リフレクティブ・アクション(注4)なぞはその卑近の一例で、こんな心持ちがする……云々と云う事もまたその働きだ。(「私は懐疑派だ」より)
読みやすいように英語のカタカナ表記を現代風もしくは英語表記に変え、一部の漢字をひらがなに置き換えはしているが、他は何にも手を加えていない。
カタカナ語の乱用、妙な饒舌体、今一つ要点が伝わってこない文章……。
一体どこの意識高い系ブログかしら、という感じだが、これは四迷が明治41(1908)年、つまり『浮雲』から21年後にして、死を迎える当年に書いたエッセイ中の一文なのだ。
「意識高い系」とは、壮大な夢を語るわりには空回りしがちな若者を揶揄する現代のスラングだ。彼はブログやSNSでの自分語りが大好物。俺様理論を饒舌に振りかざし、日本語より外来語を尊ぶ。つまり、引用文のテイストによく似ているのだ。
明治時代の知識階級は、たった20年でこのような文体にたどり着いていた。
そして、新文体誕生の立役者だった二葉亭四迷は、まさに「元祖意識高い系」人間だったのである。
迷走しまくる四迷の生涯
本名は長谷川辰之助。元治元(1864)年、つまり大政奉還まであと3年に迫っていた江戸で、尾張藩下級武士の一人息子として生まれた。維新の波に巻き込まれ、幼少時は名古屋、東京、松江などを転々として育つ。
そんな中、明治8(1875)年、四迷11歳の時に、彼の生涯を決定づける重大事件が起こった。日本とロシア帝国の間で「樺太・千島交換条約」が結ばれたのである。
ロシアと日本の国境は長らく曖昧だったが、現地のロシア人と日本人の間で争いが頻発したため、決定的な対立を避けるべく樺太をロシア領、千島列島を日本領と定めた。新生直後の日本政府に大国ロシアと戦う力なんぞあるはずがないから、賢明な策だったといえる。
しかし、国民の目には「弱腰政府の領土放棄」と映り、世論は沸騰。帝国主義が高まった。そんな空気の中で、辰之助少年はこう考えたのだ。
将来日本の深憂大患となるのはロシアに極ってる。こいつ今の間にどうにか防いで置かなきゃいかんわい……それにはロシア語が一番に必要だ。(明治41年 「予が半生の懺悔」より)
子供にしては意識が高い。
そこで外国語学校の露語科に入学したのだが、学習過程においてロシア文学と出会ってしまったことで彼の運命は変わってしまう。
19世紀、ロシア文学はドストエフスキーやトルストイなどの大文豪を次々と輩出する黄金期を迎えていた。ロシア革命前夜、もはや覆い隠せなくなった社会的矛盾、そして近代ならではの人生の諸問題に、感性と知性を武器に正面から挑む文学者たちの作品に、初心な四迷はイチコロで参ってしまった。
結果、彼は徹底した文学「信」者になったのである。
もう文学しか眼中にない。政治などどうでもいい。人生あっての文学ではなくて、文学あっての人生のような心持で、文学界以外の人生には殆ど何の注意も払わなかった
(明治40年 「平凡」より)
あれ、ロシアとの戦いはどこへ?
四迷の人生には、こんな感じの極端な転向が何度も現れる。
人に対しても、職に関しても、いきなり気持ちに火が点いて猪突猛進に突き進む。ところが、しばらくして壁にぶつかると途端に熱が冷め、むしろ悪い所ばかりが目に付くようになる。そして、何もかもが嫌になって途中で投げ出してしまう。
あれほど燃えさかっていた文学熱も、この過程で冷めていった。処女作「浮雲」は自らの脳内にあった理想の文学に届かず、己の才能に絶望した末に筆を折り、未完となってしまったのだ。
ある種の逃げ癖が、彼にはあった。
さらに、「正直」(今だと誠実ぐらいのニュアンス)を理想の生き方とし、社会問題に関わるべくあえて下層階級の人々と交流したり、友のためなら何肌でも脱ぐような侠気を見せながらも、女癖が悪く、家族には冷淡だった。
頭でっかちの男に多いパターンだ。口では立派なことを言うが、実行が伴わない。まるっきり、えらい人がいう「ダメな現代の若者」あるいは「意識高い系」そのものである。
掴んだチャンスも泡と消え
文学から逃げた四迷は、官報の記者やロシア語教授など様々な職業に就いた。しかし、最初の勤めこそ十年もったが、その後は短いスパンで転職を繰り返していく。
頭がよく、努力家でもある四迷は、どんな職でも最初はそれなりに成功する。頑な性格ながらも社会性はあるので、同僚ともそれなりに仲良くやれる。
ところが、ちょっとでもつまずくと、すぐに心が折れて現実逃避してしまうのだ。時には家族を養うことさえ放棄してしまう。当然、両親には事あるごとに愚痴られ嘆かれ、妻には離縁された。
だからといって、世をすねることもできなかったのが彼のおもしろいところである。自己分析力が滅法高かったせいで、自分の不遇は誰のせいでもありゃしない、というのを重々承知していたのだ。他人や社会に安易な責任転嫁をしないところは、四迷の美質といえるだろう。
「どうにも自分ながら情ない、愛想の尽きた下らない人間だと熟々自覚する。そこで苦悶の極、自ら放った声が、くたばって仕舞え(二葉亭四迷)! (「予が半生の懺悔」より)
半端な我が身に嫌気がさし、事あるごとに悶々とする。そして、抑うつ状態に陥る。30代に入り、この状態は改善するどころかますますひどくなっていった。理想と現実の乖離への苦悩は、年とともに薄れるどころか強固になったのだ。
「ジレンマ! ジレンマ! こいつでまた幾ら苦しめられたか知れん。これが人生観についての苦悶を呼起した大動機になってるんだ。即ちこんな苦痛の中に住んでて、人生はどうなるだろう、人生の目的は何だろうなぞという問題に、思想上から自然に走っていく。実に苦しい。従ってゆっくりと其問題を研究する余裕がなく、ただ断腸の思ばかりしていた。(「予が半生の懺悔」より)
なんともしんどそうな人生である。
しかし、38歳の時、ようやく大陸に渡って日本のために仕事をするという幼き日の大志を果たすチャンスを得た。四迷は意気揚々、得意満面だった。
ところが、ここでも夢想の前に現実が立ちはだかる。日露戦争を前にした時局の悪化は、想像以上だったのだ。もともとほぼノープランでの渡航だった上、現地の厳しい事情に己の方向性を見失い、四迷の仕事はまたもや尻切れトンボに終わってしまう。
40歳を前にして家族を捨てる覚悟までして自分探しの旅に出かけたのに、何もできずにおめおめ戻ってきた元文学者。
これほどイタイ存在もない。
しかし、四迷はそれでも大志をあきらめていなかった。
私は、奮闘さえすれば何となく生き甲斐があるような心持がするんだ。(「予が半生の懺悔」より)
「まだそんなことを言っているのか、お前は」という話だが、この懲りなさ加減に、私はなんとなくシンパシーを感じてしまう。高すぎる理想を掲げ、己の能力を超えた夢を追わずにいられない四迷の愚かさは、とても愛おしい。
小説家・二葉亭四迷の復活
帰国後、あやうく無職中年になりかけていたところを、四迷を高く評価する人物に拾われて大阪朝日新聞に入社した。だが、やっぱりまともに勤まらなかった。書いた記事がまったく採用されないのだ。
それもそのはず、四迷は社が求める一般向けの読み物ではなく、官僚の報告書のような四角四面の分析記事ばかりを書いた。専門家には役立つ立派な内容だったそうだが、市井の読者が喜ぶたぐいのものではない。ニーズに合わない記事など、社にしてみればゴミ同然だ。
一方、四迷としては、おもしろおかしいだけの記事を書くなど沽券に関わる。四迷の辞書には「忖度」などないのである。
結果、最終的な落としどころになったのは、新聞連載小説の執筆だった。
実のところ、四迷を招き入れた人物が期待していたのは、これだったのだ。大陸帰りの記者・長谷川辰之助の活躍ではなく、伝説の小説家・二葉亭四迷のリブートこそ望みだったのである。
まんまと思惑に踊らされたわけだが、長らく受けた恩を無碍にはできない。当初はロシア文学の翻訳でお茶を濁すつもりだったが、結局は逃れられなくなり、死の4年前に「其面影」、3年前に「平凡」を執筆した。両作は文壇に比較的好意的に迎え入れられ、四迷は何とか面目をほどこすことになる。
二度目の大陸行は、半ばこのご褒美として決まったようなものだった。しかも、今度はロシアの中心たるペテルブルグに新聞社の特派員という立場で行くことができる。ほぼ大陸浪人だった前回とは雲泥の差だ。
ようやく人生最高の時を迎えた四迷の高揚感は、「入露記」という紀行文によく表れている。自他ともに認める「狷介(注5)」な性格である四迷が、進んで人と交わり、会話を試み、街歩きに勤しんでいるのだ。
僕は愉快々々 たまらない(「入露記」より)
偽らざる心境だろう。苦節四十年にして、ようやく理想の環境を手にいられたのだ。誰だってテンション最高潮になるに決まっている。
だが、ナチュラル・ハイは長くは続かなかった。予想外に物価高だったロシアでの経済的不安、うまくいかない取材活動、厳しい気候、そして直面した露骨な人種差別。
僕は元来散歩嫌いの男だが、ここへ来てから急に散歩好きになったのぢやない、部屋の構造が冬向一方だから、空気の流通が頗る宜しくないので、外出して比較的新鮮の空気を呼吸せざるを得んのだ、しかるに外出すると、毎度悪口を言われる、外出の方面によつては、出る度といつてもよろしい。(「露都雑記」より)
「入露記」から八ヶ月後に書かれたエッセイ「露都雑記」には、数か月前のアドレナリン駆け巡るような生き生きとした躍動感はすでに失われている。
ペテルブルグには、友も家族もいなかった。早々に現地妻らしき女性をこしらえてはいるものの、完全な慰めにはならなかったらしい。むしろ、彼女との交際を通して、自らが異人であることを否が応でも思い知らされていたのではないだろうか。
四迷の心身は衰弱していった。そして、死病を得た。肺尖カタル(注6)だ。
直接の原因は二月に雪中に挙行されたウラジミール大公(注7)の葬儀に参列して体調を崩したことだったが、知らぬ間に少しずつ肺結核に侵されていたらしい。一か月以上高熱が続き、周囲は四迷に帰国を勧めるようになった。会社としても取材できない特派員などいらない。
だが、四迷は頑なに抵抗した。心中にはようやく掴んだ再チャンスをものにできず、中途半端で終わってしまう自分への絶望があったのではないかと思う。
また、何もできないままだ。
どの面を下げて帰れと?
しかし、病状は悪化する一方で、とうとう帰国を承諾せざるをえなくなった。無事に日本にたどり着ける保証はない旅だ。四迷は出発の二週間ほど前に遺言状をしたためている。
一 余死せば朝日新聞社より多少の涙金渡るべし
一 此金を受取りたる時は年齢に拘らず平均に六人の家族に頭割りにすべし例せば社より六百円渡りたる時は頭割にして一人の所得百円となる計算也
一 此分配法ニ異議ありとも変更を許さず
右之通
明治四十二年三月二十二日 露都病院にて
「遺族善後策」と題する書簡とともに残された二通の文書にはほぼ事務的なことしか書かれていない。社会への高い関心とは裏腹に、生涯変わらなかった家族への無関心と無責任が見え隠れする。
いずれにせよ、彼自身生きての帰国を半ばあきらめていたに違いない。事実、彼の体力は長旅に耐えられるものではなかった。それでもマルセイユまではなんとかもった。しかし、南方の海の炎熱が、四迷の体から生命力を奪っていった。
四迷の絶筆は、1909年4月28日朝に書かれたと思しき自らの体温の記録だ。それから12日後の5月10日午後5時15分、大きな理想を持って夢を追いながら、一度も追いつくことができなかった男は、ベンガル湾沖で息を引き取った。
ロシアでの客死でもない。故郷での往生でもない。旅の途中で命を落としたのは、何をしても半端だった彼らしい死に様だったのかもしれない。男一匹の人生としては、無駄死にだったともいえる。
だが、徒手空拳のまま果敢に切り開いていった言文一致運動そのものは他の人々の手によって大きく進展し、日本の近代文学のみならず、教育や文化を劇的に変容させた。
熱しやすい単純さを以て、理想に向かいがむしゃらに突き進んだ彼の行動は、無駄どころか、大輪の花を咲かせたのだ。
その意味において、彼は確かに文豪であり、偉人のひとりに数えられるべき人だと、私は思うのである。
注1:言文一致
書き言葉と話し言葉を一致させること。日本では江戸時代まで普段の会話に使われる言葉(口語)と文章として書き表す言葉(文語)に大きな違いがあった。明治時代になり、「西洋文明に近づこう!」ムーブメントである改良運動が起こると、その一環として日本語表記の大幅な見直しが叫ばれるようになった。明治19(1886)年に国学者・物集高見が『言文一致』を上梓して理論面を先導、それに呼応する形で二葉亭四迷や山田美妙などが言文一致を模索する文学作品を発表していった。文体が完成したのは四半世紀が経った明治末頃。ただし、公式文書などでは第二次世界大戦直後まで文語体が使われていた。
←戻る
注2:スケプティスト[skeptist]
ヘレニズム時代に「たとえこの世に『真理』なるものが存在したとしても、人間の言葉ではそれを認識することはできない」とする懐疑論を唱えた哲学の一学派。紀元前4世紀前後にギリシャの哲学者ピュロンによって創始された。ピュロンは、「人間は、起こった現象を受容することだけが可能であり、ものの本性それ自体を知ることはできない。よって、本性を探ることは諦め、平常不動心を持って日常を送り、心を煩わさないようにすべきだ」と考えた。こうした懐疑派が起こった背景には、細分化した哲学界の相互対立やアレクサンドロス大王の死によって混乱した社会状況があったとされる。
←戻る
注3:コンシャスネス[consciousness]
意識を持っていること。自覚、心象。
←戻る
注4:リフレクティブ・アクション[reflective action]
深い思索、思慮。内省的な心の動き。
←戻る
注5:狷介
頑固で人と妥協せず、他人に心を開かない様子。
←戻る
注6:肺尖カタル
肺上部に発生する肺結核の初期症状。
←戻る
注7:ウラジーミル大公
ウラジーミル・アレクサンドロヴィチ(Владимир Александрович, 1847年 – 1909年) ロシア皇帝アレクサンドル二世の三男、アレクサンドル三世の弟。
←戻る