第4回
森鴎外―死の床で「馬鹿らしい」と叫んだ人
2019.03.08更新
『文豪』という言葉にどんな印象がありますか? ここ数年、文豪をモチーフにしたゲームやアニメの影響による『文豪ブーム』で、文豪の人柄に関心が高まっています。この連載では、文豪の末期、すなわち『死』に注目をします。芸術家は追い立てられるように生きて薄命な印象がありますが、文豪はどうなのでしょうか。『死』を見つめることは『生』を見つめること。それぞれの『死』から、多様な生き方を見ていきます。
「目次」はこちら
森鴎外(もり・おうがい)
小説家・翻訳家・評論家・陸軍軍医。文久2(1862)年、石見国津和野町生まれ。大正11(1922)年、東京・文京区にあった自宅で病死。享年60。代表作に『舞姫』『高瀬舟』など多数。
森鴎外。
The 文豪である。
貧しい下級士族の生まれながらも、学問によって立身出世を果たし、文学者として後世に名を残した人である。近代日本の価値観から見ると、お手本のような人生だった。
ところが、だ。
その死に際のエピソードを眺めてみると、どうやら彼は自分の人生を大団円とは考えていなかったようなのだ。
証拠は二つある。
一つは死の二日前、心から信頼していた親友に口述筆記させた遺言。
もう一つは死の床で発したうわ言。
文学史上のミステリーとしてさまざまに語られてきた「鴎外の死」について、この二つの鍵を手がかりに謎に迫っていきたい。
死は一切を打ち切る重大事件なり
まず、遺言状から見ていこう。それほど長くないので、全文を引用することにする。なお、原文は漢字とカタカナによって書かれているが、読みやすいようにカタカナはひらがなに、旧仮名遣いを現代仮名遣いに改め、適宜濁点や句読点を加えた(以下、他の引用文も同様)。
余は少年の時より老死に至るまで、一切秘密無く交際したる友は賀古鶴所君なり。ここに死に臨んで賀古君の一筆を煩わす。
死は一切を打ち切る重大事件なり。奈何なる官憲威かと雖、此に反抗する事を得ずと信ず。
宮内省陸軍皆縁故あれども、生死別るる瞬間、あらゆる外形的取扱いを辞す。森林太郎として死せんとす。
墓は森林太郎墓の外、一字も掘るべからず。書は中村不折に依託し、宮内省陸軍の栄典は絶対に取りやめを請う。手続はそれぞれあるべし。これ唯一の友人に云い殘すものにして何人の容喙(注1)をも許さず。
すでに自ら筆を執る力さえなくなっていた鴎外が、学生時代からの親友である賀古鶴所(かこ・つるど)に代筆を頼んで残した一文だ。遺言とはいえ、相続など事務的な手続きについては一切触れず、自身の死後処理にのみ言及している。
特徴的なのは、250字余りの短い文章の中に「森林太郎として死せん」という文言が二度も出てくることだ。林太郎とは鴎外の本名で、一度目の頭についている「石見人」というのは、鴎外が石見国、つまり現在の島根県南西地方にある津和野出身であることを示している。
すんなり読めば、本状は「自分はあらゆる名利を捨てて、石見の国で生まれた森林太郎という一個人と死ぬのである」という決意表明であり、教科書的な解釈だと「一切の名利を捨てて無に帰っていこうとする鴎外晩年の高い境地を示すもの」ということになる。
しかし、どうもただ「高い境地を示すもの」とは思えない何かが、この文章にはある。昇華しきれない強い情念が見え隠れしているのだ。
これは何も私だけの思い込みではない。同様の解釈が多くの文学者や研究者から提出されてきた。
山田風太郎の『人間臨終図鑑』には、四人の文学者の見方が記されている。
ドイツ文学者で鴎外の評伝を書いた高橋義孝は「鴎外の自負に相当する地位、名誉を与えられなかったことに対する悲しみの表白」。
小説家の中野重治は「この遺言の対象は強大なる『官憲威力』そのものであって、それに対する反噬(注2)である」。
同じく小説家の松本清張が「鴎外をしてついに疎外者の運命を感ぜしめずにおかなかった『長州閥(注3)』への復讐の語」だとした。
そして、山風本人は「呪詛と悲哀に満ちたふしぎな遺言」と評している。
また、鴎外の専門家である近代文学研究者の山崎一穎は、「<公>的な鴎外の遺言の底流には、ある劇しさがある。不満の意がある。咆哮する獅子の荒ぶる心がある」とちょっと大仰な表現を用いた上で、私人として「父祖の地・先哲文人の地・石見に帰る」決意を表したのだとする見解を披露している。
まあ、要するにみんな「鴎外は自らを不遇の人として考え、その不満を抱えたまま死んでいった」と考えているのだ。
不遇ねえ……。帝国陸軍の軍医としては最高位である陸軍省医務局長まで昇り、退職後は宮内省帝室博物館総長兼図書頭、帝国美術院初代院長などを務め、死の直前には宮中から従二位の位が贈られている。社会的には立派な成功者だ。その上、近代文学の巨星として輝き、今に至るまで名を残しているのだから、十分な人生だったろうと私のような生涯一ぺーぺーが決定している人間は思うのだが、自らを強く深く恃んでいた鴎外には不足だったらしい。
だが、彼の死に際を見ていくと、鴎外が不満を抱えていたのは、必ずしも社会的評価に対してのみだったとは思えないのだ。もっと大きな何かが心中にあったようなのである。
そのヒントになるのが二つ目の鍵だ。これは危篤になる少し前に突然大声で発したという言葉なのだが、なんとも生々しいのでそのまま引用しよう。
意識が不明になって、御危篤に陥る一寸前の夜のことでした。枕元に侍していた私は、突然、博士の大きな声に驚かされました。
「馬鹿らしい! 馬鹿らしい!」
そのお声は全く突然で、そして大きく太く高く、それが臨終の床にあるお方の超えとは思われないほど力のこもった、そして明晰なはっきりとしたお声でした。
「どうかなさいましたか。」
私は静かにお枕元にいざり寄って、お顔色を覗きましたが、それきりお答えはなくて、うとうとと眠を嗜むで居られる御様子でした。
(『家庭雑誌』第8巻11号 伊藤久子「感激に満ちた二週日 文豪森鴎外先生の臨終に侍するの記」より)
人格者で知られた大文豪、末期の言葉としてはなかなか俗っぽい。それゆえか、山崎一穎はこの言葉を「謎である」で片付け、さほど深くは突っ込んでいない。
だが、私はこの言葉こそ、鴎外の人生そのものを象徴するリフレインだったと思うのだ。
同時に、謎というほどのものではない。額面通りに受け取っていい。
要するに、鴎外は死に直面して本気で馬鹿らしくなったのだ。
なにが。
己の人生すべてが。
「家」のためにあった一生
鴎外は文久二(1862)年、明治を迎える六年前に、津和野の下級武士の子として生まれた。森家は代々藩主に仕える家系だが、祖父も祖母も他家から入った人なので、鴎外と森家の祖に血縁関係はない。とはいえ、不妊治療もなく人も簡単に早世した時代には、家を存続させるための夫婦養子はよくあることだった。極端な血縁主義に偏りつつある現代の家族観とは相当異なる。
しかし、なんとか生まれた男児は育たず、結局は第二子の峰子が吉次静男を婿養子に迎えることになった。父・静男を鴎外は自伝的小説「本家分家」の中で、このように描写いている。
壻入をした博士の父は、周防国の豪家の息子である。こんな風に他国のものが来て、吉川家を継ぐのは、当時髪を剃って十徳を着る医者の家へは、藩中のものが養子や嫁に来ることを嫌っていたからである。此人は医術を教へられて、藩中で肩を並べる人のない程の技倆にはなったが、世故に疎い、名利の念の薄い人であつた。それを家つきの娘たる、博士の母は傍から助けて、柔に勧めもし、強く諫めもして、夫に過失のないようにしていた。
藩内で微妙な立ち位置にいた森一族は立身出世欲が極端に強かった。狭い藩社会において、承認欲求に飢えていたのだろう。そんな人々に囲まれてもなおマイペースを保った静男は、別の意味で強い人だったのかもしれない。跡取り娘として大事に育てられた峰子に尻を叩かれながらも、相性はまずまずだったようだ。
そんな中に生まれたのが林太郎、後の鴎外だった。
嫡子の誕生である。
一家、いや一族にとって、林太郎は燦然と輝く希望の星だった。当然、過大な期待が一身に集まる。特に絵に描いたような「封建時代の良妻賢母」である峰子とその母・清子の意気込みは半端ではなかった。林太郎の立身出世を成功させ、森家の家名を上げる。それが母娘畢生の事業となったのだ。鴎外の末子・類はその様子を「林さあ(父、森林太郎)を偉くする為めには寒くても、饑じくても、結束して事に当たってきた一族」(「鴎外の子供たち」より)と表現している。
とにかく、二人は林太郎を掌中の珠として育てながらも、武家の男子として恥ずかしくない気概と教養、そして出世のための学問を身につけさせようとした。
鴎外の自伝的小説である『ヰタ・セクスアリス』にはこんな一節がある。
六つの時であった。(中略)お父様は殿様と御一しょに東京に出ていらっしゃる。お母様が、湛ももう大分大きくなったから、学校に遣る前から、少しずつ物を教えて置かねばならないというので、毎朝仮名を教えたり、手習をさせたりして下さる。
これだけでも教育熱心な母である。しかし、実際には仮名の手習いどころではなかった。六歳でいきなり儒者について漢籍の勉強を始め、八歳で藩校に入れられたのである。さらに九歳になると父からオランダ語を習うようになった。とんでもない英才教育だ。
とはいえ、我が子に無理をさせるだけの二人ではなかった。鴎外の妹である小金井喜美子は、後にこう回想している。
祖母君物縫いなどし給う傍らの部屋に小机すえて、假名附きの四書手に持ちて復習させするを役とし、自らも蔵なる書ども取り出で、塵払いて読みなどし給えり。子を教うるには、先ず自ら学ぶべく思い立ち給いしなり。(中略)母君、若き程はか弱くいましつれば、物学びに通うこと難く、なおその頃の大方の習いとて、女子の文才と法師の髪は無くて事欠かずと、名高き白河の楽翁公(注4)さえのたわえりなど云う時代なれば、はかばかしく物も読み給わざりしを悔しがり給いて、今は力の及ぶ限り、読みも書きもしつべく勉め給いぬ。(「不忘記より」)
頭ごなしに「勉強しなさい!」と怒鳴りつけるだけの教育ママとは大違いだ。祖母と母に揃ってここまでやられたら、子としても身を入れざるを得まい。林太郎は懸命にがんばった。
幸運だったのは、林太郎がスパルタ教育にもついていけるだけの頭脳の持ち主だったことだ。特に記憶力は人並み外れて優れていた。おかげで、度が過ぎる詰め込みにもなんとか耐えられた。外で遊ぶよりは家で本を読んでいる方がいいという性情だったのも利した。
何よりよかったのは、父・静男が家庭内避難所として機能していたことだ。
父君は學校の事を、二人の兄君にも、己れにも、さのみきびしくはのたまわず、暗記物など覚えかねて部屋の片隅に泣きなどする折、通り掛かりては、おかっぱの頭やさしく撫でなどし給うに身にしみていと嬉しく、すり赤めたる目も乾きて、後ろ影を見送りぬ。(「不忘記より」)
鴎外自身も「この家庭では父が情を代表し、母が理を代表し、父が子供をあまやかし、母がそれを戒めると云ふ工合であつた。」(「本家分家」より)というぐらいだから、烈女ふたりに管理される子を、父なりに気遣っていたらしい。
好条件が整っていたおかげで、林太郎は大きすぎる期待に潰されずにすんだのだ。しかし、立身出世という道しか歩ませてもらえない子供の心には、すでに影が差し始めていた。
僕はぼんやりしているかと思うと、又余り無邪気でない処のある子であった。(「ヰタ・セクスアリス」より)
努力が実るか、ついていけずに転落するか。薄刃の上を歩くような幼少時代だった。
初めての「寄り道」
さて、この調子で鴎外の生涯を見ていくと、いつまで経っても本題にたどり着かないので、学生時代のあれこれは端折る。
飛び級に次ぐ飛び級で19歳にして第一大学区医学校(現・東京大学医学部)本科を卒業した鴎外は、数ヶ月父を助けて開業医をやっていたが、やがて陸軍省に入省し、軍医となった。この進路を鴎外はどう感じていたか。
どうやら本音では文学者になりたかったらしい。だが、それは自らの前半生と親の期待を一切無にするに等しい道だ。軍医になって洋行し、立身出世の緒を掴む。これしか選択肢はなかった。他家から入った父とは段違いの責任と期待が覆いかぶさっていたのだ。
20歳で父を差し置いて森家の実質的な家長として扱われるようになった鴎外。一見、年不相応な落ち着きのある青年だったが、なかなかどうして狷介な面も持ち合わせていた。
長男の森於菟は、「鴎外の母」というエッセイで次のように述べている。
一面神経質で弱気な所もあるが同時にややもすれば奔放不羈(注5)に流れる父
若い頃の父はあらゆる障壁を突破して学問に精進し、文学でも医学でも己れと説を異にする者には、たとえそれが先輩であろうと世に知名の学者であろうと、ひるまずに応酬するという風であり、家中のものが父の機嫌の悪い時には腫物に触るようにしていたらしい。
息子による鴎外評は実に正鵠を射ている。「一面神経質で弱気な所もあるが同時にややもすれば奔放不羈に流れる父」という面は、留学先で現地のドイツ人女性と関係を持ちながらも、妻になろうと来日した彼女を親族の言うがままに追い返した件(「舞姫」のモデルとなった事件)によく表れている。親の命で結婚した最初の妻にして於菟の母を、たった一年ほどで一方的に離縁したのも、この類(たぐい)だろう。
また、「たとえそれが先輩であろうと世に知名の学者であろうと、ひるまずに応酬するという風」に関しては、ドイツの地質学者・ナウマンに喧嘩をふっかけたり、坪内逍遥と「没理想論争」と呼ばれる文学論争を起こしたり、恩人ともいえるはずの西周を著作の中でこき下ろしたりと、枚挙に暇がないほど例がある。若い頃の喧嘩っ早さは有名だった。
ただし、我が性格のいびつさをはっきりと自覚していたのが鴎外の鴎外たる所以だ。自分は他人とは決して馴染みきれないことを意識していた。鴎外が50歳を前に書いた未完の自伝的小説「灰燼」に、極めて興味深い一節がある。少々長くなるが、鴎外の人生を知るには欠かせない部分なので、そのまま引用してみたい。
それと同時に節蔵は、自己と他人との心的生活に、大きな懸隔のあるのを知った。否、少くも知ったように思った。それは他人の生活が、兎角肯定的であって、その天分相応に、大小の別はあっても、何物かを肯定しているのに、自己はそれと同化することが出来ないと思うのである。そして節蔵は他人が何物かを肯定しているのを見る度に、「迷っているな」と思う。「気の毒な奴だな」と思う。「馬鹿だ」と思う。
そう云う風に、肯定即迷妄と観じて、世間の人が皆馬鹿に見えだしてから、節蔵の言語や動作は、前より一層うやうやしく、優しくなった。
「前より一層うやうやしく、優しくなった」。ここがポイントだ。
鴎外については、様々な人がその人となりを書き残しているが、中年以降の鴎外に関しては穏やかで大人物然としていたという点で一致している。
官僚として権力闘争に巻き込まれてとばっちりを受けたり、四十歳を過ぎて母の斡旋によって再婚した美人で癇癪持ちの若妻・志げが起こす嫁姑問題に直面したことで、人格が練れたためというのが一般的な見方だ。
家族も鴎外への敬愛を隠そうとしない。森一族は大変ユニークな人たちで、鴎外の弟妹・妻・子供たちがみな、鴎外について何かしら書き残しているのだが、揃いも揃ってその人格高潔なるを讃え、自分は鴎外から並々ならぬ愛情を注がれたと自慢している。ここまで身内褒めの激しい人たちはちょっと珍しい。それもこれも、決して身内を貶したり罵ったりしなかったという鴎外の人徳というものだろう。
しかし、長男の於菟と長女の茉莉は、少し冷静な視点を持っていた。
父から明晰な理性を受け継いだ於菟は、「昔家族の皆から機嫌をとられていた父が性格の円熟したこの頃になって、母と妻の間に立ち、日夜、言語挙動の末まで気をつかわねばならなかった事は皮肉とはいいきれぬ不幸であった」(「鴎外の母」より)と述べている。鴎外が死ぬまでの二十年間、旧弊で頑固な母とヒステリックでわがままな妻に挟まれて右往左往し、必ずしも泰然自若としていたわけでないことを暴露しているのだ。
一方、長女の茉莉は、もっと本質的なことに気づいていた。
私の頭に感じられても心には、体には、感じられて来ない父の愛、父の芸術の、高さ、匂い、味、細かさ、深さの、貴いようにまで優れているのに、どこか心(しん)がない、胸に来る温度がない、心臓にひびいて来る動悸の鼓動がない、というような所のある事」(「父の底のもの」より)
どこか心(しん)がない。「恋人のようだった」と表現するまで愛していた父を表現する言葉としては、ちょっと異様だ。しかし、間違ってはいなかったのだろう。怜悧な直感力を受け継いだ娘は、父の心の奥底に沈んでいる氷に気づいていたのだ。
おそらく、鴎外は、於菟が見たように家族の調和のために神経をすり減らす好人物ではあったが、人としての温かい気持ちを真には持ち得なかった人ではないかと思うのだ。
鴎外の目には、家族も親族も、職場や文壇の人々も、等しく馬鹿に見えていた。だからこそ、「うやうやしく、優しく」接することができた。それはある種ペットに抱く愛情に近いのかもしれない。人間は相手を馬鹿にしながも、深い愛情を持つことはできる。逆にいえば、どれほど愛していようが、必ずしも対等の存在として尊重するわけではない。
鈍感な人間は、こうした機微に気づかないだろう。だが、目の鋭い者、もしくは感受性の豊かな者は、その愛に混ざる侮蔑を嗅ぎつけてしまう。これは、なかなか恐ろしいことだ。悪妻とまで言われた志げの情緒不安定さも、そんな夫の心底を言葉にならずとも察知し、恐れを抱いていたのが原因かもしれない。
こうした胸の氷を、鴎外自身も自覚していた。
節蔵はいつの間にか、自分の周囲に崇拝者が出来るのを感じた。(中略)只奥さん(注・節蔵が下宿する家の奥さん)の本能が、節蔵のどこやらに、気味の悪い、冷たい処があるように感じている丈であった。(「灰燼」より)
どうも自分は人並はずれの冷澹な男であるらしい。(「ヰタ・セクスアリス」より)
子供の頃から一族の期待を一身に背負ってきた男は、ままならない人生に、ある時期は苛立ち、ある時期は諦観を抱いて生きていた。周囲の人間が、みんな馬鹿に見えた。馬鹿は同じ人間とは思えないから、むしろ優しくできた。だから、慕われ、尊敬され、ついには偶像化されるまでに至った。
そんないびつな自分を、鴎外は受け入れる他なかった。ごく一部の人間を除けば、だれもがまんまとごまかされてくれた。
だが、それは嬉しいことだろうか。私だったら、そうは思えない。
理性が薄れゆく中で
五十四歳で陸軍を退官した後は、いくつかの名誉職には就いたものの、ようやく好きなように好きなことをする時間を持てるようになった。
しかし、病はすでに鴎外に迫っていた。
彼の死因は公式では腎萎縮となっていたが、実際のところは肺結核だった。罹患の時期はかなり早かったらしい。於菟は、著作で於菟の母・登美子の実家が肺病の筋だったことに触れ、義母である志げに「パッパの結核はあなたの母親にうつされた」と告げられたことを記している。真偽の程は不明だが、鴎外の極端な医者嫌いは、このせいだったのかもしれない。当時の鴎外の立場であれば、結核であることは隠さねばならない不祥事だった。
しかし、若い頃は潜伏していた病も、加齢とともに抑えきれなくなった。
大正十(1921)年頃から、結核菌による腎不全と思しき兆候が出始めた。そして、この頃から、若い頃のような神経質でピリピリした鴎外が戻ってきた。病が、鴎外の仮面を剥がし始めたのだ。
理性が力を失っていく中で、心中に強く浮かび上がってきたのは、家族のため、一族のためにひたすら我慢してきた人生への悔恨だったのではないか。
親の期待以上の立身出世を果たし、歴史に名を残した一生。だがそれは何一つ思う通りにできなかった一生をも意味する。
つい昨年亡くなった俳優の樹木希林さんが、ジョン・エヴァレット・ミレーの「オフィーリア」に扮した姿に、『死ぬときぐらい好きにさせてよ』というキャッチコピーが乗っかる新聞広告が大変話題になった。
死を意識した鴎外の気分は、まさにこれだったように思うのだ。
遺言にわざわざ「石見人森林太郎として死せんと欲す」と書いたのは、東京に来て以降の人生にはなんの意味もなかった、と暗に示したのではないだろうか。
軍での経歴も、文名も、社会的地位も、もしかしたら「森一族」でさえ、もうどうでもよくなったのだろう。脳裏には、好きなように生きた静男の姿がよぎっていたのかもしれない。
死の床に就いた鴎外は一切の医療を拒否した。妻の半狂乱の懇願さえ、凍りついた心を溶かすことはできなかった。「一切を打ち切る重大事件」を前にして、彼が望んだことはたった一つだったのだ。
無駄な延命を拒否して、好きなように死んでいくこと。
偉人の最後の望みとしてはまことに慎ましやかだ。だが、「好きに死ぬ」ことが一族ファーストの人生を送らざるをえなかった男にとっては最高の贅沢だったのだろう。
理性の箍が失われるやいなや「馬鹿らしい」と連呼せざるをえなかったほどの抑圧に耐えきったことこそ、鴎外がやり遂げた一番の仕事であり、真に讃えられるべき功績なのかもしれない。
人間、好きなように生きなければ、幸せには死ねないものだ。つくづく、そう思う。

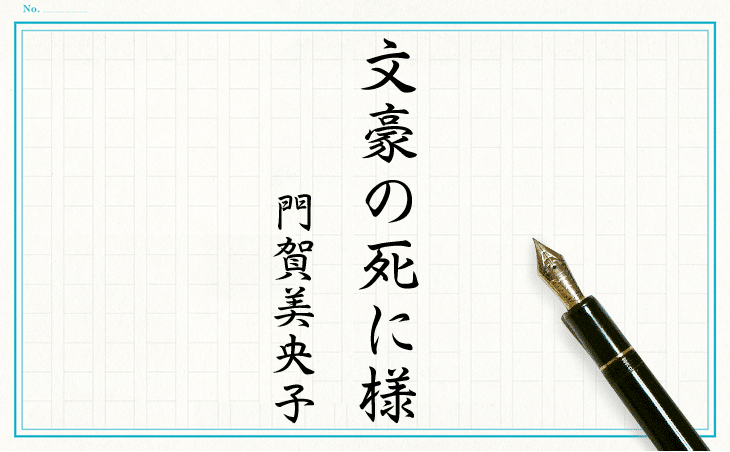







ダークサイド
2023.09.02
鴎外森林太郎は陸軍省医務局長時代に脚気の原因の誤認により、極めて多くの陸軍兵士の命を奪ってしまったと最近知りました。
その後もその責を負わず、自らの最期を迎えて「馬鹿らしい」とは不愉快極まりないと思いましたが、よく考えると、林太郎は自らの所業の全てについて馬鹿らしく耐え難い愚業だったとして、「馬鹿らしい、馬鹿らしい」と叫んだとすることで、多少は救われる気がします。