第10回
梶井基次郎――早世の青春作家はバカッターのはしり?! (前篇)
2019.07.12更新
『文豪』という言葉にどんな印象がありますか? ここ数年、文豪をモチーフにしたゲームやアニメの影響による『文豪ブーム』で、文豪の人柄に関心が高まっています。この連載では、文豪の末期、すなわち『死』に注目をします。芸術家は追い立てられるように生きて薄命な印象がありますが、文豪はどうなのでしょうか。『死』を見つめることは『生』を見つめること。それぞれの『死』から、多様な生き方を見ていきます。
「目次」はこちら
梶井基次郎(かじい・もとじろう)
小説家。明治34(1901)年、大阪生まれ。昭和7(1932)年、大阪で結核によって病死。享年31。代表作に『檸檬』『Kの昇天』『櫻の樹の下には』など。
2015年、書店の丸善が10年ぶりに京都支店を再開したことが話題になった。
当連載を読んでくださるような方は先刻ご承知のこととは思うが、丸善は明治3年に一号店を構えた日本近代書店きっての老舗である。西洋から輸入した本や雑貨を扱うというので、明治以降の文士にとっては無くてはならない店だった。文豪たちのエッセイなどにしばしばその名が現れるし、創業者がハヤシライスの生みの親なんていう俗説もあったりで、今もって日本を代表する書店のひとつだ。
こんな背景を頭に入れた上で、それでもやはり丸善、とりわけ京都店に特別な地位を与えた立役者は、梶井基次郎の代表作「檸檬」と断じて間違いないだろう。
基次郎は、1925(大正14)年に発表されたこの作品の中で「青春の煩悶を抱えるとある青年が、京都丸善の店頭に並ぶ画集の上に檸檬を乗せて立ち去る」シーンを描いた。
それが多くの若者の共感を呼び、文学史上きっての名シーンとして今も読みつがれているのだ。
画集の上でひっそりと香気を放つ鮮やかな黄色の果実。
イメージはこの上なく美しい。いかにも文学的かつ芸術的な光景である。
だからこそ、京都丸善が2005年に一旦閉店した際、そして2015年に場所を変えて再出店した折にも大勢の人が押しかけ、基次郎のひそみに倣ったのだ。店側もレモンを入れる専用籠を設置して、人々の思いに応えた。
いい話である。
いい話、なのだが。
よくよく「檸檬」を読み返してみたら、だんだん「……これ、良い話にして可い話、なのか?」ってな気分になってくるのだ。
なぜそんな気分になるのか。
そこを皆さんと共有するべく、以下において疑似読書会を開催したい。
大正青年 バンカラと繊細の狭間で
まず、「檸檬」の背景について簡単に説明しておこう。
前述した通り、この作品は大正14年に発表されている。当時、基次郎は24歳。京都の旧制第三高等学校を経て東京帝大文学部に入学し、長いモラトリアム生活を謳歌していた。
31年で終わった彼の生涯のうち、もっとも長かったのがこのモラトリアム期である。大正時代の義務教育は尋常小学校(もしくは14歳)までなので、それ以降の高等教育期間をモラトリアム期だと仮定すると、基次郎は1913(大正2)年の中学入学から1928(昭和3)年に東京帝国大学を授業料未払いで除籍されるまで、実に15年間にわたって「何者かになるための準備期間」を過ごしたことになる。卒業後は10代でかかった結核のために闘病生活を送りながら文学者を目指す生活をしていたため、いわゆる社会人として過ごした期間は皆無なのだ。
そんな生涯の中で、基次郎がもっとも弾けていたのが三高時代だった。
時はまさに大正モダン、大正デモクラシーの真っ盛り。近代日本が初めて「大衆の自由」を手に入れかけた、そんな時代だった。
時代の空気は、若者に顕著に現れる。
旧制高等学校の中でもナンバースクールと俗称される一高から八高までは超エリート校として名を馳せていたが、文弱は蔑視され、バンカラ、つまり洗練より粗野で荒々しい振る舞いを良しとする風潮があった。
直情径行タイプの基次郎はあっさりその風に染まり、三高きってのバンカラ大将になっていく。
大正十二年の春、その頃の彼の作品を見れば彼の憂鬱さを理解できるがそんな憂鬱な蟇のような顔をしてズックのかばんを肩にかけて誰かと話をしていた。(中略)妙に強い印象をその姿態から残したので、私は何という男かと人にいくと、あら三高の主や、古狸やという答えを得た。(中略)何故主かというと、何でも彼はそれまでに二度ばかり落第しつづけていたからである。
(番匠谷英一「梶井君のこと」より)
ほんとうに旧制高等学校生徒のイメージにはまりこんだような男で、わりあい制服制帽が好きなんです。ある日、ちゃんと制服を着ているのだが、足ははだしの男が、悠然と裏門から入ってくるのを、あれが梶井基次郎だ、と誰かが教えてくれたのが、彼を知った最初です。
(丸山薫・河盛好蔵「対談 紅、燃ゆる」より丸山の発言)
バンカラは姿形だけではない。
梶井の生活はだんだん乱れだした。酒の上の乱暴も甚だしくなった。(中略)その夜梶井は料理屋にいる間は、床の間の懸物に唾を吐きかけて廻ったり、盃洗でとんでもない物を洗って見せたり、限りない狂態をつくしていた
(中谷孝雄「梶井基次郎――京都時代」より)
ところが梶井君が清滝(注1)に行くと、お断りなんです。それは梶井君が、いつか、ここで暴れたらしい。泉水に碁盤をほうり込んだり、自分も飛び込んで、池の鯉を追っかけ回したことがある。「みなさん活発でいいけれども、梶井さんだけはお断りだ」ということなったらしい。(笑い)
(丸山薫・河盛好蔵「対談 紅、燃ゆる」より丸山の発言)
実際此の梶井の放蕩は底抜けのものであって、金魚を抱いて寝たり、焼き芋屋の釜の中へ牛肉を投げ込んで親爺に追駈けられたりしたような奇抜な行や、また彼の高尚な精神とは凡そ反対な悖徳(注2)な行で一杯であった。悖徳はさらに悖徳を呼び、醜悪はさらに醜悪を求めて、彼は荒廃たる狂態を演じ続けた。
(外村繁「梶井基次郎について」より)
上記はすべて、元同級生による暴露話である。なんともまあ非道い話というか、小学生男子並みの蛮行を嬉々としてやっていたわけだ。彼の生まれ故郷である大阪では愚かな坊っちゃんを「あほぼん(阿呆のぼんぼん)」と呼ぶが、この時期の基次郎はあほぼんを超えた狼藉者だった。
だが、ただの狼藉者とは一線を画する素質があった。豊かな詩情と文章力である。
それを駆使して、基次郎の化身とおぼしき主人公に当時の気持ちを語らせた告白体の小説が「檸檬」なのだ。
ツッコミながら「檸檬」を読む
こうした事情を念頭に置いた上で、次にあげる冒頭部分を読んでみてほしい。
えたいの知れない不吉な塊が私の心を始終圧さえつけていた。焦躁と言おうか、嫌悪と言おうか――酒を飲んだあとに宿酔があるように、酒を毎日飲んでいると宿酔に相当した時期がやって来る。それが来たのだ。これはちょっといけなかった。結果した肺尖カタルや神経衰弱がいけないのではない。また背を焼くような借金などがいけないのではない。いけないのはその不吉な塊だ。以前私を喜ばせたどんな美しい音楽も、どんな美しい詩の一節も辛抱がならなくなった。蓄音器を聴かせてもらいにわざわざ出かけて行っても、最初の二三小節で不意に立ち上がってしまいたくなる。何かが私を居堪たまらずさせるのだ。それで始終私は街から街を浮浪し続けていた。
どうだろうか。
「いや、不吉も何も、結核を患っているのに酒を浴びるほど飲んだり、背を焼くような借金してまで遊んだりしてるから体調不良から来る鬱状態になってるだけじゃん?」とツッコみたくなるのは私だけだろうか。えたいの知れない不吉な塊、と表現するとかっこいいが、要するに不摂生不品行を続けまくった結果、心身ストレスによって参ってしまった末の精神不安定としか思えない。
だが、基次郎はそれは原因ではない、と。うーん。本人がそう言うならそうなのかもしれないけれど、でも病んだ心を健やかにするためには生活習慣の改善が欠かせないって聞くし、やっぱり単に体調の問題じゃない?
私は、できることなら京都から逃げ出して誰一人知らないような市へ行ってしまいたかった。第一に安静。がらんとした旅館の一室。清浄な蒲団。匂いのいい蚊帳と糊のよくきいた浴衣。そこで一月ほど何も思わず横になりたい。
うんうん、それがいいよ。
希わくはここがいつの間にかその市になっているのだったら。――錯覚がようやく成功しはじめると私はそれからそれへ想像の絵具を塗りつけてゆく。なんのことはない、私の錯覚と壊れかかった街との二重写しである。そして私はその中に現実の私自身を見失うのを楽しんだ。
って、妄想するだけかいーっ!
この調子で「檸檬」ワールドと漫才をしてもキリがないので、ひとまずラスト付近まで飛ぶことにしよう。
えたいの知れない不吉な塊を持て余したまま、街から街へを彷徨い続ける主人公は、ある果物屋で足を止める。
ここでちょっとその果物屋を紹介したいのだが、その果物屋は私の知っていた範囲で最も好きな店であった。そこは決して立派な店ではなかったのだが、果物屋固有の美しさが最も露骨に感ぜられた。果物はかなり勾配の急な台の上に並べてあって、その台というのも古びた黒い漆塗の板だったように思える。何か華やかな美しい音楽の快速(アッレグロ)の流れが、見る人を石に化したというゴルゴンの鬼面――的なものを差しつけられて、あんな色彩やあんなヴォリウムに凝こり固まったというふうに果物は並んでいる。
突然店レポが始まってびっくりだが、表現は実に美々しい。少々衒学趣味のきらいはあるが、私は嫌いじゃない。
そして、主人公はこの店で手に入れる。
運命の「檸檬」を。
その日私はいつになくその店で買物をした。というのはその店には珍しい檸檬が出ていたのだ。檸檬などごくありふれている。がその店というのも見すぼらしくはないまでもただあたりまえの八百屋に過ぎなかったので、それまであまり見かけたことはなかった。いったい私はあの檸檬が好きだ。レモンエロウの絵具をチューブから搾り出して固めたようなあの単純な色も、それからあの丈たけの詰まった紡錘形の恰好も。――結局私はそれを一つだけ買うことにした。
レモンエロウの絵具をチューブから搾り出して固めたようなあの単純な色って、そりゃ相手は檸檬ですもの。語源になった果物に向かって「あんたは単純なレモン色をしていますな」って、言われた檸檬も困るってものだ。どうにも、基次郎には主客が転倒する癖があるらしい。
まあ、それはさておき。檸檬を得て、主人公は気持ちが晴れていくのを感じる。
始終私の心を圧えつけていた不吉な塊がそれを握った瞬間からいくらか弛んで来たとみえて、私は街の上で非常に幸福であった。
よかったよかった!
でも、ここで終わらないのが文学者のめんどくささだ。
檸檬のおかげでひさしぶりに気分が高揚した主人公は、意気揚々と丸善に入っていく。
ここはかつて「私の好きであった所」だったが、お金に窮乏するようになってからは「重くるしい場所に過ぎな」くなっていた。いわく、「書籍、学生、勘定台、これらはみな借金取りの亡霊のように私には見える」からだそうだが、それはもっぱら君の罪悪感がそう見せているんだよ、基次郎くん。
案の定、調子に乗って店に入ったのはいいが、
私の心を充たしていた幸福な感情はだんだん逃げていった。香水の壜にも煙管にも私の心はのしかかってはゆかなかった。憂鬱が立てこめて来る、私は歩き廻った疲労が出て来たのだと思った。
いや、違う。たぶん思い出したくない借金問題が脳裏に蘇ったのだ。つまり、借金を返さない限り、主人公に丸善の店頭を楽しむ日々は戻ってこない……はずなのだが。
ここで彼はとんでもないことを始める。
私は画本の棚の前へ行ってみた。画集の重たいのを取り出すのさえ常に増して力が要るな! と思った。しかし私は一冊ずつ抜き出してはみる、そして開けてはみるのだが、克明にはぐってゆく気持はさらに湧いて来ない。しかも呪われたことにはまた次の一冊を引き出して来る。(中略)以前の位置へ戻すことさえできない。
つまり、棚差しの売り物を次々と引っ張り出しては立ち読みし、「元に戻す体力がないよう」との理由でどんどん積み上げていっているのである。
――なんという呪われたことだ。手の筋肉に疲労が残っている。私は憂鬱になってしまって、自分が抜いたまま積み重ねた本の群を眺めていた。
憂鬱になるのはその惨状を片付ける店の方だ。元書店アルバイトとして言わせてもらおう。
出したら戻せ。戻さないなら出すな。
時空を超えて文句をつけてもしかないのだが、つけざるを得ない。なぜなら、このあほぼんはさらにとんでもないことを思いついてしまうからである。
「そうだ」
私にまた先ほどの軽やかな昂奮が帰って来た。私は手当たり次第に積みあげ、また慌ただしく潰し、また慌しく築きあげた。新しく引き抜いてつけ加えたり、取り去ったりした。奇怪な幻想的な城が、そのたびに赤くなったり青くなったりした。
やっとそれはでき上がった。そして軽く跳りあがる心を制しながら、その城壁の頂きに恐る恐る檸檬を据えつけた。そしてそれは上出来だった。
なんと、店頭で商品の本を使って積み木をし始めたのである。そして、本人の目には「城」に映る構造物を組み建て、その天辺に件の檸檬を置いたのだ。
見わたすと、その檸檬の色彩はガチャガチャした色の階調をひっそりと紡錘形の身体の中へ吸収してしまって、カーンと冴えかえっていた。私は埃っぽい丸善の中の空気が、その檸檬の周囲だけ変に緊張しているような気がした。
何を言っているんだね、君は。いい年してお店の商品で遊んでいるだけじゃないか。
しかも、これだけならまだいいが(いや、よくないが)、さらにとんでもなくくだらないことを思いついてしまう。
――それをそのままにしておいて私は、なに喰くわぬ顔をして外へ出る。――
要するに、である。
商品である高価な画集(ここ大事)の数々を棚から抜き出しては、弄り回して積み木のように積み上げ、その上に檸檬、つまりうっかり潰れたりしたら本を汚しかねない生果を放置したままトンズラしようというわけだ。
私は変にくすぐったい気持がした。「出て行こうかなあ。そうだ出て行こう」そして私はすたすた出て行った。
変にくすぐったい気持が街の上の私を微笑えませた。丸善の棚へ黄金色に輝く恐ろしい爆弾を仕掛けて来た奇怪な悪漢が私で、もう十分後にはあの丸善が美術の棚を中心として大爆発をするのだったらどんなにおもしろいだろう。
私はこの想像を熱心に追求した。「そうしたらあの気詰まりな丸善も粉葉こっぱみじんだろう」
奇怪な悪漢氏の脳内には、企みの成就を祝う高らかなファンファーレが鳴ったかもしれない。
だが、私の頭に響くのは横山ホットブラザーズの長男がノコギリで奏でる「お~ま~え~は↑~ あ↓ほ↑か↓~」である(なんのことかわからない諸兄諸姉はぜひ「横山ホットブラザーズ のこぎり」でググってください)。
この感じ。
そこそこいい年をした男が、店の迷惑も顧みずにバカなことをしでかして、あまつさえそれを自慢してしまうこの感じ。
現代の私達はよく知っている。
そう。これはまるっきり、バカッターやバカスタグラムと呼ばれる連中と同じではないか。(痛YoutuberやバカTikTokでも可。)
やっていることは、馬鹿げた迷惑ごとをしでかして画像や動画に撮り、自慢げに配信したがる若者と何一つ変わらない。
梶井基次郎はバカッターのはしりだったのだ。
とはいえ、それでも基次郎とネット上の有象無象はやはりまったく異なる。
何が異なるのか。
一つは、基次郎がバカげた衝動を文学に昇華してしまったこと。
もう一つは、死後に得た名声が、彼の行為をコマーシャルにまで高めたことである。
言うまでもなく、現代の愚行画像/動画と違い、基次郎の小説には普遍的価値が認められている。しかし、動機と行為には大差あるまい。
もし、本当に基次郎が当該行為をやったと仮定すると、第一発見者となった店員は「どこのアホがこんなことやりよったんや。ほんまええ加減にしさらせ!」と怒ったことだろう。だが、大々的な共有手段が存在しない大正時代、その怒りは店員ひとりのもの、よしんば広がったところで店内で収まる程度であって、それ以上は拡散されない。
その上で、もし、その店員がたまたま大正14年のオンタイムに「檸檬」を読んで、「あ、あの時のヤツ!」と思い至ったとしても、こんな文学に仕立てられてしまっては苦笑して許すしかなかったのではなかろうか。書店に勤めるような人間なら、余計に。
ここまで散々こき下ろしてきて何なのだが、基次郎が描いた青春の一シーンには、確実に普遍的な価値がある。どんな時代でも色褪せない繊細な詩人の魂が文中に吹き出している。
物事の価値を決めるのは、結句天秤の釣り合いだ。
片方の皿に乗ったのが愚行であっても、もう片方にそれ以上の価値を置くことができれば、世間様は多少のことには目をつぶってくれる。
バカッターだのバカスタグラムだの呼ばれて叩かれた彼らだって、自分のやっていることは誰が見ても「おもしろく」「痛快である」と思ったから、わざわざ世間様に晒したのだろう。そして、多数がそれを支持したなら、まとめサイトにおもしろおかしく取り上げられて彼らの卑小な承認欲求を満たして終わり、だったはずだ。しかし、実際には大多数の人に不快感を催させただけで、結果として配信者はボコボコに叩かれて社会的制裁を受けた上、二度と消えないデジタルTatooをネット上に残してしまうことになったのだ。
基次郎とバカッター、彼我の差は激しい。
だから、私は提案したい。
若者よ、どうせバカなことをするのであれば、それを文学や芸術に仕立ててしまってはどうか、と。
一瞬のノリ一発で撮れてしまう安直な画像や動画なんぞ、よほどの才能がない限りロクな出来にはならないものだ。必要なのは、その時におもしろいと思ったことが本当におもしろいのか冷静に振り返る余裕と、おもしろいと確信したならそれをよりブラッシュアップするために創意工夫を加える時間だ。
少し前、飲食店のアルバイト店員が店内で見るに堪えない行為をし、それをネットにアップして大騒ぎになる事件が多発した。店員たちはネットで総攻撃をくらっただけでなく、馘首されて仕事を失い、損害賠償を求める裁判の被告にさえなっているらしい。未熟さの対価としてはいささかオーバーキルな気がしないでもないが、それがご時世というものなのだろう。実際、企業は大損害を受けている。
だが、彼らのやったことをアートや文学として脱構築してみたら、それなりに評価されるものが生まれる可能性はある。やり方さえ間違えなければ真っ当な社会批評になる余地があるからだ(当たり前だが、批判を受けた彼らが批評性を持ってあれをやったとは一切言っていない)。
とにかくですな。
若者の煩悶はどんな時代にも必ず存在し、未熟さ故にとんでもない形で煩悶を発露させてしてしまうことはままある。それが作品になるかどうかは紙一重。運と美意識の賜物だ。
基次郎には美意識があった。そして、それを表現するだけの文章力があった。
だが、運はなかった。
やりたいことは定まっていながら病がそれを許してくれない運命を、死後の名声だけで「幸運」とみなすことなど、私にはできない。もちろん、歴史に埋もれていった数多くの名もなき天才に比べればまだしも、かもしれないが。
才能に恵まれながらも、それを活かす身体を得ることができなかった天才。
後篇では、元祖天才バカッターの死に際について見ていきたいと思う。

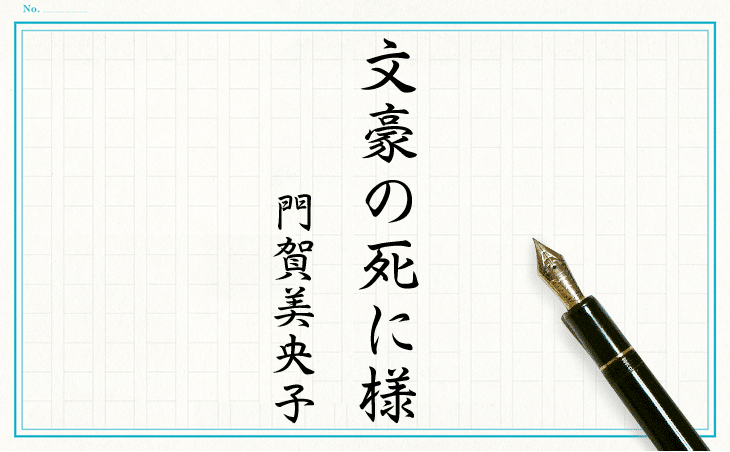







匿名
2024.01.09
現実にやってないので許してあげてください。
梶井基次郎は近藤勇に似てないですか?