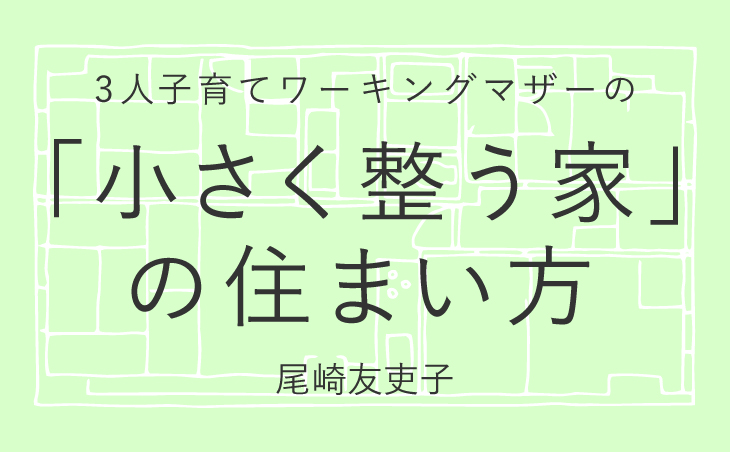第19回
お金について
2019.07.01更新
文化人類学者であり、国士館大学教授の鈴木裕之先生による新連載が始まります。20年間にわたりアフリカ人の妻と日本で暮らす鈴木先生の日常は、私たちにとって異文化そのものです。しかしこの連載は、いわゆる「国際結婚エッセイ」ではありません。生活を通してナマの異文化を体現してきた血の通った言葉で、現代の「多様性」について読み解いていきます。
「目次」はこちら
気になる事柄
このエッセイをはじめてから、かれこれ10カ月が経とうとしている。
これまで、国際結婚の現場、フィールドワークの現場を経て、私がもっとも敬愛する黒人ヒーローについて語らせてもらった。
この辺で、そろそろまとめる時期が近づいてきたようだ。
これからは「~について」シリーズと称し、気になっている事柄から毎回ひとつのテーマをとりあげ、私なりの自由な意見を展開してゆきたいと思う。
まずは「お金」について。
お金は人を選ぶ
グローバル化の弊害のひとつとしてつねにクローズアップされるのが経済格差の問題。
金持ちはより金持ちに、貧乏人はより貧乏になってゆく。
グローバル化は格差社会を助長する構造を内包している。
経済学者の提言、アナリストの解説、政治家の言説……各々が相矛盾する言葉を発し、食い違う主張が飛び交い、異なる世界観が火花を散らす。
テレビ画面に映るその顔は自信たっぷりだ。
だって私は、アメリカの一流大学で学んだのだから。
いいえ、私は日本の一流シンクタンクの責任者なのだから。
いやいや、私は当該担当大臣なのだから。
いやいやいや、私こそが大臣のスピーチを準備する高級官僚なのだから。
だが結局、有効な解決策は見いだされず、一般庶民はただオロオロするばかり。
私たち庶民の感覚では、どうやら景気というのはおおきな波のようなもので、政治、経済、社会問題が複雑に絡みあいながらつねに潮流が変化し、経済アナリストや官僚や政治家が束になってかかっても、その実態を把握して自分たちに好ましい流れをつくりだすことは困難である、いや、経験上、不可能である、という印象が強いが、どうであろか。
であるから、経済的弊害の理解とそれに対する政策というような難しい問題については、成果が上がるかどうかはわからないがとりあえず専門家たちに任せるとして、私としてはもっと身近な、肌感覚で把握できるお金の問題について考えてみたいと思う。
私がこれまでの人生で感じてきたのは、「お金は人を選ぶ」ということである。
金儲けのうまい人のところには次から次へと富が集まり、お金に縁のない人のところには富が寄りつく気配さえない。
社会的不平等であるとか、まじめに働くとか、そういった構造的あるいは道徳的レベルとは別に、お金には人の手でコントロールできない固有の次元が存在しているような気がする。
貧乏でも幸せ
私は金儲けが苦手である。
人にモノを売りつけるためのハッタリやゴリ押しが性に合わない。
アビジャンでストリートの調査をしていた時には、凶暴な不良相手にハッタリをかましながら互角に渡りあっていたが、商売となったとたんに心の奥の弱気が目を覚ましてしまう。
根が百姓なので、ほんとうに価値があるのかどうかわからないものを、他人様に金を払わせて押しつけるという商人根性が、自分の内側にはまったく存在しないのだ。
お金の方もそのことをお見通しで、私の方にはまったくといっていいほど寄ってこない。
このお金に好かれない性質は、どうやら私の田舎に起源があるようだ。
私の生まれ故郷は、なにを隠そう、あのリニアモーターカーの実験線がつくられた村である。
今から29年ほど前に実験線の着工がはじまり、その6年後に走行試験が開始されたが、実験センターはうちの村の目と鼻の先に建設され、路線は村のど真ん中を突っ切るかたちとなった。
その際、例によって用地買収がおこなわれたが、路線が我が家からほんの数十メートルほどの距離に敷かれたのにもかかわらず、うちが所有する土地はかすりもしなかった。
土地が当たった家では、それまで二束三文にしかならなかった山村の土地をそれなりの値段で買いとってもらい、引っ越して家を新築し、ある程度の蓄財もできたことであろう。
田舎に帰るたびに、幼いころよく遊んだ山の中腹に鎮座する実験センターの建物と、そこから延びる路線の高架を眺めながら、私はため息をつく。
「ああ、我が一族はほんとうにお金に縁がない……」
だが、この金欠体質がおもしろい現象を生んだ。
根が真面目な父はもともと人望があり、村でも一目置かれ、相談役的な存在であった。
リニアの件で金が入らなかったということは、利害関係のうえで「中立的」ということであり、誰にたいしても等距離にあるということになる。よって、ここでも相談役、意見の調整役として最適な存在となっていった。
事業の立ちあげから現在に至るまで、歴代のJR担当職員はかならずうちにあいさつに寄り、父を村の窓口としてリスペクトしてくれる。父は村人の利益が損なわれず、同時にリニアの事業がつつがなくすすむように気を配りながら相談に乗る。
うちは男ばかりの三人兄弟で、みな東京の大学をでて東京で働いている。年に数回しか息子たちに会えない父は、本社から派遣されてきたJRの職員にコーヒーとお茶菓子を振る舞いながら、世間話に花を咲かせる。
我が家の居間は村側にも企業側にも開かれた風通しのよい「交通」の場となり、そこを住みかとする父は齢92にして、若々しい心を保ちつづけている。
もちろん身体にはそれなりにガタはきているが、とても90過ぎのご老体には見えない。
なによりも人相が良い。
お金でも権力でも、人はそれを手に入れた瞬間から人相が悪くなりはじめる。他者と対峙するとき、それを守ろうという心の鎧を知らず知らずのうちにまとってしまい、それが顔に出てしまうのだろう。その量が増えるごとに鎧の重さも増し、人相も崩れてゆく。
父のスッキリした顔を見ながら、あぶく銭はいらない、財産は自分の両手に収まるくらいがちょうどいい、と思うようになってきた。
お金はこんな人間を選ぶことはない。
金欠体質は、やはり遺伝するのであろうか。
グリオとお金
アフリカでお金を人に貸したら、ほぼ返ってこないと覚悟しなければならない。
一度手から離れた金は、もはやあなたのものではない。
アビジャンで調査をしていた時、ストリート・ボーイは落ちていた金をDieu donné、つまり「神から与えられたもの」と呼んでいた。
こんな社会で生まれ育った者の金銭感覚は、私たち日本人のそれとはおおきく異なってくる。
生涯賃金を計算し、年金収入を計算し、物価上昇率を計算し、老後はいくら足りなくなりそうだとシュミレートし、それから逆算して現在の家計のスケールを決め、今月はいくら赤字になりそうだと逆上しながら節約生活に励む。まるで将来のために現在を人質にとられているかのような日本人の生活。
アビジャンで私の眼に焼きついているのは、マンデの祭りで大量の札が乱舞する光景だ。
私の妻が属するマンデ系の民族では、祭りに伝統的語り部・歌手であるグリオが招かれ、出席者に対する誉め歌が歌われる。グリオはマンデ系民族の起源であるマリ帝国の建国史に登場する歴史上の重要人物と出席者をさまざまなレトリックを駆使しながら結びつけ、彼を、彼女を、誉めて誉めて誉めまくる。
その勇敢さは、その優しさは、その美しさは、あなたの祖先のなにがしから譲りうけた美徳であると。まさにあなたはマンデの名に恥じない存在であると。
出席者はグリオの歌をとおしてマンデの歴史とつながり、自身のアイデンティティを再確認し、その感謝を込めながら聴衆の面前でお金をグリオに渡す。
札束を握りしめ、一枚、また一枚とグリオに渡してゆく。その枚数が増えるごとにグリオの歌は熱気を帯び、そのことばには言霊が宿り、誉められる者はマンデの一員としての自覚を深め、その実存が世界のなかのあるべき場所に位置づけられてゆく。
誉め歌の本質
私は当初、グリオの誉め歌には用心していた。
調査の一環としてマンデの祭りに出席し、写真を撮る。
美しく着飾った女グリオ、激しく鳴り響く太鼓のアンサンブル、リズムにあわせて次から次へと踊りを披露する若い娘たち、色とりどりの伝統衣装を身につけた出席者たち……じつにフォトジェニックな光景だ。
私はその場にいるものの、祭りの当該者ではないので、誉められる謂われはない。だがグリオたちと顔見知りになってくると、突然、誉め歌の矛先が私に向けられはじめた。
「スズキ~、スズキ~、あなたはあの豊かな国日本からアフリカにやってきた心の広い男……」
歌と太鼓の響きが混じりあった轟音のなか、私はジェスチャーで「いや、私、ただの調査者ですから」などと拒否してみるが、グリオはそんな言い訳など気にせず、誉め歌のヴォルテージをどんどんあげてくる。
みなの熱い視線が集中するなか、私は仕方なくポケットから札をとりだし、グリオに渡す。
1枚、これだけか、2枚、まだまだ、3枚、そうそう、4枚、もう一息、5枚……
こうして私は、調査の度にスッカラカンになって帰ってくる。まさに、伝統文化のボッタクリである。
だが、彼らの文化にも慣れ、さらに結婚をとおして文字どおりマンデの一員と見なされるようになってくると、こうした光景が違う意味を持つようになってきた。つまり、本来の姿が見えるようになってきたのである。
それまで私は、誉め歌のプロセスを収支関係で把握していた。今日の祭りではポケットからいくら減り、それは調査の際の必要経費であると。
だが実際は、収支は二次的な問題にすぎない。もちろん、誰がいくら払い、どのグリオがいくら儲けたかというのは人々の関心事であり、その額が誉める者と誉められる者の双方の社会的格付けの基準となる。
しかしもっとも重要なのは、その場で当該個人とマンデの歴史とのあいだに回路が開かれ、重層的な世界が現出するということである。この個人と歴史とをつなぐ媒介者がグリオである。
グリオは先祖代々受け継いできた歴史に関する詳細な知識と、それを語り歌う高度な技術をもって、700年前のマリ帝国を、特定の英雄や故事を詳述しながら、バーチャルなかたちで現出させる。するとその場から時間的隔たりが消滅し、人はマリ帝国の歴史を追体験しながら、グリオの話術によって自身と歴史が一体化させられ、マンデの民としてのカタルシスを得ることができる。
この一連のコミュニケーション過程の扉を開く鍵がお金である。
グリオは一様にプライドが高い。ある程度の金額を渡すというのは、グリオに対する敬意を象徴する行為である。その敬意を認めたグリオは、自身の技を開示し、「お客さん」が時空を飛び越えてマリ帝国と結びつく機会を提供するのである。
であるから、誉められたのにお金を渡さなかったり、渡しても態度が傲慢で礼を欠いていた場合など、グリオは誉め歌を「けなし歌」に転化させ、当人を「炎上」させる。伝統的に文字を持たず、グリオの生きた言葉がもっとも力を持つマンデ社会において、公衆の面前でけなされた者は、歴史から切り離され、世間的評判も地に落ち、後悔することになる。
カオスな現実
お金とは、この世に存在するさまざまな価値を共通化する尺度としての機能を果たし、それゆえ商品の交換手段としてしての機能を担い、もっともシンプルな蓄財の資産として流通している。
だが、それだけではない。
人の生との関わりにおいて、お金はより多元的な存在感を放っている。
お金は運気と結びつき、幸福を運び、あるいは不幸をもたらす。お金自身がまるで意思を持っているかのように私たちの生に介入してくる感じがする。科学的言説には存在しない運気であるが、実体験として運気が自分の人生におおきな力を及ぼしていると感じている人はおおいのではないだろうか。
お金はまた、コミュニケーション・ツールでもある。
さきにグリオの例を挙げたが、さまざまな民俗文化において、お金はこの世の人間のあいだ、あるいはこの世とあの世を結びつける媒体としての機能を果たす。祭り、儀礼、あるいは日常生活におけるお金のやりとりには民俗的な意味が込められ、額面の値段とは別の尺度の重みが担わされる。それを、かつての私のように、たんなる収支計算だけで理解しようとするだけでは、そのリアリティをつかみ損ねてしまう。
お金を扱う学問は経済学であり、それに基づいて経済政策が策定され、企業の運営方針が検討され、ファイナンシャルプランナーが個人の資産管理のアドバイスをおこなう。だがじつは、この多様な世界において、人とお金とのかかわりは経済学的領域に収まりきるものではない。
ひとは経済合理性だけにもとづいて行動するわけではない。にもかかわらず、お金を経済学的領域に閉じこめるのは、自らの生をその範囲に閉じこめてしまうことになるのではないだろうか。
お金はコミュニケーション・ツールである。にもかかわらず、老後の不安からすべてを貯金として固定化することで、コミュニケーションの流れも遮断され、知らず知らずのうちに個々人が孤立してゆくのではないだろうか。
そんなことを言ったって、実際に死ぬまでの資金が不足するのだから、仕方がないではないか。そう反論されることだろう。
だが、そのシミュレーションには、幸福感であるとか、人とのつながりであるとか、「今、ここでの充実感」などといった私たちの生を構成する大切な変数は考慮されているのだろうか。
実際のところ、私たちは、本来は計算しつくせない人生を、無理やり計算しようとする喜劇を演じせられているのではないだろうか。
だがじつは生とはカオスであり、不確定要素に満ちている。
それらを科学によって合理的に解釈しようとするが、それでも民俗レベルにおける人間の性向や、超自然的レベルとの関わりあいは把握しきれるものではない。
ここでひとつ、自身とお金との関係を、経済的合理性にもとづく数字の世界から、人と人とのあいだの、あるいはこの世とあの世のあいだのコミュニケーションの世界へと開放する、というパラダイム転換を起こしてみてはいかがであろう。
もしかすると、自分の生がより多様な世界へと開放され、多層的で充実した人生が目の前に開けてくるかもしれない。