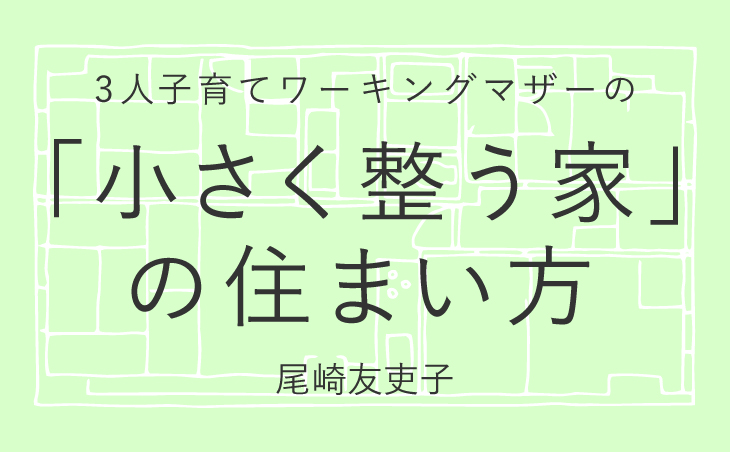第3回
「こうしちゃいられない!」の発見
2017.12.04更新
【 この連載は… 】 『アイデアNo.379 ブックデザイナー鈴木一誌の仕事』の発売を記念して行われた鈴木一誌さんと山本貴光さんとのトークイベントをもとに再構成。長きに渡り日本のデザイン界を牽引してきたブックデザイナーの鈴木一誌さんと、著書『文体の科学』で言葉と思考の関係を読み解いた批評家の山本貴光さんとの、どこまでも深い考察。全6回に分けて再現します。(トークイベントは2017年10月14日に青山ブックセンターにて行われました)
「目次」はこちら
省略してもわかるのが「文体」
鈴木 いろいろな文体を見てもらいましたが、文体ってどこかに省略があると思うんです。これは『文体の科学』の指摘では、法律の文体では、「この法律は~~~することを目指す」という文頭と文尾が省略されている。辞書は「~~~は」と「~~~である」がない文章だと書かれている。省略してもわかる人たちによって共有されるのが文体だとも言える。
山本 それは大いにあると思います。いま、一連の文体を見本帳のごとく、ジャンルもさまざまな文章を見て、なおのこと実感しました。それぞれ、読む人が読み方を知っていなければ読み解けない文章では、いわば省略されていて直に示されていないことを読み手が補完する必要があるわけです。一種の暗号のような側面がありますね。法律の文章はその最たるものです。技術書や専門書もそうですね。数学書では、のっけから数式が提示されて、やおらそれが変形されていったりします。これは「みなまで言わなくてもわかってるね?」という書き方です。いちいち記されることなく、そこでは省略されている文脈をわかっていないと読めない本です。

鈴木 囲碁や将棋の完成譜もそうです。できるかぎり省略して、わかる人だけがわかる。ある種、「わかるよね」との呼びかけに対して、読み手が「わかる、わかる」と応じる共感の世界。
山本 馴染みのない方のために補足すると、ふたりのプレーヤーが手を指した順序を数字や記号で示したものを棋譜と言います。あの図を見て、この対局では一方がこう指して、他方がこう応じたのか、と興奮できるのは、それを読む人が、記号を見て盤上の出来事を想像のうえで再現できるからですね。
鈴木 デザイナー必読と思われる『括弧の意味論』(木村大治)という本では、なぜ『週刊新潮』とか『週刊文春』の見出しはさまざまな括弧を使いまくっているかって書いてある。カギ括弧というのは、「わかるよね?」って意味で使っているという。文体文と似ている。
山本 文体はどうして生じてくるのか。この問題について鈴木さんから、ひとつには省略の働きがあるとご指摘いただきました。少し別の角度からこんな例はいかがでしょう。例えば夏目漱石の『吾輩は猫である』は「吾輩は猫である。名前はまだない。」とはじまります。この文章は、漱石がそれ以外のあらゆる表現の可能性を脇にのけて書いているとも言えますね。これは吾輩を名乗る猫が苦沙弥先生の生活を観察して報告する小説です。その中で猫がこう言っています。吾輩のような観察家といえども、24時間ずっと苦沙弥先生の言動を見張って漏れなく報告するわけにはいかないと。つまり、全部記録したりはできない。何かを省略せざるを得ない。作家は、なにを書くにしても書かなかったことを略して書いている。つまり、ある表現を選ぶとき、他を捨てたり省略したりしている。ちょっと大袈裟に言えば、そのとき地球上で起きているあらゆる出来事から、吾輩が何を見ているかだけを選び、他を捨てて書いている。省略にはそういう面もあると思います。そのとき何を取捨選択するかは、書き手次第です。その結果として書かれた文章に、固有の文体が生まれるのも宜なるかなです。

鈴木 省略しても通じるってことは結局、記憶が補っているということで、記憶を掘り出してくださいと省略する側から呼びかけている。
山本 おっしゃるとおりだと思います。入門書や専門書では、その点について調節のかけ方が違うわけですね。例えば、入門書は省略されたものを自分の記憶で補える状態にない人に向けて書く。だから、読者に予備知識を期待するのではなく、なるべく省略せずに書く。専門書では1を言えば10を連想・想起できる人に向けて書いているので、いろいろ省略もできるわけです。
鈴木 就職の募集でも、省略があるから信頼ができる。「経験不問」と素気なく書くからいいんで、ごちゃごちゃ文章で書かれたらこの会社大丈夫かな? って思っちゃいます。
山本 そうそう! 「当社の人事部といたしましては、あなたがこれまでどのような仕事をしてきたかについては表だってお尋ねすることはなく、つまり一切不問でございます。」などと書かれていたら、応募する人は身構えちゃいます(笑)。そうではなくスッキリ「経験不問」と書かれる方が余計なことを考えずに済む。
鈴木 ここで先程の(Fとf)の話に戻りますが、このFとfを少しずらして、かなり雑駁に読み替えると、こういうことも言えると思うんです。映画監督の澤井信一郎さんが映画を作るときには、ストーリーとテーマは分けろと言っている。ストーリーというのは、「難病の女性が健気に生きる」というもので、そこにどんなテーマを込めるかは、家族愛なのか死生観なのか、それは別のものだと。特に澤井さんというのは東映で娯楽映画を撮っていたから、例えばヤクザ映画なんてストーリーは全部一緒なんだけども、夫婦愛や人情だったりとテーマが違うんだと。「なにを」と「どう」とにも置き換えられる。
山本 なるほど、型と材料といってもよいかもしれませんね。
鈴木 さっきの鮎釣りの記事でいうと、鮎がどこでどう釣れたかというのがストーリー、川の底ではとんでもなくいろんなことが起きているぞと書いてあるのはストーリーじゃない。「アユが釣れている」との情報が読者に何を伝えたいかというと、「こうしちゃいられないんじゃないか!」ということでしょう。これがテーマでしょう。すぐにでも漁場に駆けつけなければいけないって煽ることが最大のテーマなんです。で、多くの文体は、「こうしちゃいられない」って思わせるのだと思うんです。
山本 「こうしちゃいられない」と、読んだ人をその気にさせるわけですね。
いかに読み手の感情を動かすか?
鈴木 以前、山本さんが吉川浩満さんと出された『問題がモンダイなのだ』のなかで、「問題は向こうからやってくる」と書かれていて、それゆえ「問題は人に不確実性を生じさせ、なんらかの対応を迫る」と記されています。このままじゃいけないんじゃないか、駆けつけなければいけないんじゃないかって、それをあらゆる分野でやっているのが文体なんじゃないかなと。囲碁もあの書き方をされると、テレビで見なきゃいけないと思うし、就職だって応募しなきゃいけないんじゃないかって思ったり。そういうふうにして見ると、夏目漱石の大文字のFと小文字のfも言えるじゃないかと思うんです。ストーリーとしてのFになんらかの不確実性を感受するのがfだと。

山本 その際、言葉だけでなく、それがどのような形で表現されているかというデザインもおおいに効いてくるわけですね。先ほど拝見したさまざまなサンプルがまさにそうでしたが、どんな書体か、どんな大きさか、どこに配置するかといった点も含めてデザインを施す。それを目にした人が「こうしちゃいられない」と心を動かされる。デザイン用語としてのアフォーダンス(もとは生態学的心理学の用語)ではありませんが、見た人に何かしたい気持ち、何かできるという心理を引き起こす。ドアノブをみたらスライドさせるのではなく、押したり引いたりしたくなるとか、椅子を見たらこう座るものだと分かるといった具合にアフォードされる、つまり行動の可能性を感じさせられる。さっきの釣りもそうですね。記事を目にして「まだ夜中だけど夜が明けたら行くぞ」みたいな(笑)。
ただの言葉ではない。鈴木さんもしばしばご著書で書いておられるように、言葉は形を持たずに存在できるわけではない。言葉と姿形、テーマとストーリーの組み合わせによって人の気持ちを動かすはずですね。だから同じ言葉であれば、どんなデザインでも同じ効果になるとは到底いかないわけです。この形でなければこのようには気持ちをそそらないということがある。
鈴木 デザインも、「こうしちゃいられない」の演出なのかもしれない。キレイな明朝体で上品に組むと、「こうしちゃいられない」感がなくなって「こうしていればよい」みたいな感じに思えてしまう(笑)。「こうしちゃいられない」っていうのは新聞紙でやってるからより切迫性が出たりもする。
(次回、第4回は12月11日(月)更新予定)