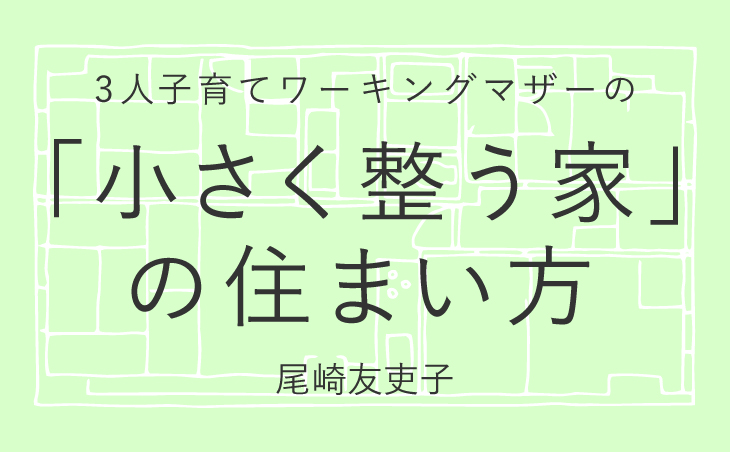第4回
同じ文章を読んでも、みんな違う読解をする
2017.12.11更新
【 この連載は… 】 『アイデアNo.379 ブックデザイナー鈴木一誌の仕事』の発売を記念して行われた鈴木一誌さんと山本貴光さんとのトークイベントをもとに再構成。長きに渡り日本のデザイン界を牽引してきたブックデザイナーの鈴木一誌さんと、著書『文体の科学』で言葉と思考の関係を読み解いた批評家の山本貴光さんとの、どこまでも深い考察。全6回に分けて再現します。(トークイベントは2017年10月14日に青山ブックセンターにて行われました)
「目次」はこちら
同じ条件でも違うデザインが生まれるのはなぜか?
山本 近年、認知科学において、人がものを読んだり見たりすることについても各種の実験や調査が重ねられていますね。例えば中村雄佑さんの『生きるための読み書き--発展途上国のリテラシー問題』という本にこういう面白い調査が紹介されています。
「このように、数学的思考の歴史は図的表現の展開と密接な関係にあるのだが、実際、現代でも私たちが数の読み書きをする場合、思考は書面のレイアウトに少なからず影響されているようだ。たとえば、心理学者ランディとゴールドストーンは、簡単な計算課題をレイアウトをいじって被験者に課したところ、四則演算規則と調和しないレイアウトを提示すると計算間違いが増えたという実験結果を報告している」 『生きるための読み書き--発展途上国のリテラシー問題』(中村雄佑)
つまり、同じような計算問題でも、レイアウトが変わるとそれを読む人の認知を左右するというわけですね。言えば当たり前のことですが、私たちは問題を理解する前に印刷された紙を見ています。どんな素材にどんなデザインを施されているのかを無視できない道理です。先ほど鈴木さんが見せてくださったさまざまな例でも同じことが言えるはずだと思います。そこに印刷された文章を実現している物質やレイアウトが「こうしちゃいられない」を生み出している。

鈴木 ミームデザイン学校(鈴木が講師を務めるほぼ毎週土曜日だけのデザイン学校。http://www.memedesign.org/))は10周年を迎えましたが、1年めにやった課題がこれです。阿刀田高さんの『楽しい古事記』を題材に、同じ文字要素を背中に配置して手書きでデザインしましょうというものなんですけど、ほとんど同じ条件なのにこれだけ違いが出て驚きました。生徒もびっくりして、こんなにやりうる幅があったのかと。「こうしちゃいられない」理論に当てはめると、著者名や版元名はストーリーだと思うんです。で、そのストーリーにどういうテーマを持たせるかというのをそれぞれが考えた結果が、この結果なのかなと。本の背という「場」を確保したからというのもありますが、ストーリーだけならほぼ同じデザインになるはずがそうはならない。そこにFとfの遭遇があるんじゃないかな。
山本 いまの話を伺って、少し別の角度から思うことを述べてみます。例えば『楽しい古事記』を100人の人が読んだとしましょう。100人が100人、同じ読解をする事はまずありません。同じ文章なのになぜ違う解釈や感情が生まれるのか。これは漱石も『文学論』で検討していることですが、読む人による違いが生じるのはそれぞれの人がどういう経験をしてきたか、つまりどんな記憶を持っているかが違うからですね。

鈴木 同じ文章を読んでも、違う記憶をもった人が読み、あるいはその記憶を基底にしてfが生まれる。
山本 しかもその都度違う。文章を読むとき、目にした文字からどのような記憶を想起するかは人によって違うし、同じ人でも時と場合によって違うわけです。これは文章の例ではありませんが、昔フランソワ・オゾンの「8人の女たち」を観にいって、あまりにも面白かったのですぐに2回目を観たところ、最初に感じたような楽しさを味わえなくてがっかりしたことがありました(いま観たらまた楽しいと思います)。そうかと思えば、何遍観ても夢中になってしまう映画もある。みなさんもそういう経験があるのではないでしょうか。
鈴木 ストーリーの解釈としての違いはないとすると、文体の感覚の違いがあり、そこからテクストが生まれてくる。映画は数百のカットの集合なわけですけど、それがいつしかテクストになっていく。テクストになっているからこそ観るたびに違う感覚を得られる、あるいは見る人ごとに違う。作品・文章というものがあるにしても、読む側がそれと衝突し、すれ違うところから作品が生じる。
『脳がわかれば心がわかるか』のなかで山本さんは吉川浩満さんとふたりで、「ある判断の意義を決めるのは、脳の内側での働きと、脳の外側つまりは環境との『関係』だというほかはありません」とします。
山本 いま目の前の状況や環境から生じる知覚と、過去の経験の記憶とがループのようになっているとも言えそうですね。外からの知覚によって記憶は変化し、記憶によって知覚を解釈するというように。
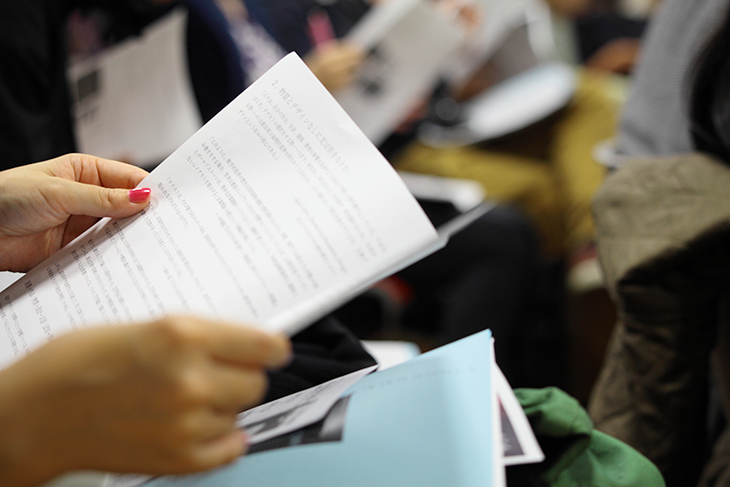
個別の違う記憶を持った人に向けてどうデザインするのか?
山本 ここでひとつ伺いたいことがあります。鈴木さんはデザイナーとして本なら本の形を提示するわけですね。このとき、不特定多数の読者は全員違う記憶を持った個別の存在なわけです。それに対してひとつの形を提示する。いま申し上げたいことを明確にするために、ちょっと別の例を出してみます。例えば建築物を設計する場合、いろんな身長や歩幅の人がいるにもかかわらず階段の高さを決めなければいけませんよね。上り下りする人に合わせて高さが変化する階段があればよいのかもしれませんが、実際には見たことがありません(笑)。本の場合も、本文を設計する際には字の大きさや書体や行間などをひとつに決めないといけないわけです。ブックデザイナーも建築家と同じように、不特定多数の人びとに向けて、ひとつの決まった形を提示します。そうしたものを作るとき、ここまで議論してきたような、人による違いについては、どんなふうに考えておられるのでしょうか。
鈴木 ちょっと回り道をする答えをすると、山本さんの本にはあらゆるところに2つの運動の遭遇と擦過があって、例えば『ゲームの教科書』のなかでは「ふたつのインタラクション」と書いてあり、書物は文字を通じて人に読まれると書かれています。読んだときにそれこそfが伴われて、作品の意味が変わってくると。ふたつのインタラクションもひとつの出会いだし、まあ、ゲームの内と外やサイエンスとアートっていうのも関係そのものだと思うんです。
『文体の科学』は一見、平易に書かれているんだけど、読んでると意外とむずかしいんですよ。全体の構成は、科学の文章、小説の文章、批評の文章といったブロックになっている。例えば科学の文章について書くならば、昔はどうで、今はどうなっていると書くのが普通だと思うんですよ。ところが山本さんの文章は内在的にいきなり入って、途中で外在的になる。内から書くか外から書くかっていうのが章ごとに違っていたり、あるいは短冊状にシャッフルされていたりしてて難しいんですよ。内在的というのは、その世界の文体に一旦溺れてみる、くらいの意味ですが。つまり、山本さんは一貫して2方向の運動の関係としてものごとを記述しようとしている。

山本 鈴木さんがあまりにも私の本をたくさん読んでいらっしゃるので驚愕しています。慣れないことでドギマギしています(笑)。読み込んでいただいてありがとうございます。
鈴木 例えば山本さんは「こういう文章がありますよ」、「こんな具合に考えてみよう」って読み手に呼びかける。「もう一つ検討したいことがあった」、あるいは、「~~~すればどうなった」といったメタな文章を挟む。
山本 一旦、身を離してみようということですね。
鈴木 一旦、身を離す感覚が山本さんの文体のなかにあるんでしょうね。それがそもそも2方向の擦過になっている。『文体の科学』の「小説――意識に映じる森羅万象」の章では、ヴァージニア・ウルフの『ダロウェイ夫人』の帽子のエピソードが出て来て、
「クラリッサは肉親のような同情を寄せながら、同時になぜか自分の帽子が気になった」(ヴァージニア・ウルフ/『ダロウェイ夫人』)
この文章で山本さんは、「クラリッサは肉親のような同情を寄せながら」は情緒を表しているが、「同時になぜか自分の帽子が気になった」では自分の被っている帽子が「なぜか」気になっている。その、「なぜか」っていうのはなんなんだってことになってくる。自分の意識に自分が出会っている。
山本 なんだか精神分析を受けているような気分になって参りました(笑)。
(次回、第5回は12月18日(月)更新予定)