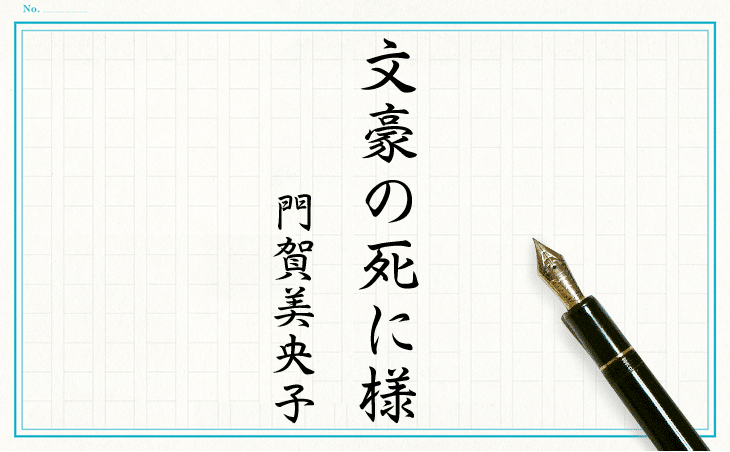第11回
梶井基次郎――死を見つめ、死と戦い、生を捨てず。(後篇)
2019.07.26更新
『文豪』という言葉にどんな印象がありますか? ここ数年、文豪をモチーフにしたゲームやアニメの影響による『文豪ブーム』で、文豪の人柄に関心が高まっています。この連載では、文豪の末期、すなわち『死』に注目をします。芸術家は追い立てられるように生きて薄命な印象がありますが、文豪はどうなのでしょうか。『死』を見つめることは『生』を見つめること。それぞれの『死』から、多様な生き方を見ていきます。
「目次」はこちら
(前編からの続き)
前篇では散々あほぼん呼ばわりしてきた梶井基次郎だが、実のところ、彼の死に様については尊敬の念を抱いている。彼ほど、最後まで生を諦めず、そのくせして散り際にはパッと命を手放した文豪はいないからだ。
大正13年(1924)に「檸檬」を同人雑誌『青空』発表してから8年、昭和7年(1932)の正月にはすでに死を待つばかりになっていた。肺尖カタルと診断された大正9年(1920)から数えると12年に及ぶ闘病生活は、ここに来て刀折れ矢尽きたのである。
そんな自分の姿を、ユーモアを交えながら淡々と書き綴ったのが、絶筆にして生前唯一商業誌に掲載された「のんきな患者」だ。
依頼があったのは前年の10月。基次郎は応諾した上で、掲載は翌年の新年号にしてくれないかと丁重に頼んでいる。
この事実をどう解釈すべきか。もし、彼が健康な青年だったのであれば、その年の5月に出したばかりの処女短篇集『檸檬』の勢いを削がないためにも掲載を急いだ、という解釈が妥当かもしれない。
だが、基次郎は違う。「のんきな患者」はそのタイトルとは裏腹に、まさに命を賭する覚悟をしなければ書けない作品だった。病状はそこまで進んでいたのだ。
吉田は肺が悪い。寒になって少し寒い日が来たと思ったら、すぐその翌日から高い熱を出してひどい咳になってしまった。胸の臓器を全部押し上げて出してしまおうとしているかのような咳をする。四五日経つともうすっかり痩せてしまった。咳もあまりしない。しかしこれは咳が癒ったのではなくて、咳をするための腹の筋肉がすっかり疲れ切ってしまったからで、彼らが咳をするのを肯じなくなってしまったかららしい。それにもう一つは心臓がひどく弱ってしまって、一度咳をしてそれを乱してしまうと、それを再び鎮めるまでに非常に苦しい目を見なければならない。つまり咳をしなくなったというのは、身体が衰弱してはじめてのときのような元気がなくなってしまったからで、それが証拠には今度はだんだん呼吸困難の度を増して浅薄な呼吸を数多くしなければならなくなって来た。
長々とした引用で恐縮だが、これを読めばどれほど彼が衰弱していたか一目瞭然と思い、そうした。
「吉田」は言うまでもなく基次郎の分身である。彼がなぜ「私」とせず「吉田」としたか。その理由は本作を通して読めばただちに諒解されるだろう。基次郎は、自分の苦しみを吐露したかったのではない。「病に苦しむ人間」を客観的に描写したかったのだ。
タイトルは「のんきな」と付けられているが、ここに描かれた彼の闘病生活はのんきとは程遠い。そして、現実をかなり正確に映していることが、当時の彼の日記と、母が記していた看病日誌を読めば確認できる。
字数は一万八千字足らず。原稿用紙に換算すると50枚にもならない。心身ともに健やかであればものの3日か4日もあれば書き上げてしまえる量だ。しかし、咳をする力すら残っていない病人にとっては、命の削る覚悟が必要だった。
それでも基次郎は話を受けた。商業誌に載る絶好のチャンスを逃すことなどできなかった。なぜなら、基次郎は知っていたのだ。己の死がさほど遠くない未来にやってくることを。
だからこそ、10月に来た依頼に対して掲載を急がせるような返事をしたのだろう。
大学を卒業してからの基次郎は、一人で死に向き合い、戦う日々を送っていた。友人たちが己の人生を雄々しく歩み始めたのを尻目に、自分は保養のために都会を遠く離れた温泉街や文化的環境に乏しい実家で過ごさなければならない。
文学への大望に燃えていた青年にとって、これがどれほど過酷な現実かは言うまでもない。
しかし、基次郎は自己憐憫の海に沈むことはなかった。
唯一自由になる想像力を武器に、いつも目の前にぶら下がっている隣り合わせの生と死を、己の文学へと大胆に取り込んでいったのである。
幻想を塗り込んだ死の風景
時代を少し戻そう。
大正13年(1924)、基次郎は23歳で東京帝国大学に入学。文学仲間も増え、有名作家との面会も叶い、自身も多数の短篇をものすなど、充実の東京生活をスタートさせた。しかし、2年後には病状が進み、伊豆の湯ヶ島温泉での転地療養を余儀なくされる。
湯治と聞けば何やら羨ましい気もするが、青雲の志を抱いている、そして世間並みの物欲や性欲を持っている25歳の青年が、山奥でただ体を養うだけの暮らしを余儀なくされたのだと思うと、心中察して余りある。時々は友人が見舞いにやって来たり、同じ伊豆に住む文学者と交流する機会を持ったとはいえ、彼にとっては逼塞同様の侘しさだったのではあるまいか。
しかし、そこで凹むほど基次郎はやわではなかった……というより、大阪人らしい能天気さというか、楽天的というか、「まあ、どないかなるやろ」精神を発揮していた。彼の奥底にはずっとそれがあったように思う。そうでなければ、絶筆のタイトルが「のんきな患者」になろうものか。
だが一方で、死から目をそらすこともない。
昭和2年(1926)、療養生活に入ったばかりの基次郎は心境小説のような「冬の日」という短篇で、こんな風に書いている。
冷静というものは無感動じゃなくて、俺にとっては感動だ。苦痛だ。しかし俺の生きる道は、その冷静で自分の肉体や自分の生活が滅びてゆくのを見ていることだ。
どれだけ療養したところで、健康体にはなれないまま生涯を終えるのだろう。
もちろん、鴎外のように60歳まで生きられることもあるが、一葉のように急激に悪化して一年もたず亡くなる場合もある。特効薬がなかった時代の結核とは、そういう病だった。
そして、基次郎の病状は、少しずつ、でも確実に悪くなっていった。
青く澄み透った空では浮雲が次から次へ美しく燃えていった。みたされない堯の心の燠にも、やがてその火は燃えうつった。
「こんなに美しいときが、なぜこんなに短いのだろう」
彼はそんなときほどはかない気のするときはなかった。燃えた雲はまたつぎつぎに死灰になりはじめた。彼の足はもう進まなかった。
「あの空を涵みたしてゆく影は地球のどの辺の影になるかしら。あすこの雲へゆかないかぎり今日ももう日は見られない」
にわかに重い疲れが彼に凭りかかる。知らない町の知らない町角で、堯の心はもう再び明るくはならなかった。
(「冬の日」より)
落日に我が生命を重ねるのは、自然な心境だったことだろう。
こうして、基次郎の心は、年不相応な諦観に支配されていく……と書ければ、東洋的価値観ではかっこいいのだけど。
そうなってしまっては、あほぼんの名折れである。
これを書いた頃、湯ヶ島にやって来た尾崎士郎/宇野千代夫妻と知り合い、交流するようになった結果、千代にすっかり心惹かれてしまうのだ。
知的なモガで四歳年上の人妻。禁断の恋の相手として、これほどうってつけの女性はいない。一方の千代も基次郎に「一種の色気」を感じたらしい。そして、何をやらかすかわからない危ない青年とも映ったようだ。
或るとき、そのときはおおぜいの仲間たちと一緒でしたが、皆で散歩の途中で、川の流れの激しいところを通りかかりました。「こんなに瀬の強いところでは、とても泳げないなァ、」誰かがそう言ったと思います。梶井は例の眼を細めた笑顔をして、「泳げますよ。泳いでみせましょうか。」と言うが早いが、さっと着物を脱いで、橋の上から川に飛び込みました。この人は危い、と私が思った最初でした。
(宇野千代『私の文学的回想記』より)
まだそんなことやってんのか、お前は……。気になる女性を前にして、いい格好をしたかったのか、それともひさしぶりに学生時代のようなはしゃいだ気持ちに戻ったのか。
いずれにせよ、ナチュラル・ハイにでもなっていたのだろう。
千代の方はというと、「恋だったのかしら、どうだったのかしら」程度の曖昧な気持ちで、恋多き女の本領を発揮しまくっていて、二人の温度差がおもしろいのだが、基次郎の存在が夫婦仲を修復不可能なまでに決裂させる原因になったのは間違いないらしい。
明けて昭和3年の正月、基次郎は文士仲間の誘いで伊豆をちょっと抜け出し、東京は馬込にあった詩人の衣巻省三のアトリエで開かれたダンスパーティーに出席した。そこで尾崎士郎と鉢合わせたところ、尾崎がいきなり基次郎の頬を殴って一触即発の事態になったのだ。当時馬込文士村では、基次郎と千代の仲が噂になっていたためだそうだが、尾崎もカフェの女給とよろしくやっていたというから、男というのは身勝手なものである。
この事件で、尾崎と千代は夫婦別れし、基次郎は基次郎で殴られた翌日に大喀血した。ちなみに喀血したのは萩原朔太郎のお家でのことだそうな。
ほんと、青春ですなあ。女を争っての暴力沙汰。とかいいながら、この時みんなもうアラサーでしたけど。昔の人は今の人間に比べ成熟が早かった感があるが、文士という生き物に限ってはそうとも言えないらしい。
しかし、そんな稚気に満ちたエネルギーがあったからこそ、肉体の衰えを物ともしない創作活動に打ち込めたのだろう。
伊豆での静養期間、基次郎は「筧の話」「器楽的幻想」「櫻の樹の下には」など、重要な短篇をいくつも書いている。
就中、旅館で自室としてる部屋に住み着いた蝿の姿を描きながら、巡りゆく四季の理に支配されて死を避けることはできないちっぽけな蝿に自らの行末を重ねる「冬の蠅」は、冷静な観察眼と自在なイマジネーション、そして死を強く意識せざるを得ない人間ならではの深い考察に裏打ちされた素晴らしい作品だ。
だが、何より特記すべきは、やはりそこはかとないユーモアが全篇に漂うことだ。おもろうてやがて悲しき、なのではない。悲劇と切り離された、独立したユーモアがあるのだ。これは梶井作品の傑出した点であると私は思う。
冬が来て私は日光浴をやりはじめた。(中略)
私は開け放った窓のなかで半裸体の身体を晒さらしながら、そうした内湾のように賑やかな溪の空を眺めている。すると彼らがやって来るのである。彼らのやって来るのは私の部屋の天井からである。日蔭ではよぼよぼとしている彼らは日なたのなかへ下りて来るやよみがえったように活気づく。私の脛へひやりととまったり、両脚を挙げて腋の下を掻くような模をしたり手を摩りあわせたり、かと思うと弱よわしく飛び立っては絡み合ったりするのである。そうした彼らを見ていると彼らがどんなに日光を恰しんでいるかが憐れなほど理解される。とにかく彼らが嬉戯するような表情をするのは日なたのなかばかりである。(中略)虻や蜂があんなにも溌剌と飛び廻っている外気のなかへも決して飛び立とうとはせず、なぜか病人である私をまねている。しかしなんという「生きんとする意志」であろう! 彼らは日光のなかでは交尾することを忘れない。おそらく枯死からはそう遠くない彼らが!
高校の授業のような読み解き方をすると、「おそらく枯死からはそう遠くない彼ら」は基次郎の姿を投影した存在だ。日光の中で弱々しい姿をさらすのも、そうだ。
だが、彼らは一点において基次郎とは異なる。どれだけ弱っていても、交尾は忘れないのである。
ここでの交尾は「性」というよりも「生」の象徴だ。
冬の日光の、わずかばかりのエネルギーを借りて行う営みが交尾であるというのは、生物が根源的に持つ生への執着に他ならない。
生への執着を描くにあたり、基次郎の筆力ならば、もっと深刻なシーンにすることも可能だっただろう。
しかし、そうはしなかった。
じっと観察しながら、湧き上がってきているのは、昆虫でさえ命に執着する現実に対する、呆れるような、苦笑するような、シンパシー混じりのユーモアを感じているような、複雑な感情の塊だ。
その感情の塊はすなわち基次郎が自分自身に向けたものでもある。
誰よりも意気盛んで、無鉄砲な男性気質にあふれているのに、病気が人生の冒険を許してくれない。もうすぐ死ぬ蝿と一緒に日向ぼっこするのが関の山である。
そんな自分を見て、冷笑するのではなく、プッと吹き出している。悲観的になることもあるが、底の底まで沈み込むことはできない。沈み込むつもりもない。
この態度は、とても健全だ。彼の本質は間違いなく大阪のあほぼんであり、あほぼんは基本陽性の精神でできあがっている。だから、基次郎の精神はどこまでいっても光を失うことはないのである。しかし、人間、陽ばかりでは生きられない。ましてや、不治の病を得た若き病人がポジティブばかりで過ごせるわけがない。
では、基次郎はどこで陰を処理していたのか。
それは幻想の世界だ。幻想の世界で自由に遊び、死と親しみ、自分を含めた人を思うさま弄ぶことで精神の均衡を保っていた。
ドッペルゲンガーとしての我
たとえば、ものの本に「梶井基次郎は優れた幻想小説の書き手である」という記述があったとして、どれだけの人が「うん、知ってた」とうなずくだろうか。
彼の作風について、日本人名大辞典は「繊細な感覚による詩的散文ともいうべき作品」、日本国語大辞典は「鋭い感受性と強い生命力に貫かれた短編」、デジタル大辞典は「鋭敏な感覚的表現で珠玉の短編」と定義している。
さらに、みんな大好きWikipediaには、
その作品群は心境小説に近く、散策で目にした風景や自らの身辺を題材にした作品が主であるが、日本的自然主義や私小説の影響を受けながらも、感覚的詩人的な側面の強い独自の作品を創り出している。
と書かれている。
「幻」の文字はどこにもない。「日本幻想作家事典」で<幻視の光景>と記されているのが管見では唯一の例外だ。
もちろん、「幻想」が文学上のジャンルを分ける正式な術語にはなっていないという事情があるのは念頭に置いた上で、それでもやはり完全に現実を離れた光景=幻想を描き出す作家としての評価はもうちょっと記述されてもいいのになあと私は思う。
想像力溢れる人間が何らかの理由によって自由な行動を制限されたら、どうなるか。
内なるヴィジョンを育て、その世界に入り込み、遊ぶようになると相場が決まっている。
基次郎の幻想は、当然ながらもっとも近い「死」を中心に繰り広げられた。
長い療養生活に入る直前に書かれた「Kの昇天――或はKの溺死」という書簡様式の名作短篇がある。ゴス心を揺さぶるこのタイトルに惹かれて手にとった読者も多かろうこの作品では、ある男が療養地のN海岸で出会ったKの死に際について語る。完全に想像に過ぎないその語りの、確信に満ちた迫力はぜひ原文で読んで楽しんでほしいのだが、ここでは次の一文を引用して、注目したい。
「影と『ドッペルゲンゲル』(注1)。私はこの二つに、月夜になれば憑かれるんですよ。この世のものでないというような、そんなものを見たときの感じ。――その感じになじんでいると、現実の世界が全く身に合わなく思われて来るのです。だから昼間は阿片喫煙者のように倦怠です」
当時、ドッペルゲンゲルことドッペルゲンガーは一種の流行りだった。
芥川龍之介はじめ、複数の文豪たちがこの存在について言及しているのだが、「分身」を求める気持ちの強かった基次郎にとってはまさにうってつけの主題だったことだろう。
影とは物体が光を遮った結果生まれる実体のない幻。しかし、その形は正確に本体を写し、本体なくして存在しえない。「影」はもっとも身近なドッペルゲンガーであり、「幻」だ。
存在にとっては従に過ぎない曖昧な幻に、本体が乗っ取られていく。
自我の喪失は人間にとってもっとも恐ろしい結末のひとつだが、しかし失うことで月へも飛ぶ自由が得られるのだとしたら。
これから先、行動の自由をどんどん失っていくであろうことを予測できた基次郎にとって、これほど危険な魅力に満ちたヴィジョンはなかったのかもしれない。
妄想はさらに拡大し、「ある崖上の感情」というド直球のドッペルゲンガー小説に結実していく。
この小説は、山ノ手の町のとあるカフェで、ある青年が自分の覗き趣味について語り始める場面で始まる。
「いや、ところがね、僕が窓を見る趣味にはあまり人に言えない欲望があるんです。それはまあ一般に言えば人の秘密を盗み見るという魅力なんですが、僕のはもう一つ進んで人のベッドシーンが見たい、結局はそういったことに帰着するんじゃないかと思われるような特殊な執着があるらしいんです。いや、そんなものをほんとうに見たことなんぞはありませんがね」
なんともまあ悪趣味な、という話ではある。あるのだが、物語が進んでいくにつれ、ただの窃視愛好者の話ではないことが明らかになっていく。主客の巧みな反転、そして立ち顕れる二重存在。
俺の欲望はとうとう俺から分離した。
この分離こそ、彼の文学の主たるテーマだといえるだろう。
病をいう現実を前に、基次郎は文学的離人症を発していたともいえる。そんな彼は、自分を客体としてじっくり眺めながら、十年ほどかけてゆっくりと死へと近づいていった。
「私も男です。死ぬなら立派に死にます」
昭和7年(1932年)3月、31歳の基次郎は死の床に着いていた。
1月に「のんきな患者」が「中央公論」誌に掲載され、14日には読売新聞の文芸時評欄で直木三十五が好意的な評を寄せたのを見た。
それに力を得たのか、31日には「『のんきな患者』が『のんきな患者』でいられなくなるところまで書いて、あの題材を大きく完成したい」と綴った手紙を友人の飯島正に送っている。
創作意欲は失われていなかった。
しかし、体調は急坂を転げ落ちるような具合だった。
2月末には心臓の苦しさを感じるようになり、筆を持つことができなくなった。3月10日を過ぎると本を読めなくなり、病苦による不眠に陥った。12日には酸素吸入を始めている。
狂人ノヨウニ苦シム、スイミン不足。極度ノ疲労。ソノ上へサイミン剤ノ作用
[呼吸]膚ノ上ヲ 少年ノトキ恐怖ニオソハレタトキノヨウナ冷カナ感ジ ガアル
ソレガ各所ヘ出没スル
ソレデ モー苦シクテネラレナイ。
(梶井基次郎 3月13日の日記より)
衰弱による呼吸困難と心臓機能の低下。薬剤によるむくみ。食欲の減退。
肉体の苦しみは精神に悪影響を及ぼし、基次郎は「のんきな患者」ならぬ「わがまま極まりない患者」として、看病する母や通いの看護師、弟などに当たり散らした。
家族は、余命幾ばくもない彼の望みをできるだけ叶えてやろうとした。しかし、物事には限度がある。
3月22日、基次郎は苦しみに耐えかねて医者を呼べと家族に再三要求し、派遣されて来た看護婦が気に入らぬから帰せと頑強に主張した。
母は、覚悟を決めた。
私は暫く考えていましたが、願わくば臨終正念(注2)を持たしてやりたいと思いまして「もうお前の息苦しさを助ける手当はこれで凡て仕尽くしてある。是迄しても楽にならぬでは仕方がない。然し、まだ悟りと言うものが残っている。若し幸にして悟れたら其の苦痛は無くなるだろう」と言いますと、病人は「フーン」と言って暫し瞑目していましたが、やがて「解りました。悟りました。私も男です。死ぬなら立派に死にます」と仰臥した胸の上で合掌しました。(中略)「お母さん、もう何も苦しい事は有りません。この通り平気です。然し、私は恥ずかしい事を言いました。勇(注3)に済みません。この東天下茶屋*(注4)を駆け回って医者を探せなどと無理を言いました。どうぞ赦してください」
基次郎はこのように前非を悔い改め、従容として死んでいった、のならキレイに終わらせられたのだが、やはりそうもいかなかった。生物の命への執着は、本体の意識を超えた細胞一つ一つの叫びである。まして31歳のまだまだ若い肉体が、死をおいそれと受け入れるはずもない。
翌日も苦しみ、悟ったという言葉がなかったかのように医者を呼ぶよう求めたが、夕方になると意識がなくなり、24日の午前2時、そのまま息を引き取った。
悟れと促されて悟られるものなら、人は苦労しない。
それでも、基次郎は一旦覚悟を決め、死を受け入れた。この過程があるとないのとでは、相当違うのではないか。
どうせ死ぬなら、心安らかに死んでいきたい。命大事でジタバタしたくない。
私自身は常々そう考えている。
基次郎は十数年かけて死を見つめ続けた。それでも、大人しく死んでいくことはできなかったし、本人としても納得はいかなかっただろう。しかし、一度は「悟りました」と言えたのは、やはり「死」についてずっと考え続けていたからだろうと思われる。
現代社会は、死を見えづらくしていると言われる。
霊柩車が宮型からリムジン型に変化したのは、ひと目で死を連想させるその形が忌まれたためだそうだ。最近は、死者の命日ではなく誕生日を記念日にする人も増えてきている。まるで、死という事実を無視するかのように。
ことの可否は個々の判断によるだろう。だが、私は死を直視しない風潮を憂いている。確実にやってくる死をずっと見て見ぬふりをしてきた人間が、いざ自分の終焉を迎えた時、死を受け入れることができるだろうか。また、身近な者が亡くなろうとしている時に安らかに死んでいけるよう覚悟させてやろうとできるだろうか(もっとも、基次郎の母は自分の言葉を後悔したようだが)。
生物の死亡率は100%だ。どうやったって死ぬ。死を知らなければ、本当の意味で生を知ることはできない。だから、時には「死」についてしっかりと考えることも必要だと私は思っている。
死を見つめながらも、死と戦い、生を捨てず、それでも最後には「死ぬなら立派に死にます」と言えるように。
注1:ドッペルゲンゲル Doppelgänger
自己像幻視。自分の姿を自分で見ること。オカルト的な意味では、本人がいないところに現れる、本人そっくりの何者かを指す。現在では「ドッペルゲンガー」表記が多い。
←戻る
注2:臨終正念
仏教用語で、浄土に旅立つため、臨終に際して一心に仏を念ずること。しかし、基次郎の母は「心安らかに死を受け入れる」という意味合いで使っているようである。
←戻る
注3:勇
基次郎の弟の名前。晩年、近所に済んでいた。
←戻る
注4:東天下茶屋
大阪の地名。基次郎の旧居跡は現在の大阪市阿倍野区王子町にある。
←戻る