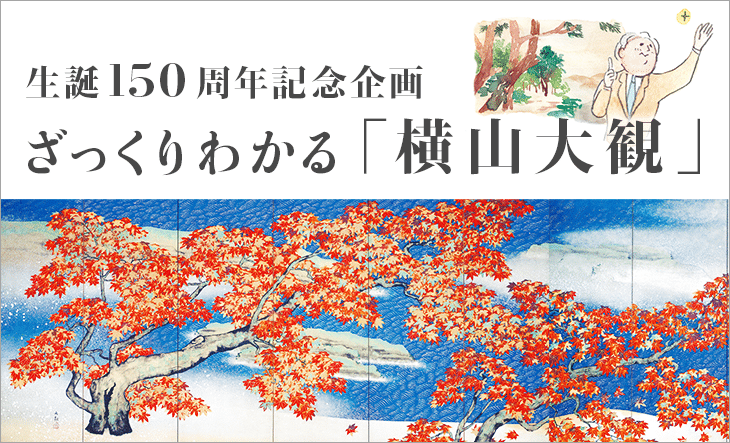第84回
解説(3)
2019.04.05更新
日本人の精神世界に多大な影響を与えた東洋哲学の古典『老子』。万物の根源「道」を知れば「幸せ」が見えてくる。現代の感覚で読める超訳と、原文・読み下し文を対照させたオールインワン。
「もくじ」はこちら
二 老子の人物像
1 議論を呼ぶ老子の出自と実態
中国古代の歴史を見るに、最も権威があるのは司馬遷の『史記』である。しかし、その『史記』でも老子という人物について一人に絞りきれず、候補として三人を紹介している。老聃(ろうたん)、老萊子(ろうらいし) 、儋(たん)の三人である。
その中で一番有力とされているのが老聃である。『史記』によれば、老子は、姓は李、名は耳じ であり、聃とは字(あざな)である。「聃」とは耳が長いという意味である。以下、『史記』による。
老子は、楚の苦県(こけん)、厲郷(らいきょう)の曲仁里の人であるという(ここが本当にあったのかどうかはわからない)。
老子は周の守蔵室の官史だったという。守蔵室とは図書や公文書を保管する部屋である。
老子は周が衰えるのを見て官を辞し、旅に出て、関所で関守の尹喜(いんき)に頼まれて一気に五千字あまりの「老子」を著したという。老子は、その後も旅を続け、どこで死んだのかもわからない。
『史記』では、孔子が老子に教えを乞うために会いに行っている話も出ている。孔子は老子の人物の大きさに圧倒され、老子のことを「龍のようだ」と話したとされる。
しかし、今では、この話は老子の流れをくむいわゆる道家の人たちのつくった話だったとされている(そもそも老子は孔子よりも一〇〇年から二〇〇年近く後の人だとされている)。
「老子」の約五千字についても、後の道家の人たちの書き足した部分が多いのではないかといわれる。確かにその通りかもしれないが、「老子」全体を読むと、一人の人物の思想が中心となっているのは間違いないのではないか。
『史記』は老子が「隠君子」であったとしているが、「隠君子」とは世を避けて功名を求めない知識人といった意味であろう。日本でもこうした「隠君子」とか「隠者」を理想として、知識人の生き方に大きな支持を得ている。後に紹介する『徒然草』の兼好法師や松尾芭蕉などはその例である。
「隠君子」の理論的拠りどころとして「老子」は完成していったが、それでも一人の人物としての老子を想像している。
同じく日本の中国哲学者である木村英一氏の見解は、私の想像に近いものがあるので、少し長くなるが引用紹介したい。
「時代は前四世紀で、孟子や荘子とあい前後するころのこと、楚の農村出身者で隠逸の士である一長老があった。姓は李、名は耳、字は聃(たん)(耽とも書かれる)というから、身分は士族であろうが、おそらくもとは殷の遺民としての知識人で、周の史官を勤めた家柄から出ており、殷の故城の商邸に近い農村を故郷としてもつ聡明な知識人であったであろう。いったい周の官吏は、もとは殷の知識人で、奴隷としての才能を利用された専門職から出たものが少なくない。彼等の特殊技能は周の支配者に重宝された結果、その官職は世襲され、彼等は次第に周の士族の一部となってゆく。この人物もおそらく殷の遺民で史官の家に生まれたため、周の蔵室の史となっていたのであろう。そして多年勤めあげた末に、乱れて行く世の末を思い、都会における官僚の生活に見切りをつけて、辞職して故郷の農村へ帰り、そこで長老として晩年を送ったであろう。何しろ若年から都に居て、官廷の知識の府である図書館を、多年にわたってあずかってきた賢い老人が、田舎へ帰ったというわけである。近隣の知人は親しみと尊敬とをこめて「老聃」と呼び、遠村の人々は伝聞して「老子」と尊んだであろう。そして彼の語る老成した人生の知識や、鋭い政治批判・文明批判の言葉は、遠近の村落や郷邑にかくれている逸民達の間に、金言・名言として珍重され、それが世上に行われている俚諺や格言と相混じって、民間知識人の一種である逸民群のなかにおける一つの思想的中核となって行った。そしてそこでまた種々の材料が附加されたであろう。秦漢の際に及んで、道家思想が発展して一大学派と成るに当り、学祖と経典とを作る必要が起こった時、この人とこの文献が、モデルともなり素材ともなり、また再編集におけるヒントともなったであろう)」(『老子』講談社文庫、木村英一訳/野村茂夫補)
【単行本好評発売中!】
この本を購入する