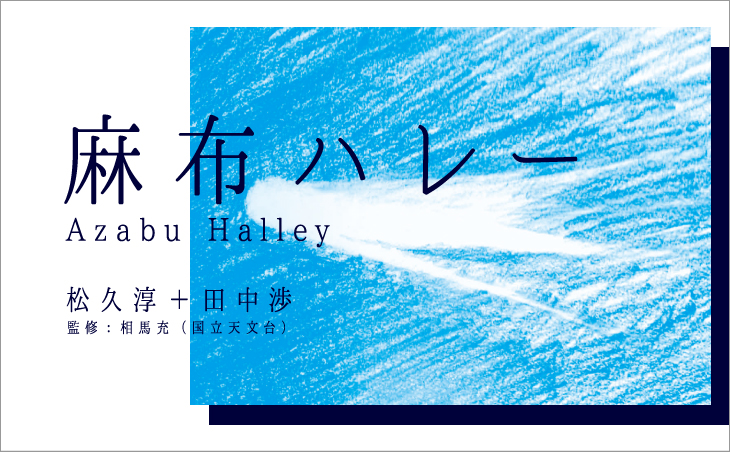第1回
1986年 駒場
2017.01.18更新
【この連載は…】76年ごとに地球へ接近するハレー彗星とともに現れる、美しく不思議な女性。そして運命的な出会い。時代を超えた、はかない恋の物語。
「目次」はこちら
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1986年、東京駒場キャンパス
1910年、麻布天文台
1933年、早池峰
1986年、再び早池峰へ
時を超えて回帰する、
ハレー彗星をめぐる人びとの
長い長い、約束の物語
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・第1回
1986年 駒場
3台並んだ14インチのモニター画面のひとつに、探査機「りゅうせい」が1分おきに送ってくる、ハレー彗星の水分放出量の変化が、8桁の数字で刻まれている。その、部外者にはまったく面白味のない数字の羅列を、4人の男たちがおもちゃに夢中の子供のように体を寄せ合い見守っていた。
「ほぼ予測どおりの結果と見ていいのかな」
椅子の真後ろに立って腕を組んでいた秋尾量は、誰に言うでもなく呟いた。
秋尾の左側で前のめりになって画面を見ていた村林は、「うーん」と肯定とも否定とも取れるような調子で反応し、右側で痛む腰を右手で揉みほぐしていた加上(かがみ)は、同じ「うーん」という言葉を、伸びをする軽い呻き声のように発した。
そんな50代半ばの3人の真ん中に座って、キーボードを操作してデータを記録しているのは、大学を出てそのまま研究所に残った、まだ23歳の川葉敦雄(かわばあつお)だ。川葉は父親ほどの年の天文学者たちが、その天才的な頭脳と経験に反比例して、コンピューターの操作と、モにター画面の表示にいまひとつ不慣れなのを気づいていた。
「ちょっとお待ちください」
川葉はそう言うと立ち上がり、3つ隣のデスクに置いたプリンターに向かった。そこには、「りゅうせい」が送ってきていた、ハレー彗星の水分放出量と自転周期の昨日からのデータをまとめたものと、それをグラフ化した書類が、ちょうど出力されたところだった。
川葉はそれを秋尾に手渡した。すると今度は3人の男たちはモにター画面に背を向け、その後ろにあるスチールの長テーブルにプリントを広げ、先ほど以上に「おお」と感嘆の吐息を漏らし、さっそくそれぞれ鉛筆やボールペンを片手に、手近な紙にメモを取ったり計算に取り掛かったりし始めた。
川葉はそんな大先輩たちの背中に、敬意と同時に可愛らしさを感じ、少し笑ってしまいそうになるのを堪えて、再び椅子に座るとモにター画面との「にらめっこ」を再開した。
ハレー彗星が76年ぶりに地球に接近する。
前回ハレー彗星がその姿を人々に見せたのは、明治時代、1910年のことだった。それからの科学技術の進歩のスピードは、それまでとは比べものにならなかった。紀元前から観測されてきたその巨大彗星に対し、1910年までは望遠鏡が発明され、その精度が上がっていったにすぎない。
しかしいまや、人類は宇宙空間へロケットを飛ばし、そこから直接画像やデータを得て、それを地球に届けることができる。太陽系の海王星軌道の外からやってくるハレー彗星は、宇宙の謎を解き明かすために重要かつ貴重な天体であるばかりでなく、その観測のために科学技術を躍進させるためにも、絶好の機会だった。
とくに技術大国と言われながらも、宇宙ロケットに関してはアメリカやソ連に遅れをとっていた日本は、このハレー到来を機に、官民一体でこの一大事に取り組んだ。地球の重力圏を脱出する初の国産ロケットを開発する。探査機をハレーに接近させる。彗星の物質データを分析し、高性能カメラでその姿を捉える。探査機に指令を送るために、長野県臼田の山奥に64メートルの巨大アンテナを建設する。
これらは宇宙科学研究所所長の秋尾をリーダーに、各分野の科学者と企業が集い一大事業として行われた。そしてハレー彗星が太陽に最接近する1年1ヵ月前に探査機「きらめき」が、6ヵ月前には2機目の探査機「りゅうせい」が、鹿児島の内之浦から無事に打ち上げられた。
ハレー彗星の観測に関しては、世界各国の相互協力が密に行われた。それぞれが打ち上げた、日本、アメリカ、ソ連の各2機、ヨーロッパの1機、合計7機の探査機のデータは共有され、地球の自転でその地域が探査機やハレーに「背を向けた」ときなどは、それぞれの観測所が他国の探査機のデータ収集も行った。いつしかその探査機群は「ハレー艦隊」と呼ばれるようになった。
日本の観測の中枢である管制室は、東京大学駒場キャンパスの隣にある宇宙科学研究所の中に作られた。その管制室の主要スペースは20平米ほどしかなかった。コンピューターはわずかにメインが5台で予備が2台。前方には2つのスクリーンが設置されているが、それぞれ50インチにも満たなかった。大きなガラス窓で仕切られた隣には小ホールがあり、そこでは会議や記者会見が行われ、ときには所員が布団を敷いて寝泊まりすることもあった。
所員たちはそこを、半ば自虐的に「世界一小さな管制室」と呼んでいた。そして「きらめき」と「りゅうせい」はその短い円柱のようなシルエットと、黒い器に金色の蓋をしているような見た目から、「おひつ」というニックネームがついた。
川葉がモニター画面を凝視している隣では、先輩所員たちが、アメリカのスペースシャトルの打ち上げ事故の原因について、最新の報告書を手に議論しあっていた。
その声がふと止まったときに、管制室内の空気も変わったことに川葉は気がついた。顔を上げ振り向くと、秋尾たちも同時に、隣のホールへ目をやった。そしてそこに現れた人物に気づくと、3人ともすぐに背筋を伸ばし、先を争うように入口のドアへと向かった。
川葉がガラスの向こうを見ると、そこにはゴルフパターを持った平川郁彦(いくひこ)がまず見えた。平川は探査機開発部門の責任者で、秋尾とともにこの計画を中心に推し進めた人物だった。メンバーの中ではいちばんの天才肌だがそのぶん変わり者で、皆がデータにかじりついているときでも、テニスコートの脇にある小さなグリーンで、呑気にパターの練習をしていたりする。
その平川が丁重に案内するように、小柄の老人も一緒にホールに入ってきていた。かなりの高齢であるのは間違いない。しかし、杖をついているが、歩く様子はしっかりとしていた。仕立ての良さそうなスーツをきちんと着こなし、白髪をきちんと手入れしている。そして何よりも表情に精気が溢れていた。
平川の様子と、慌ててドアを開けて近寄る秋尾たちの姿を見て、川葉はようやく、その写真で見たことがあったその老人が誰なのかが、わかった。
糸口博士。川葉にとっては、もはや歴史上の人物のようにすら思えるほどの、偉大かつ遠い存在だった。戦時中に革新的な戦闘機を設計し、戦後は国産ロケットの開発の第一人者となる。つまり現代日本の航空力学の権威であり、生きる伝説とも言える人物だ。
おそらく年齢は80歳を過ぎているはずだった。いまは引退して長野県で余生を送っていると聞いていた。秋尾教授と平川教授は、糸口博士の直属の弟子でもあったことを、川葉は思い出していた。
糸口博士は平川に付き添われ、そして秋尾に出迎えられて管制室へ入ってきた。川葉たちすべての所員が立ち上がって、深々と一礼した。
「お邪魔します。私を気にせず、手を止めないでください」
糸口博士ははっきりとした口調でそう言うと、全員に微笑みかけた。

しばらくの間、秋尾と平川が糸口博士に管制室内の機材や、スクリーンに映るデータの説明をして、糸口博士はひとつひとつを食い入るように見つめ、そしてその都度、的確な質問を投げかけた。ふだんは貫禄のあるリーダー然としている秋尾も、我が道をゆくタイプの平川も、このときばかりは師を前にした学生の顔に戻っていた。
やがて、その糸口博士が川葉の元へやってきた。
「うちの若きエース、川葉くんです」
秋尾がそう紹介し、川葉は緊張で体を強張らせたまま、頭を下げた。
「ダスト接触の際も、彼が中心になってりゅうせいの軌道修正を行ったんです」
秋尾がそう続けると、糸口博士は「ほお」と感嘆の吐息を漏らした。
4日前、りゅうせいのデータがこれまでとは明らかに「違う」ことに秋尾が気づいた。太陽電池に問題はない。取得しているデータも順調だ。しかし定期的な画像撮影の「向き」が、わずかに違う。
前日からのデータをすべて洗い直してみると、りゅうせいは大きな衝撃を2度、受けていることが判明した。原因を解明した結果、それはハレー彗星から飛来した5ミリグラムほどの小さなダスト、すなわちゴミが衝突したものだと結論づけられた。
幸いにも推進機器にも観測機器に故障はない。しかしりゅうせいの「姿勢」を正さなくてはならなくなった。その正しい運用に戻すための作業に、川葉は皆が驚くようなアイデアで素早い計算をやってのけた。
「来年のスイングバイも、川葉くんに任せてみてはどうかな」
糸口博士が言った。りゅうせいはハレー彗星を観測後、地球の重力を利用したスイングバイという推進方法で、太陽を公転する軌道に載せられる計画になっていた。川葉にしてみると、伝説の博士が自分の名前を口にしてくれただけでも震えるような嬉しさだったが、さらに冗談でもそんな重大任務を勧められて、「いえ、そんな」ともごもごと返事をすることしかできなかった。
「僕も適任だと思うよ」
平川がまだパターを持ったまま、のんびりした口調で言った。
「僕なんかまだまだ、大学出たばっかりですし」
川葉は緊張したままなんとかそんな風に返事をすると、糸口はしっかりと川葉の目を見ながら口を開いた。
「どんな世界でも同じだが、とりわけ宇宙(そら)は、すべてにおいて長い時間がかかる。私も人生を費やしてもまだ見ぬこと、わからぬこと、やりかけに終わったことのほうが、たくさんある。続く秋尾くんや平川くんが新しい時代を拓いた。しかしそれでもまだ先は長い。いつの時代でも、君のような優秀な若者が次の展開への種となり希望となるんだ。遠慮なんかしている暇はないよ」
糸口博士はそう言うと、にっこりと川葉に笑いかけた。川葉はきゅっと口元に力を込めて、無言のまま力強く頭を下げた。
川葉はふと思ったことを口にしてみた。
「博士。博士は前回接近時のハレーは、ご覧になられましたか?」
年齢的にそうであっても不思議ではなかった。すると糸口博士は、嬉しさと懐かしさを同時に表情に浮かべ、次に少年のような顔になるとどこか得意気に言った。
「見たよ、ハリー。肉眼でね」
糸口博士は当時一般的だった呼び名のまま、「ハリー」と発音した。
今回のハレー彗星の接近は、日本からはあまりよく見ることができない。川葉だけでなく、秋尾や平川も博士と同じような少年の顔になって、羨ましさを素直に表情に浮かべた。
管制室を出た糸口博士を、ホールで孫の大隅隼(おおすみじゅん)が待っていた。
隼は「天体月報」という雑誌の編集部に勤めていて、秋尾たちともほぼ全員面識がある。子供のころから本や雑誌ばかり読んでいて、得意科目も国語と社会のみ、数学と理科は高校時代にぎりぎりで落第を免れた程度という、いかにも文系な男だ。しかし祖父が伝説のロケットエンジンの博士であったのが影響したのか、その文才や編集能力を活かしつつも、苦手な理系の天体専門誌で仕事をしている。
秋尾たちに見送られて、糸口博士と隼は、駒場キャンパスの銀杏並木を抜け、門の前でタクシーを停めた。
「上野駅にお願いします」
タクシーに乗り込んで隼が運転手にそう告げると、糸口博士は少し不満そうに鼻を鳴らした。長野から来たときにも、新宿駅に迎えに来た隼にタクシーに押し込められ、「電車でもすぐだ」と言い張るのをなだめられた。
「じいちゃん、俺が母さんに怒られるんだから文句言うなよ」
隼が言った。84歳の父が、長野から東京の宇宙科学研究所に陣中見舞いに行くというだけでも、娘としては1人で行かせるわけにはいかなかった。それどころかその父が、駒場の後はそのまま上野駅から、昨年開通したばかりの東北新幹線で岩手に行くと言い出した。何度も諦めさせようとしたが糸口博士は折れず、やむを得ず娘は東京に住む自分の息子の隼を出迎えに行かせ、岩手にも同行させることで渋々納得した。
糸口博士はタクシーの中でも、老眼鏡をかけつつ、先ほど秋尾に渡されたハレー彗星の観測データに目を通していた。
「それが目的じゃないよね?」
渋谷から首都高速に乗ったタクシーが神田橋で一般道路に降りたところで、隼は祖父にそう聞いた。
「目的?」
「わざわざ早池峰(はやちね)に行く理由」
糸口博士は「ああ」と孫の言葉の意味に気づいて頷いた。
岩手の早池峰山には大きな電波望遠鏡を擁した天文台がある。ハレー彗星の観測はそこでも行われているが、今回のハレーは地球上から観測しやすい軌道を通らないので、ハレー艦隊からのデータほど重要なものはない。さらに、今回のプロジェクトで、日本各地の天文台はほぼ同時にネットワークでデータのやりとりができるようになっていた。つまり駒場にいればほぼすべての情報や画像を手にすることができる。
さらに言えば糸口博士はすでに引退の身だ。確かに伝説の人物が訪ねてくれば天文台の台員たちの士気も上がるかもしれないが、84歳の老人がわざわざやるべきこともない。
「隼にはいい取材になるだろう。行ったことはあるのか」
糸口博士は話をはぐらかすように、のんびりとした口調で言った。
「早池峰は初めてだけど……じいちゃんは?」
「数回ある。初めて行ったのは53年前だった」
隼は、祖父がやけに正確な数字を口にするのが気になった。
タクシーが上野駅に着き、糸口博士と隼は駅構内のレストランでスパゲティを食べ、12時過ぎの東北新幹線に乗った。糸口博士は今日の早朝、長野県上田から上京し、駒場に顔を出し、そしていまは東北へ向かっている。しかし疲れた様子を少しも見せない。隼は祖父の年齢的には強靭と言える体力に感心しつつ、どこか呆れてもいた。スパゲティも残さず食べ、パンをおかわりするほどだった。
「じいちゃん、そろそろ本当のことを教えてくれないかな。早池峰に行く理由」
音もなく新幹線が動き出したタイミングで、隼はこれで祖父が答えなかったら、もうこの話を聞くのをやめようと思いつつ、その横顔を見た。
糸口博士は孫の顔を見て、しばらくの間、何かを考えるような表情を浮かべていた。そしてやがて肩の力をゆっくり抜いて座席にもたれつつ、口を開いた。
「約束なんだよ」
「約束?」
糸口博士は小さく頷いた。そしてそこから、孫に向かって長い話を語りだした。
「ハリーが前に来たときの話だ」
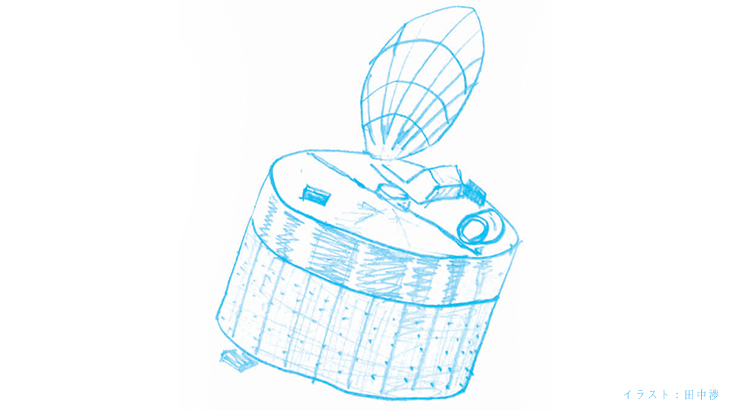
*本小説は実在の施設・人物などを参考にしていますが、すべてフィクションです。
*本連載は、雑誌「月刊天文ガイド」にて連載されたものの再掲です。
月刊天文ガイドHP http://www.seibundo-shinkosha.net/tenmon/
【単行本好評発売中!】
この本を購入する