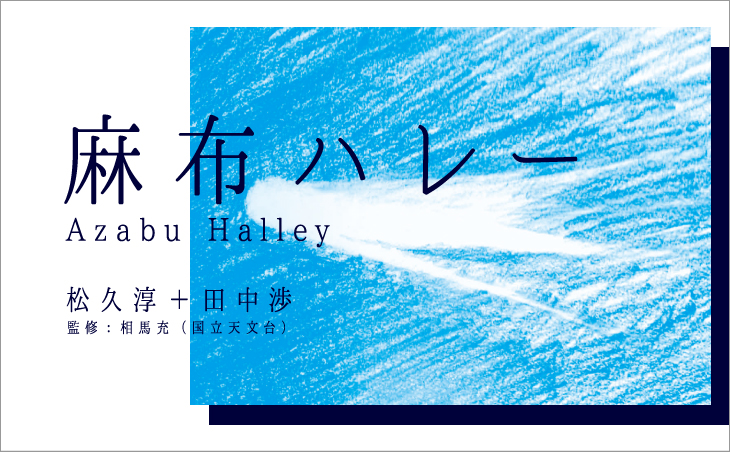第7回
1910年 麻布(6)
2017.03.01更新
【この連載は…】76年ごとに地球へ接近するハレー彗星とともに現れる、美しく不思議な女性。そして運命的な出会い。時代を超えた、はかない恋の物語。
「目次」はこちら
・・・・・・・・・・・・・・・・
早池峰天文台の木戸によって談話会に連れてこられた少年・柳木賢男は、人並み外れた想像力と発言で、栄や大人たちを驚かせる。一方、國善は自分の話を宮田が作品として形にした原稿を初めて目にし、その素晴らしさに感動する。天文台で過ごす日々は、栄と國善を着実に変えてきていた。
・・・・・・・・・・・・・・・・
最終回
1910年 麻布(6)
國善が十以上の話を語り終えると、すっかり熱中していた宮田は時計を見て、「いかんいかん、役人仕事に戻らねば」と慌てて天文台を後にした。國善は宮田の原稿を読んだせいか、話をするのにも熱が入っていたし、終えた今でも、高揚感を感じていた。
宮田さんが言うとおり、僕たちは何か新しいことができるかもしれない。
これほど前向きな気持ちを持てたのは、ただ一度短編が採用されて以来、初めてかもしれない。國善はつい顔に笑みを浮かべてしまい、この気持ちのまま晴海に会いたくなった。その前に、ひどい言い方をしてしまったことを謝らなくてはならない。
言葉を「予習」するのはあえて止めた。國善は、晴海がいることを祈って、赤道儀室(せきどうぎしつ)へと向かった。
「國さん、こんにちは」
いてほしいときに、きちんと晴海はいてくれた。あれ以来ずっと会っていなかったのに、晴海は優しく微笑みかけてくれる。
「あ、は、晴海さん、あの……」
「國さん」
謝罪の言葉を口にしようとした國善を、晴海はやんわりと遮(さえぎ)った。そして言った。
「國さん、私にも何かお話を聞かせてくださる?」
晴海が言った。國善は「え、え?」と慌てた。
「宮田さんや天文台の皆さんは聞いてるのに、私だけ仲間はずれじゃ、ずるいわ。それに私は、國さんはお話が上手だって、最初から言ってたでしょう」
晴海はそう言うと、目は笑いながらも口を尖(とが)らせた。國善は、自分の非礼をこんな形で許してくれる晴海の心遣いに、思わず涙ぐみそうになったが必死に堪えた。そして、余計な言葉は口にせず、ただ深く頭を下げた。
そして國善は必死にいくつもある話の中から、晴海が喜びそうな幻想的な話を選び出した。
「『竹取物語』のごとき、て、天女(てんにょ)の話があります」
「天女? 素敵」
晴海は居住(いず)まいを直して國善の顔を興味深げに見た。
「盲目の母と暮らす孝行者の優しい男がおりました。ある日、魚とりに行った帰り、突然の雨に濡れて木の下で雨宿りをしていると、美しい娘がやってきて、私をおまえの家に置いてほしいと頼んできました。男が断っても、娘は勝手に家までついてきて、やがて2人は夫婦になりました」
國善はやはり、淀(よど)みのない口調で語り始めた。晴海は少し驚きつつも、嬉しそうに國善を見つめ、耳を傾けた。
「女は毎日機(はた)を織り、織り上げた衣はたいそう高値で売れ、いつしか家も裕福になっていきました」
「まあ、『竹取物語』ではなく、『鶴の恩返し』のようだわ」
晴海が相槌(あいづち)のように呟(つぶや)いた。
「やがて夫婦には男の子が生まれました。さらに女が観音様(かんのんさま)に願掛(がんか)けをしたおかげで、母の目も見えるようになったのです。しかしそんな幸せな日々のさなかに、女は突然言いました。私はこの家を長者にさせるために、天から遣(つか)わされた者です。私の下界での年季が切れたので、暇乞(いとまご)いをいたします、と」
晴海は黙って國善の話に聞き入っていた。國善はこのときも、自分が物語を語るときには言葉も滑らかで、つっかえることがほとんどないことを、まだ自覚していない。
「夫も母親も必死に引き止めましたが、女は十二単(じゅうにひとえ)を着て、美しく化粧をし、座敷の縁側に出ると、天から紫の雲がたなびいてきて、それに乗って天に登っていったそうです」
國善は話し終えた。晴海はしばらくの間、この話を堪能するかのように目を閉じていた。
「その姿は、さぞ美しかったことでしょうね」
やがて晴海は呟くように言った。天に帰る女の姿を想像していたようだった。
「いつごろのお話なのかしら。平安時代かしら。なんだかそんな顔立ちとお着物が似合いそう」
「は、晴海さんも、へ、平安美人です」
國善はふと、これまで思っていたことをそのまま口にした。口にしてしまった後で、身体中にかっと血が巡った。自分はいったい、突然何を言ってしまったのだろう。國善は慌てた。そして慌てれば慌てるほど、弁解の言葉は頭から口へはなかなかたどりつかず、あわあわと呻(うめ)き声のようなものを漏らすことしかできなかった。
「國さん、あんまり褒められた気がしないわ」
「そ、そんなことは、あの」
晴海の言葉に、國善は真っ赤になって頭を下げた。しかし晴海のその口調はどこかおかしそうで、恐る恐る顔をあげると、果たして晴海はにっこりと笑っていた。
そこへ、どたどたと階段を駆け上がってくる草履(ぞうり)の音がして、勢い良く栄が飛び込んできた。いままで木戸と柳木少年と話し込んでいたと、嬉しそうに國善に報告した。
栄はこれまでの星の観測に加え、通信機にも夢中になって、図書室の本で勉強したモールス符号もあっという間に覚えてしまっていた。
「國さん、晴姉さん、何でも打ってあげるよ」
栄はそう言うと、何度も國善に「例題」をせがんだ。最初のうちは、「私は佐澤國善です」くらいでも、栄は喜んで送信機の取っ手を、トンとツーに分けて打ち込み、「どう?」と得意げに國善を見た。どうと聞かれたところで國善には正解がわからないので、ただ「す、すごいね」としか答えられなかったが、栄が求める「例題」はもっと高度になっていった。
「親譲りの無鉄砲(むてっぽう)で小供の時から損ばかりしている」
國善は昨今、覚えがある有名な小説の一節を諳(そら)んじるようになった。しかしこれほどの長文でも、栄は事も無げに打ち込んでしまい、また次の一節をせがむ。
「小学校に居る時分学校の2階から飛び降りて」
トン、ツー、トン、ツー。
「1週間ほど腰を抜かした事がある」
トン、ツー、トン、ツー。
そのうち、『坊ちゃん』を1冊全部読み上げることになるんじゃないかと國善は思った。
「そんなに上手なのに、受け取る人がいないのが残念だわ」
晴海が栄の様子を見て微笑んだ。そして送信機を見つめた。
「でもなぜかしら。私、この無線機を見ているとなんだか、懐かしい気持ちになるの。不思議だけど」
その言葉に、國善は思わず晴海の顔をじっと見つめてしまった。
「なあに? 國さん、怖い顔して」
「あ、その、ご、ごめんなさい、えっと」
いつも以上に慌てていて、なかなか言葉が出てこなかった。それは、ずっと頭の片隅でもやもやとしていた「何か」を、晴海がそのまま言葉にしていたからだった。そして晴海も同じことを思っていたのかと思うと、さらに頭がいっぱいになってしまった。
「ぼ、僕も、同じように、その……」
急いで弁解したいのだが、やはり言葉がまとまらない。晴海は柔らかい笑みを浮かべた。慌てなくても大丈夫よという表情だった。國善はごくりと唾(つば)を飲み込んで、なんとか自分を落ち着かせてから、一語一語、確かめるように口を開いた。
「あの、晴海さんが懐かしいって、じ、実は、僕も、なぜだかわからないけど、同じことを、お、思っていたのです。こんな、見たこともない機械だから、最初はただ、おかしな気持ちに、なっていたのかなって。で、でも、いまそう言われて、ぼ、僕も実は、なぜだか、これが懐かしい」
「嬉しいわ、國さん」
晴海がにっこりと笑った。國善はきちんと自分の言葉が伝わったことにほっとして、そっと息をゆっくり吐いた。
「私もなぜなのかはわからない。でも、國さんも同じように思うってことは、見えないものだからかしら」
晴海は小首を傾(かし)げながら言った。
「み、見えないもの?」
「だって、もしアンテナがついていたとしたら、さっきの栄君の通信は、電報みたいに誰かに届くかもしれないんでしょう。でも、それは目には見えずに、空中を飛んでいくのよね?」
「ど、どんな仕組みか、わからないけど、そう、なのかな」
「私は、そういう目に見えないものになぜか惹かれるの。國さんのお話が好きなのは、きっとそのせいだとも思うわ。私ね、國さんが教えてくれる河童や座敷(ざしき)わらしのお話、怖いけどすごく好きだもの」
國善は、すぐには晴海が言わんとしていることがわからなかった。自分の話が好きだと言ってくれたことに舞い上がってしまってもいるが、古い言い伝えと最新の科学技術を同じように捉える考え方に、面食(めんく)らってしまっていたからだった。しかし晴海は神妙な面持ちで続けた。
「いま自分でもわかった気がするわ。もしかしたら、昔なのか未来なのか、それとも全然違う世界でなのか、國さんと私はこの無線機を見ていたかもしれない。私たちには、そのときの記憶が残っているのかもしれないんじゃないかしら」
「ぼ、僕の話なんかより、よ、よっぽど、奇天烈(きてれつ)だけど、お、面白いです」
國善は目を丸くしてそう呟いた。そしてふと、談話会で柳木少年と語り合ってみたいと思ったのは、この「目に見えないもの」についてだったことに、國善は気づいた。
「僕だって、そのとき、一緒にこれを見たよ」
2人のやりとりを黙って聞いていた栄が、我慢しきれなくなったように口を尖らせて言った。すると晴海は、ぽんぽんと栄の頭を撫でて微笑んだ。
「それはきっとそうよ。だって私も國さんも、無線機は扱えないわ。栄君が通信してくれなくちゃ、何て言ってるのかわからないし、伝えたいことも伝えられないわ」
「うん」
栄はご満悦(まんえつ)な顔になって、こっくりと頷いた。そして急に顔色を変えると、「お、おしっこ」と勢いよく立ち上がって、そのまま外へと飛び出していった。
ここしかない。國善は思った。そして袂(たもと)から封筒に入れた切符を2枚取り出した。
「お、お話しした、ほ、本郷座(ほんごうざ)の芝居なのですが、ゆ、友人より切符を、に、2枚譲り受けました。そ、そ、その、晴海さん、よろしければ、ご、ご一緒しま、せんか」
前回のような失敗はもうしない。そう思って何度も一気に言い切る練習をしてきた台詞(せりふ)だった。そのかわり、これ以上の言葉は用意していない。國善はただどきどきしながら、晴海の返事を待った。すると晴海は國善が拍子抜(ひょうしぬ)けするくらい、笑みを浮かべてあっさりと頷いた。
「嬉しい。すごく楽しみ」
「あ、そ、そうですか」
國善はひどく間の抜けた返事をしてしまった。そしてじわじわと喜びが体の奥から湧き上がってきて、次は震えを堪えるのが大変だった。
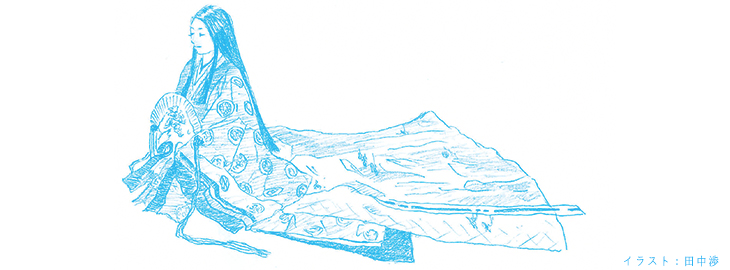
芝居はとっくに始まっていたが、いつまで経っても晴海は現れなかった。
國善は本郷座の立派で洒落(しゃれ)た洋館の壁にもたれて、その中へ入ってゆく人々と、前の通りを行き交う人々をぼんやりと見ていた。開演から1時間ほど経ってから、國善は握りしめていた2枚の切符を見つめた。友人から貰ったものなどではなかった。食費と本を買うのを我慢して、なんとか手に入れたものだった。
ものめずらしそうに本郷座の建物を見上げている老夫婦に、國善は近づいていった。そして「も、もう終わりかけですが、よ、よかったら中もご覧に、なり、なりませんか」と声をかけ、すっかり汗でくしゃくしゃになってしまっていた切符を、半ば強引におじいさんの手に押し付けるようにして、その場を急ぎ足で立ち去った。
風邪をひいたり急に具合が悪くなったりしたのだろうか。國善は、そんな風に晴海の心配をしなければいけないと頭ではわかっているのに、どうしても落胆のほうが大きすぎた。女性と2人きりでどこかへ行くこと自体が初めてだったので、相手のことを慮(おもんばか)る余裕などなかった。
御茶ノ水から皇居沿いを抜けて、とぼとぼと1時間半以上かけて下宿へと歩いて帰った。おかみさんが「國さん、おかえり」と声をかけても、國善はすっかり血の気の抜けた顔のまま部屋に入り、布団につっぷすとその日はそのまま動かなかった。
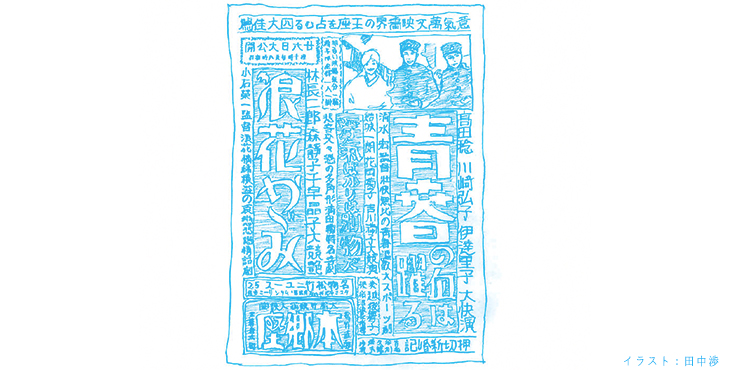
しかし翌日、國善はただ困惑するしかなかった。
本当なら天文台へは行きたくなかった。もし晴海が、わざと本郷座へ来ることをやめていたのだとしたら、何の落ち度があったのかは覚えがないが、自分と会うことを拒(こば)む意味だったとしたら。國善はそれを当人の言葉や態度から知らされてしまったら、とても立ち直れないと思っていた。
しかし、普通ならば急な用事や病があってどうしても来られなかったと考えるのが普通だ。それならば、きっと晴海は謝罪の言葉を用意して自分が来ることを待っているだろう。
國善は心がざわめいたまま、学校帰りの栄にすぐに手を引かれて、天文台へと向かった。赤道儀室に入ると、そこには晴海がいた。そして、にっこりと國善と栄に「こんにちは」と微笑みかけた。それはいつも2人を迎え入れるときと、変わらぬ態度だった。國善は、何が起きているのかよくわからなくなっていた。もしかして、日にちを間違えて伝えたのだろうか。いや、そもそも自分はちゃんと晴海を誘って承諾を得ていたのだろうか。
栄は最近は、望遠鏡よりもまず最初に無線機の「練習」に取り掛かる。栄は國善に『坊ちゃん』の続きをせがんだ。國善は自分が何を考え、どんなことを思っていいのかすらわからなくなってしまって、ただ無心に、栄の要望どおりに、無線機の隣に置いておいた『坊ちゃん』を読み上げ始めた。
「ねえ、國さん、栄君」
國善が3行ほど読み進め、そのたびに栄が、ますます速く上手になった打ち方であっという間にモールス信号を打ち込んだところで、晴海は小首を傾げて言った。
「何か、素敵な言葉を打ってほしいわ。國さん、ご存じない?」
「す、素敵な、こと、言葉、ですか」
國善は面食らった。こんな風に普通に話しかけているということは、やはり芝居に誘ったことはうまく伝わっていなかったのだろうかと、自分自身を疑い始めた。さらに、女性が言う、素敵な言葉とはいったいどんな分野の言葉なのだろうか、まったく想像もつかない。國善は混乱しながらも、知っている小説作品から、晴海が喜びそうなものを必死に考えた。
ふと、天啓(てんけい)のように、頭にある一文が浮かんだ。それは小説の一節ではなかった。國善は晴海には言わずに、こっそりと栄に耳打ちした。
「なあに、内緒話なんかして」
晴海が口を尖らせた。國善は真っ赤になっていたが、栄は嬉しそうに國善にこっくりと頷いた。そして三六式無線機の前に、改めて居住まいを直して座り直し、演奏を始めるピアにストのような面持(おもも)ちと雰囲気で、送信機に手をかけた。
-・・ --・-・ ・-・・ ・・
-・-・・ --- ・-
・-・-- ・・ ---・- --・-
栄はそれを、ゆっくり間を取って、3回繰り返した。そして得意げな顔になって國善を見た。國善は、自分が告げた文言がこんな信号になるのかと妙な感心をして、晴海に目をやった。晴海は、やけに神妙な顔をしていた。そして消え入りそうな声で國善に聞いた。
「國さん、いまの……」
「あの、な、夏目漱石(なつめそうせき)、です。しょ、小説ではないのです。あ、アイ・ラブ・ユー、という英語を、が、学生が、わ、我君を愛す、と訳したとき、そんな、ちょ、直接的な訳文ではなく、つ、月が綺麗(きれい)ですね、とでも、しなさいと、教えた、そうです」
國善は赤い顔をしたまま、そう説明した。晴海の前で、アイ・ラブ・ユーだの愛すだの、そんな言葉を発して冷静ではいられなくなっていた。しかし、晴海の様子は変だった。國善は、それこそ「まあ、素敵だわ」とでも晴海が喜んでくれるのかと思っていたが、急に思いつめたような顔になっていた。
「私、なぜだろう、この信号を知ってる」
「え?」
「國さん、いまの本当? 本当に、月が綺麗ですね、だった?」
國善は目を丸くした。晴海の言うとおり、いま栄に打たせたモールス信号は、「月が綺麗ですね」ではない。國善は、最初の言葉を間違えて栄に告げてしまっていたのだ。
「な、なぜ、そ、それを……」
「わからないわ。ねえ國さん、本当は何?」
慌てている國善に、晴海は少し強い口調になって、じっと國善の目を覗き込んだ。國善は少し怯(ひる)むように体を強張(こわば)らせてから、いまの信号の本当の言葉を口にした。
「ほ、星が綺麗ですね、でした」
國善は言った。晴海はしばらくの間、何も言わずにただ、國善を見つめていた。國善はただ黙って、晴海の次の言葉を待つしかなかった。栄はそんな2人の顔を不安そうに交互に覗き込んでいた。
晴海はやがて、何も言わずに立ち上がった。そしてなんとか顔に笑みを作ると、國善と栄に「ごめんね」という表情を向けると、ふらふらと赤道儀室を出ていった。國善も栄も、ただ無言でその姿を見送ることしかできなかった。
4月14日、麻布天文台に小橋の声が響いた。
その声に、洋館の2階から平村誠一と一尾が同時に降りてきて、隣の日本家屋からは寺山も出てきた。写真儀室や子午儀室などにいたのか、平村聖士、高代も歩いてきていた。
赤道儀室の2階の入口に、興奮した様子の小橋が立っていた。その階段の下には、まず最初に駆けつけたのか、田倉も興奮した面持ちでいた。
小橋は皆を見渡し、最後に寺山を見据えて、叫ぶように言った。
「見えました、ハリーです!」
*本小説は実在の施設・人物などを参考にしていますが、すべてフィクションです。
*本連載は、雑誌「月刊天文ガイド」にて連載されたものの再掲です。
月刊天文ガイドHP http://www.seibundo-shinkosha.net/tenmon/
【単行本好評発売中!】
この本を購入する