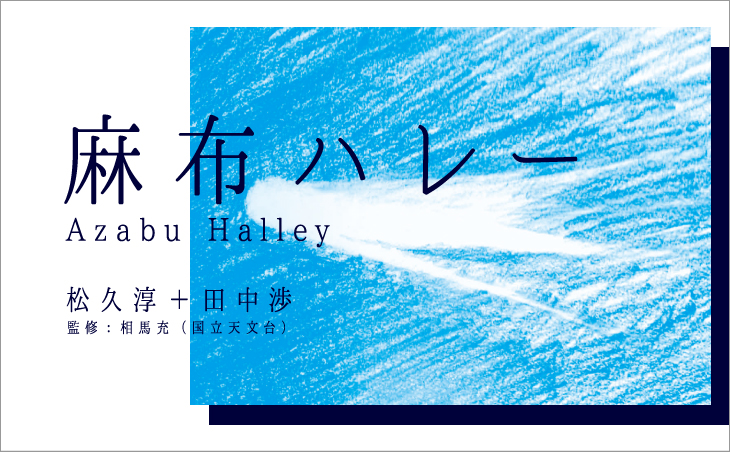第4回
1910年 麻布(3)
2017.02.08更新
【この連載は…】76年ごとに地球へ接近するハレー彗星とともに現れる、美しく不思議な女性。そして運命的な出会い。時代を超えた、はかない恋の物語。
「目次」はこちら
・・・・・・・・・・・・・・・・
栄のお供として、毎日のように麻布天文台に通うことになった國善。魅力的な女性・晴海に会えるという下心もありつつ、浮世離れした空気の流れる天文台に、栄とはまた違った理由で國善は魅かれていく。そんなある日、國善と栄は、台長の寺山に天文台で開かれる談話会へと誘われた。
・・・・・・・・・・・・・・・・
第4回
1910年 麻布(3)
寺山が言う「談話会」と称した集いは講義室で行われ、麻布の台員たち以外にも10人近くの人物が集っていた。皆すでに顔見知りのようで、寺山台長が國善と栄を紹介した。はきはきとした少年に全員が相好(そうごう)を崩し、國善は初対面の大人たちにひたすら緊張して、それぞれの自己紹介の言葉もほとんど頭に入ってこなかった。
そんなメンバーの中心人物は、早池峰(はやちね)天文台の台長、木戸英二だった。
木戸は平村聖士と東京帝大星学科の同期の36歳で、昨年まではこの麻布天文台に勤務していた。地球の自転軸が地球に対してわずかに移動する現象があり、それを極運動と呼ぶ。この数値を国際協力で解明するために、日本では國善の故郷、早池峰に緯度の観測所が作られることになった。そこは他の観測装置も設置され、初代台長に選ばれたのが若き木戸だった。
木戸は巨漢で、その体格だけでも圧倒的な存在感だったが、声も張っていて大きく、身振りも激しかった。あらゆる点で國善と対極のような人間だった。談話会はそんな木戸が自然と司会役になっていた。そして豪快そうに見えて、話題ごとに相応(ふさわ)しい人物に話を聞くなどの、繊細な気遣いもできていた。
今回の談話会の主題は、ハリー彗星のことだった。
「國善君は知ってるかい、ハリー」
木戸が聞いたが、國善はもちろん初耳だった。そもそも天文の知識がなく、ここに通うようになって多少は星々のことを覚えたが、それでも栄がすごい勢いで台員たちが教える話を吸収していくのには、到底敵(かな)わなかった。
「いえ、その、ぼ、僕はわから……」
「エドモンド・ハリーが発見したほうき星のことだよ」
國善が顔を赤らめていると、栄がすかさず胸を張って言った。台員たちはいつものその姿に微笑みを浮かべ、初めて出会った人々は、尋常小学校2年生の子供からその名が発せられたことに、皆目を丸くして驚いていた。
「このあいだ、一尾先生に習ったんだ。ね、一尾先生」
栄は足を投げ出すように椅子に腰かけている一尾に言った。ふだんから無口でいつも1人で研究に没頭している一尾は、栄に片目を閉じてみせた。台員たちからしても、ふだんあまり愛想の良くない一尾が、栄にはあれこれ教えている姿を微笑ましく思っていた。
「ハリーは76年に1度、地球に接近するんだ。國さん、次回はなんと再来月なんだよ。すごいでしょう」
栄は嬉しそうに國善に解説した。その様子を見て木戸は、「わっはっは」と講義室の天井にまで響くような声で笑った。
「寺山台長、栄君はいまのうちに星学科のエリートとして育てるべきですな」
「とっくにそうしちゃってるよ。なあ諸君」
寺山は表情を変えずに、飄々(ひょうひょう)とした調子で言った。田倉がおかしそうにその後を続けた。
「木戸先生、いまや栄君はうちの学生より宇宙(そら)を熟知しとうとです」
「そうか、栄君。今度ぜひ早池峰のほうにも遊びに来てくれよ」
「國さんの故郷なんでしょ。一緒に行こうよ、ね、國さん」
「う、うん」
國善は慌てて頷いた。もうどちらが子供なのかわからなかった。一尾が栄に声をかけた。
「栄君、ハリー博士はハリー彗星を見ずに発見したのさ。前に教えたかい」
「ううん」
栄は驚いて首を横に振った。一尾は人差し指を上に立てる仕草をして続けた。
「そこがハリー博士のすごいところさ。過去の天文の記録を研究していたとき、1531年、1607年、1682年に地球に接近した彗星があることがわかった。そのころは写真機もないんだよ。でもハリー博士はその軌道が似ていることに気づいたのさ。そしてこれは同じ周期で太陽の周りを回っている同じ彗星なのではないかと結論づけた。そして次は1758年に、またその彗星が飛来すると予言した。ハリー博士はその16年前に亡くなったが、予言通り、1758年のクリスマスの日に地球に近づいてきているのが発見されたのさ」
「すごい……」
栄は思わず呟(つぶや)いた。國善も声こそ出なかったが、ハリー博士の偉業と、その神秘的な彗星の話にすっかり魅了されていた。
「そしてその彗星は、ハリー博士に敬意を表して、ハリー彗星と名付けられたのさ」
続けて、田倉が優しく栄に語りかけた。
「栄君はまだ小さいけん、長生きすれば2度見られるかもしれんね。でもだいたいの人にとっては、ハリーは一生に1度のチャンスやろうね。この天文台も、もうすぐハリー一色になろうもん」
「僕も観測したいです」
「栄君はもう重要なここの一員やけん、しっかり頼むよ」
「はい」
栄は元気よく返事をした。國善は前から思っていたことだが、栄には純真で頭のいい子供ということ以外にも、大人を惹きつける魅力のようなものがある。はたして、いまここにいる台員たちはもちろん、いつのまにか仏頂面(ぶっちょうづら)の役人や強面(こわおもて)の新聞記者まで、可愛い息子や孫を見るような目になって栄に微笑んでいた。
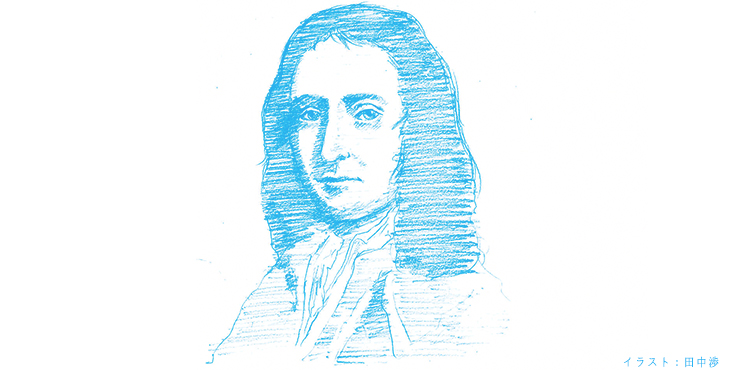
「またあちこちが騒然とするんでしょうかね。どうですか、寺山台長」
木戸が聞いた。國善にはその言葉の意味がわからなかった。寺山は「どうだろうね」という感じで肩をすくめただけだった。國善に続いて栄も不思議そうな顔をしたので、田倉が話を繋いだ。
「昔は、いやいまでもそう信じとう人も多かけど、彗星は凶星だと思われとってね」
「きょうせい?」
田倉の説明に小橋が続けた。
「不吉なことをもたらす星のことだね。とくにハリーはでっかく見えるから、古代ではそう思われてね。ローマの皇帝が死んじゃったのも、アフリカで戦いが起こったのも、オーストリアが滅亡しちゃったのも、インカ帝国が滅んじゃったのも、全部ハリー彗星がもたらした災いだって」
続いて、一尾が人差し指を立てて栄に言った。
「1066年にはノルマン人が英国への侵攻に勝利したんだ。そのときの様子が70メートルもある大きな絵画のような刺繍(ししゅう)に描かれている。そこには負けたほうのハロルド王の家来たちが、戦いの前に、上空を見て怯えている姿があって、そこに描かれているものこそ、ハリー彗星なんだ」
これまで黙って皆の話を聞いていた、平村誠一博士がゆっくりと口を開いた。
「栄君、英語で災害のことをdisasterというんだ。これはdisとastrumという2つの言葉からできている。これを日本語にすると、『死の星』といったところだね。つまり災害をもたらすのは彗星だというわけだ」
「となるとエンケやウォルフといった彗星を何度も観測している我々は、とっくに呪い殺されてなければなりませんな」
木戸はそう言うと、自分の言葉におかしくなったようで、わっはっはと笑った。
國善はふと、ある話を思い出していた。祖父母に聞いたのか、それとも近所の老人に聞いたのか。それは忘れてしまったが、幼いころに故郷で聞いた話であることは間違いなかった。その話の輪郭が頭の中で明確になっていくと、國善は自然と話し始めていた。
「私の村に伝わる話です。遠出を終えた青年が山を越えて自分の村に帰ろうとしていたとき、ふと開けた山道の向こうから、とぼとぼと1人の少女が歩いてきます。青年はどこかで見たような子だと、近づくと、その姿に驚きます。それは自分が小さい頃に、神隠しにあった同い年の少女でした。少女は当時の姿のままで、赤茶色の粗末な着物も、青年がかつて見慣れていたものでした」
これまでのざわめきが、ぴたりと止まった。講義室にいる全員が、國善の話に瞬時に引き込まれていった。そして、初対面ではない台員たちは皆、國善が訛(なま)りも吃(ども)りもなく、それどころかこれほどしっかりと、流暢(りゅうちょう)に話ができることを初めて知り、その驚きもあって声も出なかった。
「青年は尋ねます。おまえはいったい、どこで何をしていたのだと。しかし少女はそれには答えません。そのかわりに、今年は畑を耕してはいけません、実りはほとんど生まれません、来年まで耐えるのですと諭しました。青年がなぜかと問うと、少女はただ、星がやってくるから、とだけ答えました」
國善はその情景を思い浮かべるかのように、ゆっくりと目を閉じた。
「そのまま少女は消えてしまいました、村に帰ると、青年は全員にこの話をしました。少女の父親は青年に詳しい場所を聞くと、少女がいたほうへ数人の男たちと探しに行きました。しかし少女は見つかりませんでした。やがて、青年は狐(きつね)につままれて幻でも見たのだろうということになりました。しかしその年、これまでに見たこともない大きなほうき星が空を通っていきました。そして何が原因なのかはわかりませんでしたが、畑は枯れてしまったそうです」
國善が語り終えた後も、誰も何も言わなかった。國善は急に素に戻った。自分はなんと場違いなことをしてしまったのかと、真っ赤になって慌てた。
「あ、あの、と、突然すいません、なんか田舎の、は、話なんかしてしまって」
それでも皆、無言だった。やがて田倉がぽつりと口を開いた。
「國さん、すごかやないですか」
田倉の言葉を聞いても、國善には意味がわからなかった。自分が物語を語ると人はぐっと引き込まれていくことなど、まったく自覚などなかったからだった。しかし話の内容だけでなく、國善の話術のようなものは、確実にここにいる全員を早池峰の小さな村へと誘い、奇妙な話を間近で体験しているような気分にすらさせていた。
田倉の言葉に、台員たちとそれ以外の人々は、少し違うにュアンスだが全員頷いた。
「國善君、いまのがあの村に伝わる話なのかい?」
木戸が大きな声で聞き、國善は少し萎縮しながら「は、はい」と返事をした。
「なんせ私はまだ早池峰に1年でね。あそこにそんな不可思議な言い伝えがあるとは」
「そ、その、僕はそういう話を、幼いころからいくつも聞いて育ったもので」
そのとき、これまで一言も発していなかった男が、「佐澤さん」と國善に声をかけた。
この中でいちばんいい仕立ての着物を着ていた。歳は木戸や平村聖士と同じくらいの、30代半ばのようだった。いちばん最初の木戸の紹介をうろ覚えで、國善は名前や素性がわからず慌てた。立派な口ひげをたくわえていて、ふと見たところ政府の役人のように見えた。
「は、はい」
「日を改めて、そういったお話をまとめて聞かせてはもらえないでしょうか」
「法制局の参事殿も、かつての文学の血が騒ぎましたかな」
木戸が愉快そうに笑った。本当に政府の役人だったのかと、國善はびっくりした。
「國善君、こちらの宮田さんは官僚だがそもそも文学に造詣(ぞうけい)が深くてね。島崎藤村(しまざきとうそん)、田山花袋(たやまかたい)とも親交があるし、ご本人も若いときは詩人として作品を発表されたこともあるんだ」
宮田がいたって堅物(かたぶつ)で真面目そうな風貌だったので、その木戸の説明に國善はさらに驚いた。そして彼が宮田喜治(みやたよしはる)という名であったことをようやく思い出した。
「木戸先生、文学はとうに諦めていますよ」
宮田はふっと笑った。そして國善を再び見て続けた。
「法制局の前は、私は農商務省におりましてね。年中、日本各地の農村の実態を調査して回っておりました。東北はとりわけよく出向き、早池峰ももちろん数度訪れています。それぞれの地方を訪れると、よく地元の老人たちがその土地の言い伝えや民話を教えてくれたものです。しかし、そういった話はいまだ書物として編(あ)まれたことがない。役人の仕事の傍(かたわ)ら、いつかその作業に取り掛かりたいと思っていたのですが、なかなかきっかけがなく数年が過ぎてしまいました。でも佐澤君……國善君、君のその達者なお話をいくつか伺えれば、いよいよ始められるかもしれない。どうか協力いただけないでしょうか。いや、一緒にやりませんか」
國善は宮田の話を聞くだけで舞い上がってしまい、赤くなって要領を得ない相槌(あいづち)を打つことしかできなかった。栄が目を輝かせて國善を見ている。木戸や両平村博士、一尾、高代、小橋、田倉も嬉しそうな顔をしていた。寺山台長は髭(ひげ)に手をやって口笛を吹く仕草をしていた。
下宿のおかみさんが、いつも栄が天文台の皆さんにお世話になりっぱなしだから、ときどき何か持たせなきゃと悩んでいたので、國善はすかさず「三ツ矢シャンペンサイダーがいいと思います」と答えた。もちろん、本当の目的は晴海と一緒に飲むことだった。
「おいしい。すごく不思議な味がする」
晴海はサイダーの瓶を大事そうに指先で持っていた。栄は辛抱(しんぼう)できなかったらしく、栓を開けるなりほぼ一気に飲み干してしまっていた。晴海は自分の残りを差し出したが、栄は恥ずかしそうに「いいよ」と首を横に振った。
そして昨日の談話会での出来事を國善ではなくほとんど栄が説明すると、晴海は我が事のように喜び、ぱちぱちと手を叩いて國善に微笑んだ。宮田は今日、さっそく國善を訪ねてくる予定になっていた。
「すごいじゃない。ぜひやるべきだと思うわ」
「その、ぼ、僕はずっと聞いてきた村の話を基に、それを小説にしようと、そんな風に思って、やってきました。宮田さんは、僕の話をそのまま書き取っていきたいと、そ、そんな風におっしゃってる」
天文台の皆も、そして栄も晴海も喜んでいるが、それでも國善は本当にいいのだろうかという思いが拭えずにいた。談話会の後で宮田に聞くと、執筆は宮田がやると言い張った。國善はただ、幼い頃から聞いてきた話を、なるべく思い出し、語ってほしいと。自分は作家になりたい、自分の筆で作品を書きたいと強く思っているのに、それは不要だと言われたような気分だった。
晴海は國善を見つめて言った。
「國さん、國さんは自分の信じるように小説を書けばいいと思うわ。でも、國さんの力を違うことに使いたいという人がいたら、そのときは違うやり方でも、やってみることも必要だと思うの。私ね、人は誰もきっと、何かの役割を持ってるんじゃないかって、そんな気がするわ」
「役割?」
「そう。國さんは小説を書くのも役割かもしれない。でも、おじいさんやおばあさんの世代の人たちの話を、語り継ぐことも役割かもしれない。自分の筆で小説を書くことが役割かもしれない。でも違う人の筆のために、語ることが役割でもあるかもしれない。それは、実際にやってみないとわからないんじゃないかしら。もしかしたら本当の役割は何かってわかるのは、もう國さんがいなくなったずっと先の未来になってからかもしれない」
國善は晴海が言うことを、頭の中でひとつひとつ整理していった。晴海の言葉はいつもながらに明快で無駄がない。しかしどうしても、納得ができず、國善の中にはいつまでももやもやしたものが残った。
「お昼の月も神社の白石のようにきれいだね」
國善の心の変化に気づいたのか気づいていないのか、いつのまにか望遠鏡を覗き込んでいた栄が、妙に神妙な声で言った。
「栄君、なんだか素敵な詩みたいだわ。國さんの影響かしら」
「いや、さ、栄君はもともと、あ、頭が良いから」
晴海の笑顔に、國善は赤くなりながら首を横に振り、照れ隠しでサイダーをぐっと一口飲み、そして「ごほっ」とむせた。
國善はひとまず宮田の申し出の件を頭から追い払い、この数日、晴海にずっと口にする勇気がなかったことを、我慢できず、思い切って言ってみることにした。
「は、晴海さん。このあいだお話した、と、徳冨蘆花(とくとみろか)の、ほ、『不如帰(ほととぎす)』ですが」
「覚えてるわ。そのお話、映画にもなったんでしょう」
國善は頷いた。そしてその小説の話をしたのも、これから言い出すことのためでもあった。
「え、映画にもなりましたが、その、いま、ぶ、舞台がかかっていて、なかなかの、その、ひょ、評判だそうです」
「まあ、それは面白そう」
「ほ、本郷座での、上演です。学生時代の、ゆ、友人が切符を貰(もら)ったとかで、それを、その、ゆ、譲り受けることが、できるのです」
「本当? 國さん、羨(うらや)ましいわ。ご覧になったら、またそのお話も聞かせてくださいね」
國善は思わぬ返事に言葉を詰まらせ、ごくっと飲み込んだ。今日は必死の覚悟を決めて、その舞台に晴海を誘おうと、下宿の部屋で何回も何十回も、その会話を「予習」していた。ところが、この晴海の返事は想定していなかった。そして頭の中できちんとした返事を吟味する余裕もなくなってしまった。
「は、はい、見ましたら、か、必ず」
國善は思わずそう頷いてしまった。なぜ「いえ、晴海さん一緒に行きましょう」と、すぐに自分は言えなかったのか。そしてなんとか顔に出さぬように、しかし心の中ではこれまでにないくらい、果てしなく落ち込んでいった。
「國善君、いるかい」
そのとき、外から声が聞こえた。宮田だった。國善はいま宮田に呼ばれたことが良かったのか悪かったのか、自分でもよくわからなかった。晴海にぺこりと頭を下げ、栄に小さく手を振って、赤道(せき どう)儀(ぎ)室のドアを開けると、外への階段を下っていった。

*本小説は実在の施設・人物などを参考にしていますが、すべてフィクションです。
*本連載は、雑誌「月刊天文ガイド」にて連載されたものの再掲です。
月刊天文ガイドHP http://www.seibundo-shinkosha.net/tenmon/
【単行本好評発売中!】
この本を購入する