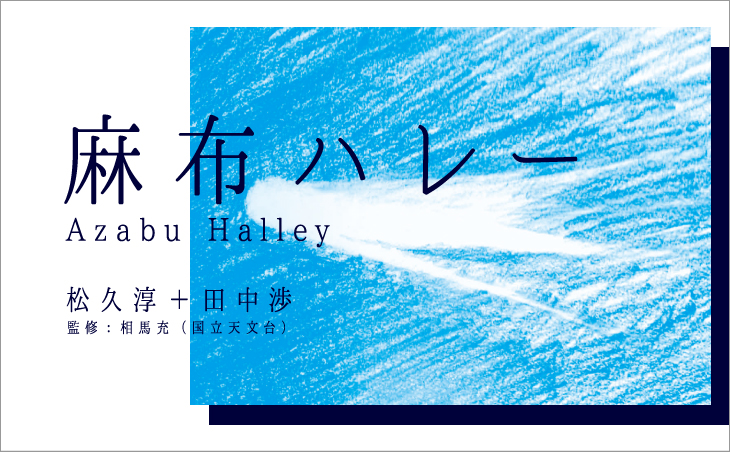第5回
1910年 麻布(4)
2017.02.15更新
【この連載は…】76年ごとに地球へ接近するハレー彗星とともに現れる、美しく不思議な女性。そして運命的な出会い。時代を超えた、はかない恋の物語。
「目次」はこちら
・・・・・・・・・・・・・・・・
ハレー彗星の話題でもちきりの談話会の中、國善が何気なく語った言い伝え。その話に興味を持った宮田に頼まれ、國善は言い伝えや民話をまとめる手伝いをすることになる。しかし、自分の物語を語る才能に気付いていない上、あくまでも作家を目指す國善は苦悩する。しかも晴海を舞台へ誘うのにも失敗し……。
・・・・・・・・・・・・・・・・
第5回
1910年 麻布(4)
宮田の顔を見ると、また先ほどの悩みがぶり返してしまう。晴海を誘うことにも失敗し、本意ではないことをこれからやることになるかもしれない。國善はそっと溜息をついた。
宮田とともに講義室へと向かうと、外壁の黒板に一尾が何やら熱心に白墨で書き込んでいた。また難しい数式なのだろうかと覗き込むと、國善はそこにあったものに驚いた。それは数式ではなく、玄人はだしな絵だった。そして國善はその図版などを見たことがなかったにも関わらず、それがハリー彗星だとすぐにわかった。
「これはこれは見事だね。一尾君」
宮田も感心したように呟いた。しかし一尾は宮田と國善のほうに、少しだけ顎を向けるとそれを挨拶としたらしく、何も言わずにまた絵に戻った。一尾は縦横それぞれ80センチほどを使い、黒板自体の黒色を宇宙(そら)に見立て、月やいくつかの星々、そしてその中央を流れる彗星を、白墨のかすれをうまく使ってその光や尾を表現していた。
「天才は何をやらせても、といったところなのかな」
一尾が反応しないことには宮田も慣れているのか、本人に言うでもなくそう呟くと、絵に見とれている國善に、「中へ」と仕草で促した。
講義室に入ると、2人の平村博士と高代が大きな模造紙に記された暦を広げて、何やら真剣に話し合っている最中だった。
「これは失礼」
宮田が頭を下げると、平村誠一博士が隣のほうを指差した。
「宮田さん、國善君、図書室がいま空いてるよ」
「ありがとうございます」
國善と宮田は、3人の脇を抜けて廊下に出て、言われたとおり隣の図書室へ入った。そこは講義室よりは狭く、小学校の教室ほどの広さだが、壁面も書棚も、天井までぎっしりと本で埋め尽くされていた。ほとんどが天文の資料で、海外の貴重なものもかなりあるという。それだけではなく、分厚く背表紙が金文字の大学や海軍の年鑑から、なぜか國善が好む文芸雑誌が積まれていたりもした。
4人掛けの洋風の丸テーブルが2つ、本に埋もれるように置かれていて、國善と宮田はそのひとつに座った。宮田は立派な革の鞄から、まず1冊の雑誌を取り出した。
「國善君、これ知ってるかい」
「こ、これは……」
その雑誌には「白樺(しらかば)」という題名と、その名のとおりに白樺の木の絵があしらわれていた。持ち込みに行った出版社で、噂は聞いてきた。東京帝大や学習院大を出た、文学を志す20代の金持ちの息子たちが文芸雑誌を作るらしい。これがそうかと、國善は目次に踊る聞いたことがない作家たちの名前を、どこか苛立(いらだ)ちを持って見つめた。
「明後日の4月1日に刊行されるらしい。知人が目を通してくれと、さっき持ってきてね。國善君がいちばん興味を持つかなと」
興味は大変にあった。しかし國善は目次を見ただけで、それ以上の頁をめくりたい欲求をぐっと抑えた。それは作家として一向に芽が出ない自分の、嫉妬や悔しさのようなものだという自覚はあった。ただそれに押し流されてしまわぬよう、必死に自分の頭の中に浮かびそうになる罵倒なのか負け惜しみなのか、そんな言葉を消した。
「5月のこれも1日には、今度はそこからも1冊出るらしい」
宮田は壁の向こうの、斜め下のほうへ指を向けて言った。國善は意味がわからず、そんな顔を宮田に向けた。
「森鴎外先生や上田敏先生の後押しで、永井荷風君が中心になって作るらしいよ。題名は『三田文学』だったかな」
宮田が指をさしていたのは、麻布天文台の崖の下の先、つまり慶應大学の方向だった。鴎外と上田は文学科の顧問、荷風は主任教授だ。
「いろいろなところから、文学の新しい潮流が生まれ始めているのかもしれないね」
自分はしょせん、どんな流れにも乗れていないんだ。そう思った瞬間、ふっと、國善は心も頭も静かになった。もう何もかも、自分の望むとおりにはならないんだと、そんな自暴自棄のような気持ちが限界を超えてしまったような感じだった。
その後、國善はただ淡々と、宮田に故郷の言い伝えを語っていった。
4月になって、栄の3年生としての新学期も始まったが、結局学校から帰ると、おかみさんが用意したおやつを口に放り込み、國善を促し麻布天文台へと走っていくのが日課となった。
ただ、國善は自覚も多少はあったが、明らかに様子が変だった。誰からも、いつも苛立(いらだ)ちのようなものを抱えているのが見てとれた。國善はそれを、いちばんぶつけたくない相手にぶつけてしまった。
「國さん、あんまり顔色が良くないわ。大丈夫?」
赤道儀室(せきどうぎしつ)で晴海が國善の顔を覗き込んだ。栄は平村博士たちとともに講義室で、江戸時代に描かれたという天文図に夢中になっていて、赤道儀室は2人きりだった。これまでの國善ならば、緊張こそするが晴海と狭い空間で2人きりでいられるのは喜びだったはずだが、この数日のもやもやは、そんな嬉しい状況の中でもなんら変わることはなかった。
「こ、このあいだ、は、晴海さんは、人には役割が、その、あるって」
國善はぽつぽつと、いつのまにか語り出していた。晴海は「ええ」と笑みを浮かべて頷(うなず)いた。
「で、でもそれは、す、少し違うんじゃないかなって、ず、ずっと思ってて。ぼ、僕はやっぱり、自分で小説を書く、作家に、な、なりたい。そ、それには、やっぱり宮田さんとのことを、つ、続けてたんじゃ、いけない、気がする」
「どうして?」
晴海は真顔で聞き返した。國善は、ごくりと唾(つば)を飲み込んでから続けた。
「や、役割を見つけるのって、む、難しいと思う。寺山台長や、み、みんなは、ほ、星が好きで、その才能もあって、こ、ここで働いている、んだと思う。み、宮田さんだって、ほ、本当は役人としての、ちゃんとした職務が、ある。ぼ、僕には、まだ、な、何もない。でも、作家になろうって、気持ちだけは、つ、強く持ってる、つもり、なんだ。なんだか、いま、やってることは、だ、妥協してるって、いうか、安売り、してるっていうか」
「國さん」
晴海は少し強い口調で、國善の言葉を遮った。
「私、國さんにはお話の才能があると思う。そしていま、その力を望んでる人がいる。でもそれをしたくないっていうのなら、そこで才能を使い果たしてしまうって思ってるなら、そんな國さんが書いた小説は、きっと人には伝わらないと思うわ」
國善は晴海が何を言っているのか、しばらくわからなかった。これを売り込みに行った出版社の編集者に言われたのなら、かっとなりつつも、納得はしなくても、言葉自体はすぐ理解できる。しかし、まさかいつも優しく微笑んでくれる、自分がすっかり惚(ほ)れてしまっている女性の口から発せられると、耳なのか脳なのか、その言葉を受け入れることを瞬時に拒否してしまったような感じだった。
國善はがたっと椅子を尻で押し出すようにして立ち上がった。危うく屈折望遠鏡に頭をぶつけそうになってしまったが、ずいぶんここにいるおかげで、ぎりぎりのところで避けることができた。
晴海に何かを言い返したかった。晴海くらいしっかりと、明解な言葉で言い負かしてやりたかった。しかし言葉は何も頭に浮かばない。國善は思わず、「くそっ」と吐き出すように呟いてしまった。そして自分の発してしまった汚い言葉に驚いた。晴海は、表情を変えずに國善を見つめていた。
國善は、息を大きく吸い込んで、赤道儀室を飛び出した。

國善は麻布天文台から飯倉交差点までただひたすら走った。もともと体力はそれほどなく、その100メートルばかりで、膝を押さえてぜえぜえと屈みこんでしまう羽目になった。
「國善君、かけっこかね」
やけにのんびりとした声が隣から聞こえてきて、國善は「え?」と、なんとか顔を上げた。するとそこには、寺山が立っていた。その涼しい表情と小粋な格好にはまったく似つかわしくない、4輪の大きな荷車を引いていた。
「だ、台長、そ、それは」
「いまからちょっと品川沖までね。ちょうど飛んで火に入ってくれたりしたね。國善君、これ頼める?」
寺山はそう言うと、國善の返事を待たずに荷車の取っ手の棒をまたぐと手を離した。國善は慌ててそれを押さえ、寺山の代わりに荷車を手にした。まだ荷物は何も積んでいなかった。國善は言われるがまま、すたすたと歩く寺山の後ろを、やや小走りになりつつ追いかけていった。
「台長、う、海には、その、何をなされに」
「國善君、宮田君との作業は進んでいるのかな」
慣れたつもりでも、寺山のこの調子にはいつも面食らう。國善は自分の質問の返事はおそらくないなと諦めて、「はあ」と溜息混じりに頷いた。たったいま、このことで晴海に悪態をついてしまったところだ。
「それが、その……」
國善はどこまで話そうかと悩んだが、その必要はなかった。またしても寺山は國善の返事など聞いていないかのように、自分から話をし始めた。
「宇宙(そら)を相手にした仕事なんかしてたりすると、ときどき、誇らしさと虚(むな)しさを同時に感じることがあったりするよ。新しく知り得たことがある。すると同時に、まだ知り得ないことまでわかってしまう。その繰り返し。何百年前からの、世界中の先人の観測と思考のおかげでいまがある。そしていま麻布にはこれだけの才能が集っている。しかし解けない謎がある。いつの日か、私たちがその先人の立場となって、後世の人々はより深く、宇宙(そら)を知ることになったりする」
國善は寺山の言葉の意味を考えた。自分がただたんに、未来で解き明かされた何かの真理の過程の駒(こま)にすぎなかった場合もあるわけだ。すると寺山はそんな國善の思いを察したわけではないだろうが、のんびりと続けた。
「でも、ひとつの真理に向かって、こうして仲間たちと研究ができる。それはかけがえのない幸せだったりするんだなって、この年になってようやくわかってきたりしてるよ。その点、國善君は若いうちにいろいろあって、良かったね」
國善は驚いて、思わず寺山の背中に向かって「え」と声をかけた。
「だってそうだったりするじゃない。君はとても上手に古い話を語る。しかもいろんな話を知ってるそうじゃないか。つまり君は、地元の老人たちが、思わず心を開きたくなる才能もあったということだ」
頭をよぎったこともない考え方だった。訛(なま)りと吃(ども)りがきつい自分が、話が上手だと言われたことも驚きだった。しかし、寺山はその前段階の、子供のころから國善が言い伝えや民話を様々な大人たちに語ってもらっていたこと自体を、才能と呼んだ。
「いやいや、羨ましいかぎり。さて、先を急ごう」
寺山はそう言うと、左にこんもり芝公園の丘陵が見える道を、歩調を早めて進んでいった。國善は慌てて、荷車を押す腕に力を込めた。
品川沖で、寺山は海軍基地から何やら謎の機械を、國善にはわからないがそれなりな地位の将校から受け取った。全部で5つの機械と、小さなそれに付随している装置、そして電気用の線を数本を荷車に詰め込むと、それはかなりの重量感があり、國善がゆるやかな上り坂でもある帰り道で、へとへとになってしまった。
押すだけでも大変なうえに、寺山は荷車の後ろに回り込んで、観察したり触れたりしていたので、先頭で引く國善は、それが何なのかを聞くことすらできないままだった。
麻布天文台に戻って、荷車を赤道儀室の前で止めたころには、國善は汗だくでただうずくまることしかできなかった。物音を聞きつけて、講義室にいた栄と、小橋と田倉の若手2人がやってきた。荷車を覗き込む栄の目は、いつになく輝いているのが國善にもわかった。
「お、國善君、重労働じゃん」
小橋が笑いかけた。國善は「は、はい」と頷きながらなんとか立ち上がり、荷車の中を覗き込んだ。
「あ、新しい、か、観測装置ですか」
運んできたのに何かを知らない國善が聞くと、小橋はふっと笑った。
「國善君、これ無線装置」
「む、無線装置?」
「無線って何?」
國善に続いて栄が小橋と田倉を見た。
「これがあると、遠くの人と、通信ができるすごか機械ったい」
田倉にそうは言われても、國善は何がどう動き、どう通信できるものなのか、まったく想像がつかなかった。電話機ならば、使ったことはないが新聞などで見たことはある。しかし荷車の中の機械は、それとはまったく違う形をしていた。電報のようなものなのだろうかと、國善は思った。
「三六式無線機。海軍の艦艇(かんてい)で使われとったとよ」
田倉が説明しようとすると、それを遮るように寺山がのんびりと言った。
「いつか、日本中の天文台が無線で繋がれば、楽しいことになっちゃったりするんじゃないかな。じゃあ諸君、よろしくね」
寺山は髭(ひげ)をすっと指で撫でると、皆の返事も聞かずに踵(かかと)を返し、自室のある日本家屋のほうへとすたすたと歩いていった。
「台長の新しもの好きにも困ったもんだねー」
寺山の姿が消えると小橋は溜息をつきながら、しかしどこか楽しそうに呟いた。
「ほら、ここはもともと海軍の観象台だったし、台長はそっちのお偉方(えらがた)とのつきあいも多いからね。きっと型落ちしたこれのこと聞いたら、すぐ欲しがっちゃったんだろうね」
田倉が続けた。確かにこの天文台には他では決して見ない観測機器や高性能の時計だけでなく、講義室にはどっしりとした扇風機が置かれているし、ハイカラな寺山の洋装にはいつも驚かされる。
荷車からやけに重い機械を、大人3人と栄で、狭い赤道儀室の階段を運んだ。國善が入ると、晴海はいなかった。屈折望遠鏡の右斜め向こうの壁側にある机に、無線機の機械を並べていった。小橋と田倉は、説明図をもとにそれぞれの機械を繋いでいった。
右側の手前には白い大学ノート大で3センチほどの厚みの石板の上に、取っ手のような金属を頑強に固定した。その奥には映画の映写機のように大小の円に線がつたった機械。中央には大きなコイルのような装置。左側にはひときわ大きな、旅行鞄ほどありそうな黒い機械が置かれた。
田倉はそこから伸びた線を持って、國善と栄に肩をすくめた。
「さっき台長は、日本中の天文台で通信ができるって言いよったけど、そもそも不可能たい」
「どうしてなの?」
「だって栄君、ここから先に繋げる、肝心のアンテナがなかよ」
田倉はそう言うと、小橋が「はははは」と愉快そうに笑った。
「言ったろ。寺山台長は無類の新しもの好き。しかも機械には目がないんだ。まあアンテナももらってきたところで、そもそもどこの誰と無線でやりあうんだって話だよ」
「じゃ、じゃあ」
國善は苦労して品川沖から運んできた無線装置に目を落として言った。
「そう。いまのところこれは、ただの飾り。簡単に言うと、台長のおもちゃ、といったところかな」
小橋はそう言うと、手にした線をくるくると巻いてまとめ、黒い機械の上にぽんと置いた。
「でも僕、これすごくやってみたい。どうするの?」
「そうか、新しもの好き、機械好きは、ここにもいたか」
先ほどから無線機に触れたくてしょうがなそうだった栄の姿に、小橋はまた大きな口をあけて笑った。
「栄君、無線はモールス信号っていうとよ。ほらここを打ってみて」
田倉は栄を手招きして、右側の石板の上の金属の取っ手に指を乗せさせた。そして栄の人差し指を優しく、上からとんと打ち、続いて長く押した。
「この、トンって押すのと、ツーって押すのの組み合わせで、言葉を伝えると。残念ながら、僕にはわからんけどね」
「僕も知らないよ」
「ぼ、僕も、も、もちろん、わ、わからない」
栄の目が小橋から順番に向いていったので、國善も慌てて首を横に振った。
「でもモールス符号の本は図書室にあるけん、もし興味あったら勉強したらよかよ」
「はい。覚えて、僕が麻布天文台で最初の通信士になります」
栄ははきはきと答えた。小橋と田倉は一気に頬を緩め、そんな栄を可愛い弟を見るような目になった。國善は栄の好奇心がさらに生まれたことに、同じように微笑ましく思いながらも、その熱量が素直に羨ましかった。
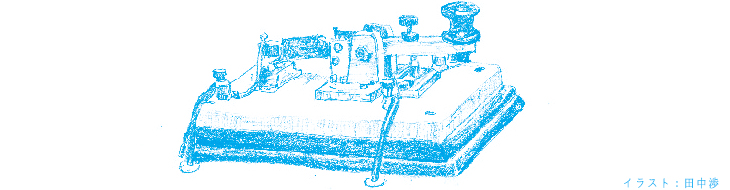
*本小説は実在の施設・人物などを参考にしていますが、すべてフィクションです。
*本連載は、雑誌「月刊天文ガイド」にて連載されたものの再掲です。
月刊天文ガイドHP http://www.seibundo-shinkosha.net/tenmon/
【単行本好評発売中!】
この本を購入する