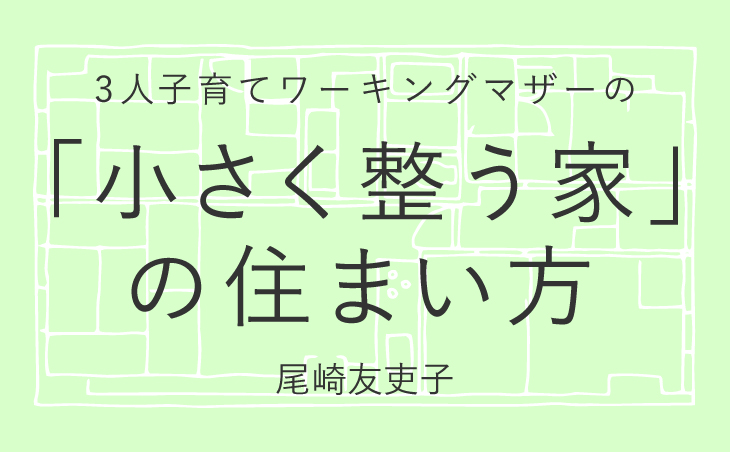第12回
ストリートの再教育課程(後編)
2019.03.18更新
文化人類学者であり、国士館大学教授の鈴木裕之先生による新連載が始まります。20年間にわたりアフリカ人の妻と日本で暮らす鈴木先生の日常は、私たちにとって異文化そのものです。しかしこの連載は、いわゆる「国際結婚エッセイ」ではありません。生活を通してナマの異文化を体現してきた血の通った言葉で、現代の「多様性」について読み解いていきます。
「目次」はこちら
拳の一撃
アビジャンのゲットーの酒場で、私はストリート・ボーイの一団に脅されている。
相手は筋骨たくましい強面が6、7人。
こちらは、私と子分のストリート・ボーイが3人。
多勢に無勢である。
ストリート文化の調査の過程で、私の子分のひとりから「肉体派」のグループを紹介され、彼らにインタビューし、写真撮影を終えたところである。
「友だち」の紹介だからと非常に愛想よく迎えられ、友好的な雰囲気のなかでのインタビューと写真撮影が終わったとたん、彼らの態度が豹変し、「取材料」を求めてきたのだ。
紹介してくれた子分が「話が違うじゃないか」と取り乱すのを黙らせながら、リーダー格の男が口を開いた。
「このあいだ、スウェーデンから取材にきたジャーナリストは20万フラン払ったけど、お前は友だちの紹介だから、12万フランでいいよ」
これは日本の感覚で、12万円払えというのに近い。
完全にはめられた。取材という既成事実をつくったあとに、金を要求してくるとは。
ヘビのように冷たい眼差しが私に集中する。私は慄然としながら、ことばを失う。
すると、私の子分のひとりが「スズキ、こいつらにはタバコ代だけあげて、さっさと帰ろうぜ」とスラングで叫んだ。
その瞬間、彼の左隣に座っていた顔面におおきな傷跡をつけた強面が、図太い右腕をブーンと振りまわし、その巨大な拳で彼の鼻先に一撃を加えた。
彼は鼻血を吹きだしながらもんどりうって椅子ごと後ろに倒れ、すぐに詫びをいれた。
これは冗談でも遊びでもない。本気のストリート・ライフなのだ。
その後、私は先方のリーダーと粘り強く交渉し、最終的にはそのとき財布に入っていた持ち金全部を渡すことで話がまとまった。結果として12万フランを7000フランにまでまけてもらい、なんとかこの場を切りぬけたのである。
爆発するエネルギー
あの時は殺されるかと思ったが、今となっては良い思い出となったこのエピソード。
私の子分のひとりとこのグループ「ゲシュタポ」(この名前を聞いた時点で、調査をやめておくべきだった)はおなじゲットーに住む知りあいである。「ゲットー」は、いわゆる下町から本格的なスラム街まで、貧困層が住む街の総称として若者たちが好んで使う言いまわしだ。
当時、私はさまざまなタイプのストリート・ボーイたちとの接触を試みていた。そこで彼は知りあいの肉体派グループと話をつけ、インタビューの段取りをつけてくれたのだ。
アビジャンには種類の異なるストリート・ボーイたちがいる。
肉体派は「ルバ」と呼ばれ、カラテ映画の影響を受け、身体を鍛え、用心棒、警備員などに従事しながら、暴力でストリートを支配しようとする。フランス語で「ならず者」を意味するloubardが語源である。筋肉に投資した手間・暇・金をあらゆる手段を使って回収しようとするので、取材にたいして金を要求することは、彼らにとっては「常識」なのだ。
いっぽう、「普通」のストリート・ボーイは従事する経済活動によってお互いを分類する。
靴磨き、新聞売り、バスの客引き……私の子分たちは、自動車見張り番である。これは、路肩に駐車する自動車を泥棒やイタズラから守り、その手間賃を運転手からもらうというもの。日本大使館の前の道路を縄張りにしているグループと仲良くなり、彼らが私の師匠兼子分となったのだ。
他に、スリ、強盗、麻薬密売などの犯罪を生業とするストリート・ボーイもいて、こちらもその活動内容によって分類される。
ストリートにおけるルバの重要性にはやくから気づいていた私は、自分の調査が一歩前進するのを期待しながらインタビューに臨み、玉砕してしまった。
アビジャンのストリートにはエネルギーが充満している。それが一触即発の状態で渦巻いている。私たちのように、中学校から高校にかけて、受験勉強でエネルギーの大半が吸いとられ、大学で抜け殻となってしまったような輩とはわけがちがう。100パーセント保存されたエネルギーが、爆発の機会をうかがっている。
学校をドロップアウトし、家庭から追いだされ、身の置き場のない若者たち。
未来になんの保証もなく、自分自身の力で今日を生きぬかねばならない。
ストリートに自分の居場所をつくりだし、自己の存在を主張しなければならない。
彼らの発するエネルギーは熱く激しい。
その前では、学術的意義やボランティア精神のような、金持ち「白人」が彼らに近づくために多用する方便など、すぐに溶解してしまう。
あの時、幸いにも(?)私自身ではなく、子分のひとりの鼻面をへし折ったあの拳は、同時に私の狭量な受験マインドの鎧にヒビを入れる一撃でもあった。
目の前にいるのは、教科書のコラム欄に閉じこめられた「ホニャララ」族ではない。生きた人間の一群だ。小細工は通用しない。ただ、彼らの文化を理解し、それを実践することだけが、その強力なエネルギーに対抗する唯一の手段なのだ。
ストリートのDIY
私がアビジャンのストリートで発見したのは、この一見すると無秩序と思われる世界が、じつはある種の様式に規定された秩序ある世界であるということだった。
学校と家庭という、社会の設計図の主要な柱から「はぶかれ」たストリート・ボーイたちのエネルギーは、迷子になるようでいて迷子にならず、無軌道に爆発するようでいて、じつは一定の様式にしたがって爆発する。
ストリートに長居し、その風景に目が慣れるにつれ、彼らのエネルギーが流れる通路が見えるようになってきた。この通路こそ、ストリート文化にほかならない。
どんなことばをしゃべるのか、
どんな風に喧嘩がはじまるのか、
誰が仲間で誰が敵か、
誰が強者で誰が弱者か、
金はどう稼ぐのか、どう盗むのか、
……
たとえば、自動車見張り番である私の子分たちを見ていると、どうやって縄張りを決めるのか、縄張り内では誰がその自動車の担当となるのか、どうやって見張り代を運転手からせしめるのか、掟破りにはどう対処するのかなど、じつに秩序だった方法で経済活動を営んでいることがわかる。
あの悪名高きルバたちは、より高度な文化を発達させている。
彼らの動きのインスピレーションは、すべて「カラテ」からきている。彼らがKarateと言うとき、そこには日本の空手、韓国のテコンドー、中国のカンフーが含まれ、おもにカラテ映画と道場での実践からその動作を学んでゆく(ちなみにコートジボワールにはテコンドーの道場があり、競技大会では強豪国として知られている)。
彼らはつねに清潔を心がけ、オシャレに気をつかい、ジーンズ、Tシャツ、スニーカー、野球帽、金のネックレスなどで身を飾るが、このファッションはアメリカ黒人をまねたものである。また、アメリカのストリート・ギャングをまねて、地区ごとにルバ・グループを結成し、たがいに対抗する。グループ名も、「シカゴ」「ブラック・パワー」「ブラック・タイガー」などなど。
彼らは暴力で相手を脅し、カツアゲもおこなうが(暗殺を請け負うという噂もある)、そのファッション感覚、魅力的なボディーランゲージ、印象的なスラングの言いまわしなど、ストリート文化のクリエイターとして光り輝いている。
前回のエッセイで紹介したジョン・ポロロはルバの親分で、彼がカラテの「型」をもとに編みだしたストリート・ダンス<ニャマニャマ>はコートジボワール全土で若者たちを熱狂させ、一種の社会現象となった。さらに、ルバのダンスとアメリカのラップを結びつけてブレイクしたグループも登場した。
アジアの空手文化、アメリカの黒人文化と並び、ジャマイカのラスタ文化もアビジャンのストリートにおおきな影響を与えている。ドレッドロックスにラフなジーンズ、Tシャツのいでたちでレゲエを愛好する若者は「ラスタ」と呼ばれ、そのなかから数多くのレゲエ・シンガーが生まれている。
こうしたさまざまな若者たちの営みが、たがいに絡みあい、融合し、反発しあいながら、アビジャンのストリートというミクロ・コスモスを形成している。
それは社会学的に記述すればサブカルチャーの生成であり、ダンスや音楽というポップカルチャーの発生ということになるが、私の眼に焼きついたのは、その奥にある、人類が文化をつくりだすパワーと能力であった。
社会から除け者にされた者たちは、みずからの力で生の枠組みを形づくってゆく。
まさに、文化のDIY、Do-It-Yourselfである。
ブリコラージュの現場
文化のDIYを文化人類学では「ブリコラージュ」と呼んでいる。
ブリコラージュbricolageとは、フランス語でありあわせの道具と材料を使ってモノづくりをする、いわゆる日曜大工を意味するが、著名な文化人類学者レヴィ=ストロースにより、人間の認識の仕方、文化のつくり方にまで拡大されて使用されるようになった。
アフリカで誕生したホモ・サピエンスは、世界に拡大する過程で異なる環境に適応しながら多様化していった。ゆく先々で、自分たちを取り囲む自然環境を人類に特有の感性で読み解きながら体系化し、それぞれの共同体が独自の世界観を形成していった。
あらかじめ設計図があり、それにしたがって形をつくるのではなく、たまたまそこにあった環境という「ありあわせ」の道具と材料を使いながら、非常に自然な形で文化が生みだされてゆく。アフリカの熱帯雨林の文化と、アラビアの砂漠の文化と、四季豊かな日本の文化はおおいに異なるが、その地の自然と密着した「必然性」という観点で眺めると、共通性が見えてくる。
この、目の前にある具体的な環境を読み解き、それを取りいれながら世界観を形成し、社会を形づくってゆくという思考は人類が共通に持つ「野生の思考」であり、レヴィ=ストロースがブリコラージュの比喩で説明した「具体の科学」とでも呼べる方法論なのである。
ところが、産業革命以降に西欧で発達した「近代の科学」はコンセプト優先であり、まずなんらかの基準にしたがった設計図がつくられ、そこにさまざま部品が組みこまれ、全体を形成してゆく。重要なのは目の前にある具体的なモノや状況ではなく、与えられた設計図である。必要であれば(おおくの場合、必ずそうなるのであるが)、設計図にあわせて環境を強引に改造し、有用な部品と化してゆく。
基準があり、有用があり、無用がある。
無用なものは、改変するか、切り捨てるか、無視する。
始末の悪いことに、この基準が「普遍的」「絶対的」であるとされている。
しかもそれは、「普遍的価値観」として学校教育に組みこまれている。
さらには、ヨーロッパによる植民地化の過程でこの教育制度が世界中に普及し、現在の学校教育の、ひいては世界の価値観のスタンダードとなっている。
日本で西洋式の教育を受け、受験戦争を生きぬき、大学院にまで進んだ「知的エリート」である私がアビジャンのストリートで発見したのは、まさにブリコラージュの現場であった。
それは学術的に分析・記述するのにもじゅうぶん魅力的で、じっさいに私はそうしたのであるが、ルバの拳が、自動車見張り番の叫び声が、ラスタの歌声が、私のもっと奥深いレベルにおける価値観の変革を促してくれたのである。
除け者たちの自由
社会の設計図の内部に居場所失い、文化的・社会的・経済的資源へのアクセスを失ってしまった人間は、いったいどうなってしまうのだろう。そのまま人生が終わってしまうのだろうか。その答えのひとつを、アビジャンのストリート・ボーイたちが見せてくれた。
彼らは「具体の科学」にしたがって、ありあわせの道具と材料を使いながら文化の創造をはじめた。
アビジャンという都市空間において、学校と家庭という資源が活用できないのであれば、あとは万人に開かれたマスメディアを利用するしかない。
彼らは、自分たちの感性で「カッコいい」という基準に照らしてアジアのカラテ文化、アメリカの黒人文化、ジャマイカのラスタ文化を選び、それらを素材としながら言語と身体によるコミュニケーション様式をつくっていった。
犯罪を含めたさまざまな経済活動を編みだし、主流社会の内部を循環する貨幣をゲットする手段を開発していった。
すべてが手作りであり、DIYであり、ブリコラージュであるが、すべてのストリート・ボーイがその世界観を共有し、流動的ではあるが確かに存在するその掟にしたがって生きていた。
設計図の外側に世界はないと思っていたら、じつはその「空白地帯」にたくさんの人々がいて、たしかに生きていた。
つまり、ほんとうの世界は、私がそれまで学校で教わってきた世界よりも広く、かつ自由なものであった。
であるならば、世界の多様性にたいして、恐れを抱く必要はないのではないか。
設計図があれば、守らなければならない構造がある。
構造があれば、それを乱すであろう異質性が怖くなる。
でも、もし人類が本来的にDIY能力を持っているのであれば、いつでも変化を修正することができるはずだ。
たしかに住み慣れた世界が変わるのは苦痛である。だが、もともと私たちの祖先がブリコラージュしながらこの世界を創ってきたのではないだろうか。
私たちの祖先にできて、アビジャンのストリート・ボーイにできて、私たちにできないということはないだろう。
みな、おなじ人間なのだから。