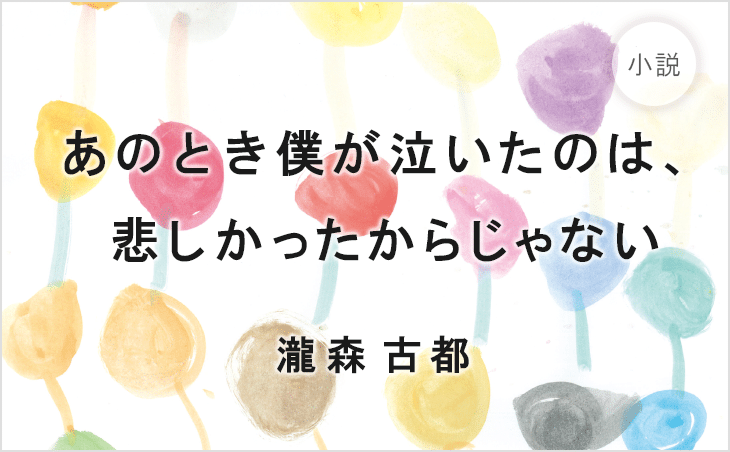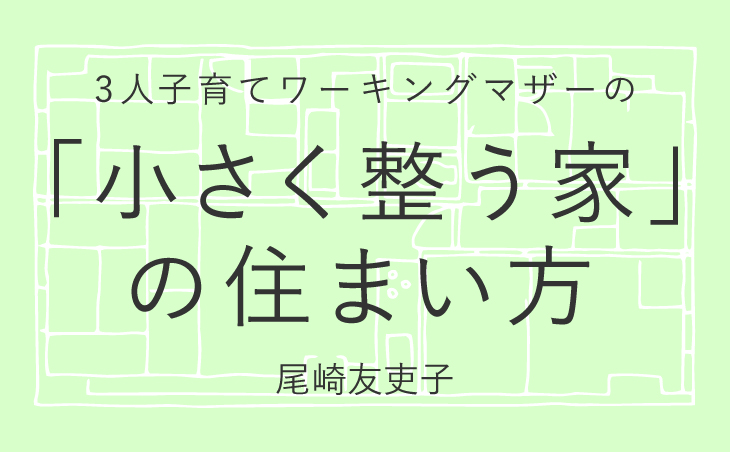第0回
【一気読み】ショコラの種
2018.07.17更新
【この連載は…】2018年8月上旬発売の瀧森古都最新小説集から、第1話を全文無料公開。涙が枯れるほど泣いたあと、大切な人に会いたくなる「心潤す感動短編集」。
「あれ? 今日はミートボールじゃないの?」
保育園へ向かう朝、私が作ったお弁当をチェックすることが息子の日課である。
「ごめんね、ナオくん。ミートボール買い忘れてたの。でも玉子ハンバーグも好きでしょう?」
「うん! ぼく、こっちのほうが好き!」
今月、保育園を卒園する息子は、そう言うと屈託のない笑顔を見せてくれた。
女手一つで育てている私にとって、この子の笑顔は最高のサプリメントといえる。
息子が好きな玉子ハンバーグとは、お弁当の材料を買い忘れた時の「ピンチのおかず」である。少ない挽き肉と玉ねぎを、卵一個と混ぜ合わせ、フライパンで焼く。
五分もあれば、小学生でも作れるだろう。
一見、オムレツといったほうが近いかもしれないが、一度ふざけて「玉子ハンバーグよ」と言ったら、たいそう喜んだため、そう呼ぶことにした。
「ねぇママ、おこらない?」
「ん? どうしたの?」
「おせんたくのせんざい、こぼしちゃった」
「まぁ、ナオくんお洗濯がしたかったの?」
「う……うん」
「そう、じゃあ帰ってきたらママと一緒にお片づけしましょうね。さ、お靴はいて保育園行きましょう」
「うん!」
息子を保育園へ送り届けた後、私は駅前のスーパーへと直行する。
夫と別居することとなった半年前、専業主婦だった私はすぐに仕事を探したものの、なかなか決まらず、知人の紹介で駅前のスーパーに勤めさせてもらった。
今はまだパートだが、半年間勤めたら社員にしてくれるという形態に惹かれたのと、あまったお惣菜や青果などを格安で譲ってもらえるため、接客やレジなどの経験はなかったが、勤めてみようと決意した。
しかし、半年が経ったものの、まだ社員になれていない。
息子が小学校に上がるまでには、安定した生活を送れればいいのだが……。
そこはかとなく不安を感じつつ、制服に着替え、タイムカードを押そうとした時、血相を変えた店長が、私のほうへと駆け寄ってきた。
「鮫島さん! すぐに病院へ行って! ナオ君が……ナオ君が……」
「店長、直輝が何か?」
「今、保育園から電話があって、ナオ君がのぼり棒から落ちたって……」
店長の口元が、ただ動いているようにしか見えないというか、何を言っているのか理解するまでに、私は数秒かかった。
すぐにタクシーを呼んでもらい、制服のまま、直輝が運ばれた総合病院へと向かった。
病院へ着くと、園長先生と担任の先生が、手術室の前で祈りながら立っていた。
私と目が合った担任の先生は、「ごめんなさい、ごめんなさい」と言って、真っ赤に腫らした目からポタポタ涙を流している。
「先生、直輝の容体は!?」
「意識がなくて……のぼり棒から落ちた直後は、かすかに話していたのですが……」
「のぼり棒……!? あの子がのぼり棒なんて、公園でもしたことないのにどうして……」
「ええ、園でもいつもやらないんですが、お友達の話によると、一番てっぺんまで登ったらママのスーパーが見えるかもしれない、と話していたらしく……」
──私のせいだ。
寂しい思いをさせていた、私のせいだ。
直輝にもしものことがあったら……私はどうしたらいいんだろう。
すると、手術室の扉が開き、医師がマスクを取りながら出てきた。
私たちと目を合わせることはなく、下を向いたまま首を横に振っている。
約三メートルからの転落により、全身を強打。
多臓器不全により、午前十時五十分 死亡。
医師が何を言っているのかなど、耳に入らなかった。入れたくなかった。
ベッドで横たわっている、青ざめた皮膚の幼児が、自分の息子だなんて信じられなかった。
*
それからのことは、よく覚えていない。
たくさんのお友達と、お友達のお母さんに見送られ、直輝の葬儀は静かに終えた。
そして、葬儀から数日経ったと思われる日、別居中の夫が弁護士を連れて家に来た。夫と会うのは、葬儀以来である。
夫は、保育園側が充分な見守りを怠っていたとして、約四千万円の損害賠償を求める訴訟を起こすと言う。
私には、正直どうでもいい話だった。
「おい、聞いてるのかよ」
「え?」
「だから、お前が病院に駆けつけた時、保育園の先生はなんて言ってたんだよ」
「ああ……」
「ああじゃなくて、ちゃんと思い出せってば」
「『ごめんなさい』って、言ってたと思う」
すると、古びた畳とは不釣り合いの、高級スーツを身にまとった男性弁護士が、正座をピクリとも崩さず口を開いた。
「やはり、お母様に会って早々に謝罪の言葉が出るというのは、保育園側が充分な見守りを怠おこたっていたという可能性が非常に高いと言っていいかもしれません」
「じゃあ、先生。オレら四千万円貰もらえるんですか? いや、五千万だっていいくらいさ」
「さぁ、それは裁判をしてみないことにはなんとも。ただ、勝てる可能性は低くないと思います」
夫は、どうやら慰謝料目当てに、保育園を訴えようとしているらしい。
この半年、ろくに顔も合わせていない息子の死を、お金に変えようだなんて……。
しかし、一般企業の社員である夫が、お金に困っているとは思えない。
また貢ぐ相手でもできたのだろうか。
夫と別居した原因は、よくある女性問題だった。入れ込んだあげく、女のアパートで暮らし始めたものの、結局飽きられて今は都内のウィークリーマンションを転々としている。
直輝のことを思えば、ここに戻ってきてもらい、一緒に暮らすことが正解なのかもしれない。いつかそうしなきゃ、そうしなきゃと、自分に言い聞かせているうち、半年も経ってしまった。
そして、直輝はもういない。
夫を受け入れようとする努力も、もうする必要がなくなったのだ。
気がつけば、また辺りが暗くなっていた。
何をする気にもなれない。
何かをしようとも思わない。
そんな日々が、もう何日続いているのだろう。
毎晩のように直輝が夢に出てくる。夢の中の直輝は、私の方を見ながらポロポロ泣いているのだ。小さな川の向こう岸からこちらをじっと見つめ、ポロポロ、ポロポロ、涙を流している。
きっと、私のことを恨んでいるんだ──。私が寂しい思いをさせたせいで直輝は向こう岸へ行くこととなり、寂しくて、悲しくて、直輝は涙を流しているんだ──。
ぎゅっと抱きしめることのできない夢の中の直輝との再会は、朝目が覚めるたび、残酷な余韻しか残らない。
もうすぐママもいくからね。
私は、青ざめたあの子と対面した時から、そう決めていた。
希望のない人生を歩み続けても、何の意味もない。
だから、私は葬儀の時も、あの子が灰になった時も、涙を一粒もこぼさなかった。
すぐに会えると思っていたから。あの子をちゃんと見送ってあげた後、再び会いに行くつもりだったから──。
そして、見慣れていた「点滅しっぱなしの留守電ボタン」に目をやった。
電話が鳴っているのはわかっているものの、受話器を取る気になれず、ずっと放置していた。
夫と弁護士が帰った後、直輝のところへ行く決意を改めて固め、ずっと放置していた留守電をふと聞いてみようと思った。
最期に周囲の声を聞いておくのも悪くないだろう。そう思ったから……。
点滅している留守電ボタンを押すと、まず初めに聞こえてきたのは、職場の店長の声だった。次に、私の母親、そして保育園のお母さんたち、最後は学資保険についての説明だった。保険対象者である直輝が死亡したことにより、ある程度のお金が振り込まれるという。
そうだ、直輝が生まれた時、いつか大きな夢を叶かなえる手助けになればと、貯金をかねて保険に入ったっけ。聞き慣れない男性の声は、手続きの詳細を淡々と話していた。
「いつか大きな夢を……か」
今月に控えていた卒園式のプログラムを、私は手に取った。
ようやく書けるようになった漢字まじりの「さめじま直き」という字が、私は大好きだ。『直』の字が、ひらがなより遥はるかに大きな存在感で、一生懸命書いた想いがひしひしと伝わる。
そして、プログラムには直輝の将来の夢も書かれてあった。
『ぼくのゆめは、たくさんのひとを、えがおにしてあげることです』
私は、卒園式のプログラムを胸に抱きしめ、今から会いに行くね……と、小さく呟つぶやいた。
あらかじめ用意しておいた、ひも状のタオルを押し入れから取り出した。
全身を支えられるようなひもなど、うちにはない。こんな小さな田舎で、そのような物を買っている姿を誰かに見られたら、計画に気づかれ、直輝に会いに行けなくなってしまう。そこで、バスタオルを縦三本に切り分け、それらをしっかりと結び合わせて、一本のひも状にした。
そして、ひもを吊るせるところはないか、私は家の中を見渡し、ふと目についた脱衣所のドアを開くと、溜まった洗濯物の悪臭が鼻をついた。
直輝が旅立ってから、まともに鏡すら見ていないため、ここのドアを開けるのはあの日以来だった。
すると、床に白い粉が散らばっている。
「なにこの白い粉……」
そうだ、あの日の朝、直輝が洗濯洗剤をこぼしたと言っていた。
帰ったら一緒に片づけようねと言ってたっけ。
私は、直輝のいない現実を、再び目の当たりにした。
ふと洗濯機の隅を見ると、いつも台所で使っている踏み台が置いてある。
「どうしてこんなところに……?」
踏み台の上を見上げると、新しい洗剤やタオルをストックしてある棚の上に、小さな箱が置いてある。
私は、つま先立ちでその小さな箱を手に取り、そっと蓋ふたを開けた。
中には、折り紙で包まれたアーモンドほどの大きさの物が、ざっと七、八個入っていた。
箱を洗濯機の上に置き、折り紙で包まれているものを一つ開いてみると、甘い香りのチョコレートが姿を現した。
しかも、直輝が一番好きだった「ショコラ」という名前のチョコレートだ。
また、包んであった折り紙の裏には、なにやらクレヨンで文字が書かれてある。
『ママのわらったかおがだいすき 直きより』
それは、私が大好きな漢字まじりの直輝の字だった。
覚えたばかりの文字が、力強く書かれてある。カラフルなクレヨンをぎゅっと握り、一生懸命書いている直輝の姿が、鮮明に浮かんだ。そして、私は他の祈り紙をすべて開いた。
『えんそくのときには たまごハンバーグつくってね 直きより』
『おとなになったら おおきくてまるいケーキかってあげるね 直きより』
『としをとっても ずっとげんきでいてね 直きより』
『パパと なかなおりできるといいね 直きより』
『びょうきのときは かんびょうしてあげるね 直きより』
『パパへ ママとはやくなかなおりしてね 直きより』
『ママとパパのこどもにうまれてよかったよ 直きより』
全部で八個のショコラが姿を現した。
直輝の息吹を、感じずにはいられない。「ねぇママ」と私を呼ぶ直輝の声が、すぐ後ろから聞こえてくるような、妄想ともいえる錯覚が私を襲った。
そして八個のショコラが入っていた箱の底に、緑色の折り紙が一枚入っているのを見つけた。
直輝が一番好きだった、緑色の折り紙。
裏返すと、マジックペンで『そつぎょうしょうしょ』と書かれてある。
『ママどの
まいにちおべんとうつくってくれて ありがとうございました。
ママも おべんとうそつぎょうです。
ごほうびに えがおのたねをあげます。
ショコラをたべると えがおになるよ』
今まで一粒たりとも流さなかった涙が、心の奥底から溢れ出るかのように、泣いても泣いても、泣いても泣いても、一向に涙は止まらない。
そうだ、あの子は誰よりも人を笑顔にすることが大好きだった。夫と別居した時も、仕事がなかなか見つからなかった時も、いつも私を笑わそうとしてくれた。
小さなこの箱も、きっと卒園式まで隠しておこうと思ったのだろう。踏み台に乗り、背伸びした拍子に洗剤を落としてしまった情景が目に浮かぶ。
今の私を見たら、直輝はなんて言うだろう。
寂しさに耐えきれず、自ら命を絶とうとしている私を、あの子はどう思うだろうか。
左腕に掛けたままの、ひも状のタオルを右手に持ち、私は散らばった洗剤の粉をかき集めた。これでもか、これでもかってほど床を拭きながら、心の中で直輝に謝った。
ごめんねナオくん……ごめんね……。
直輝は、私の笑顔を心から愛していた。
夢の中の直輝が泣いていたのは、きっと悲しかったからじゃない。
私を恨んで泣いていたわけでもない。
私が笑顔じゃないから泣いていたんだ。
私の笑顔を祈る思いで泣いていたんだ。
自分のために生きることが辛いなら、誰かのために生きてみればいい。
──死ぬ気で生きてみよう──
一度捨てようと思った命だ。何が起きたって、ちょっとやそっとの苦労は乗り越えられる。
私は、脱衣所を掃除したあと、部屋全体もピカピカに掃除した。直輝の玩おもちや具やお道具箱も、元通りの位置に片づけた。
人生に終止符を打つのは簡単だ。だからこそ、私は死ぬ気で生きる。いつでも死ねるという覚悟をもって今を生きる。取りとめもなく流した涙のお陰で、もう一生泣かず、強く生きていけるかもしれない──。
昨日までは想像がつかなかった「未来」に向かい、一歩踏み出そう。
そう決意した瞬間、私はあることが頭に浮かんだ。
その「あること」を夫に伝えるべく、彼に電話をかけた。
夜になり、会社帰りの夫が訪れた。弁護士を連れてきた時とは打って変わって綺麗になった部屋を、彼は隅々まで見渡している。
彼が住んでいたころ使っていたマグカップに、淹れたてのコーヒーを注ぎ、そっと差し出すと、深呼吸するかのようにコーヒーの湯気を吸いこみ、そして一口すすった。
夫は、安らいだように大きく息を吐くと、マグカップをテーブルに置いた。
マグカップの底がテーブルにコトンと当たる音と共に、私は「あること」を切り出した。
「ねぇ、もうやめない?」
「何をだよ」
「別居も、訴訟も」
「絶対勝てるってあの弁護士も言ってるし、こちらの要求額が通るかもしれないって」
「あなたが欲しいのは、本当にお金なの?」
「……」
「本当は、お金なんかじゃなくて、直輝と過ごせなかった時間を、取り戻したいんじゃない?」
「……」
「保育園の先生たちは、本当によくしてくれたわ。直輝も先生たちが大好きだった」
「それとこれとは、話が別だよ」
「別じゃない! あなたは……あなたは訴えることに精力を注ぐことで、自分の気持ちをごまかしているのよ」
私は、脱衣所で見つけた小さな箱を、夫の前に差し出した。
「開けてみて。直輝がくれた、再出発の種よ」
「再出発の……種?」
夫は、ショコラが包まれていた折り紙を手に取り、一枚一枚メッセージを読んでいった。そして最後に、私宛の『そつぎょうしょうしょ』を読み終えると、唇を噛みしめ、声を震わせて泣いている。
きっと、夫も寂しかったんだ。
かけがえのない息子の死を、受け入れられず苦しんでいたんだ。
やり場のない気持ちを、ぶつけるあてもなく、保育園を訴えることで気持ちのバランスを取っていたのかもしれない。
私は、今までこんな風に夫の心と向き合ったことがあっただろうか。いや、振り返ればいつも私は怒ってばかりだった気がする。「親なんだから」「夫なんだから」「家族とは」「父親とは」と、凝り固まった自分なりのルールを彼に押しつけるばかりだった。だから夫は、居場所を失ってしまったのかもしれない。家や家族に対して、居心地の悪さを感じてしまったのかもしれない。
もう繰り返さない。繰り返しちゃいけない。自分なりのルールに彼を当てはめるのではなく、一人の人間として、彼の心と向き合ってみよう。
そうすればきっと、やり直せる。いいえ、やり直すんじゃない。新たに始めるんだ。
直輝は、そんな私たちを見れば喜んでくれる。絶対に喜んでくれる。
「ねぇ、あなた。私と一緒にお店やらない?」
「店? 何の?」
「お弁当屋さん」
「そんな簡単に始められるわけないよ」
「確かに、簡単じゃないかもしれない。でも、挑戦してみなければ何も始まらないでしょう? 小さくてもいい、あの子の夢を叶えてあげられるのは、私たちだけだと思うから」
「夢?」
「ええ、これを見て」
私は、卒園式のプログラムを夫に手渡した。そこに書かれている直輝の夢を、彼は黙って読んだ。
『ぼくのゆめは、たくさんのひとを、えがおにしてあげることです』
彼は、何度も何度も読み返していた。
何もかも、すぐにうまくいかないかもしれない。夫との生活も、新たな挑戦も。
でも、スムーズに進むことが目的ではなく、着実に前を向くことが、今の私たちには正解なのかもしれない。
そして私たちは、直輝がくれたショコラを、泣きながら全部食べた。
── 一年後 ──
夫が訴えていた保育園への告訴は取り下げ、直輝の夢をサポートするためにかけていた学資保険からの二百万円と、賠償責任保険の死亡見舞金五百万円をすべて店の資金にあて、私たち夫婦は小さいながらもお弁当屋を開店させた。
学生時代に定食屋でバイトしていたという夫は、必死で調理師免許を取得し、日々キッチンに立っている。
私が勤めていたスーパーからも、たくさんの協力を得て、ようやく軌道に乗ってきた。
「いらっしゃいませ。あら、あみちゃんこんにちは。今日はおつかい?」
「うん。弟が誕生日だから、玉子ハンバーグ買いに来たの」
「そうなの、それはおめでとう。弟さんはいくつになったの?」
「三つ」
「じゃあ、今日は特別あみちゃんと弟さんに、ショコラの種を三つずつあげちゃおうかな」
「わーい、ありがとう。でも、どうしてこのショコラもお弁当屋さんの名前も、『ショコラの種』っていうの?」
「このショコラはね、笑顔の種なの。だから、ここでお弁当を買ってくれた人が、みんな笑顔になるよう、このショコラもお店も『ショコラの種』って名前にしたのよ」
「そうなんだ、すてきな名前だね」
「ありがとう」
そして、小さなお客さんは屈託のない笑顔を見せてくれ、小袋片手に帰って行った。
キッチンで汗まみれになっている夫は、小さなお客さんの背中を見て微笑んでいる。私は、お店の外へ出て空を見上げた。
ナオくん、見てる? パパもママも毎日笑顔で頑張ってるよ。
ありがとね……ナオくん、ありがとう。パパとママの子どもに生まれてくれて、ありがとう。
その夜、私の夢の中に久々に直輝が現れた。
満面の笑みで駆け寄ってくる直輝を、私は思いきり抱きしめた。
(完)
*第2話以降は書籍でお楽しみください。
目次
ショコラの種
最期の小説
真昼の花火
おしるこ
家族だった家族
黄色い鳥と赤い鳥
一本のオール
【単行本好評発売中!】
この本を購入する