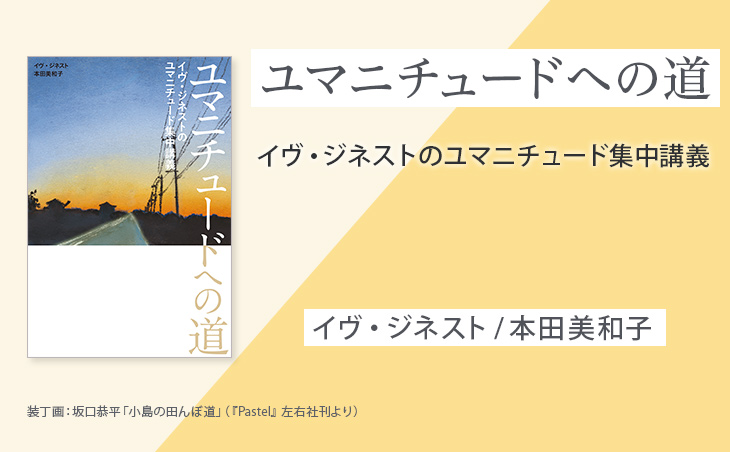第4回
どういうきっかけでユマニチュードを考案したのですか?
2022.11.22更新
フランスで生まれたケア技法「ユマニチュード」。ケアする人とケアされる人の絆に着目したこのケアは日本の病院や介護施設でも広まりつつありますが、現在では大学の医学部や看護学部などでもカリキュラムとして取り入れられてきています。本書は、実際に大学で行われたイヴ・ジネスト氏による講義をもとに制作。学生たちとジネスト氏との濃密な対話の中に、哲学と実践をつなぐ道、ユマニチュード習得への道が示されます。
「目次」はこちら
病院での仕事に就いた初日の‟奇跡”
私は幼い頃から考えることが好きで、11 歳のときにはじめて哲学の本を読みました。またスポーツも得意で、国の強化選手に選ばれたこともあります。ただ、勝ちにこだわる試合は苦手で、運動は喜びのためにあると感じていました。そして体育学の教師になろうと思い、大学に入りました。
フランスの体育学のトレーニングには、外科医とほぼ同じレベルの解剖学を学ぶコースがあります。その他にも心理学、生理学など、サイエンスに基づくさまざまな分野を学びました。
体育学を7年間教えたのち、私は新しい分野に踏み込むことにしました。病院です。病院で働く職員たちの腰痛を予防するための研修をしてほしいと、フランス文部省から依頼を受けたことがきっかけでした。私は同僚のロゼット・マレスコッティとともに病院を訪れました。
研修先の病院では、患者さんのなかでとくにケアをおこなうことが困難な人を10 人選んでもらい、その方たちのケアを職員と一緒にやってみることから始めました。私自身はつねに健康で元気でしたから、それまで病院とはほとんど縁がありませんでした。この仕事がきっかけではじめて、重い病気の方々にお目にかかることになったわけです。
そこでまず、看護師さんたちに普段の仕事を教えてもらうことにしました。ベッドサイドへ行って看護師さんたちが患者さんの身体を拭くのを見学したとき、なんと込み入った難しい作業をしているのか、と非常に驚きました。
私にとってはじめての患者さんは半身麻痺で、自分ではまったく動けないという、体重が120キロもある方でした。私たちが病院を訪ねる前の週に、その患者さんを移動させようとした2人の看護師がぎっくり腰になってしまい、職場に来られなくなってしまっていました。
病室に足を踏み入れると、ひどい臭いが充満していました。看護師さんたちは、便にまみれたその男性患者さんの身体の向きを変え、オムツを替え、シーツを取り替えるという作業を手際よくおこなっていきます。そのケアを見ながら私は感銘を受けると同時に、心配になりました。というのも、このケアが終われば私の仕事の出番だからです。
私の仕事というのは、ベッドで清拭を受けた患者さんを椅子に移動させることでした。フランスでは1日中ベッドで寝たきりで過ごすことは許されず、ケアが終わったら椅子に座ってもらいます。それを私がやらなければならないのかと思うと、ドキドキしてきました。こんなに重い人をどうやって動かせばいいのでしょうか。私にとって生まれてはじめての経験です。
そこで困った私は、どうしたと思いますか?
―アイコンタクトをとった?
惜しいですね。その男性は目を閉じていたので、私は男性の正面に立って、こうお願いしたんです。「申し訳ないですが、椅子に移っていただきたいので手伝ってくださいませんか」
すると、その患者さんの目がパッと開き、私のほうに手を伸ばして動こうという意志を見せてくれたのです。そして自分の片足で立とうとし、わずかな援助で椅子に座ることができました。
その光景を見た看護師さんたちは、驚愕しました。なぜなら、それまで医師や看護師が何をやってもまったく反応せず、協力してくれたこともなかったからです。しかし、そもそも彼に何かをお願いしたこともありませんでした。
医師も看護師も、この患者は半身麻痺で反応がなく、何もできないのだと思い込んでいたのです。ところが私が出会って20 分後には、彼は自ら起き上がろうとしました。
病院での初日に、私は多くを学びました。医師も看護師も、私が生み出した状況を見て「奇跡だ」と言いました。でも、なぜ私にこんなことができたのでしょう?
―偶然……でしょうか?
それもそうですね。何より、私自身が病院の文化をまったく知らなかったことがその理由だと思います。「患者さんは何もできないから、私たちが全部やってあげる」という病院の文化を知らなかったので、私は彼にお願いし、彼はそれを聞き届けてくれました。
「自分は何も知らないから、学ばなければならない」という謙虚な気持ちがいかに大切であるかを、私はこの日に学びました。
人としてあるべきコミュニケーションが‟ない”現場
病院で通常おこなわれるコミュニケーションといえば、医師や看護師が一方的に「○○してください」「私が○○します」と患者に伝える行為ばかりです。
患者との‟対話”ではなく、ほとんどが一方通行の通告ですから、患者からすれば、それは命令のようでもあります。ケアする側に「患者さんにお願いする」という発想はありません。
私たちは誰もが一生懸命仕事をしています。優しさと愛を届けようと思いながらケアをし、自分はよくやっていると感じる人もたくさんいるでしょう。その気持ちに間違いはありません。
ただ、実際におこなっている行為を客観的に評価する必要があります。これがなぜ大事なのでしょうか?
―相手に無理強いしているかもしれないから?
そうです。人と人は、互いが元気であれば、互いに情報をやり取りして容易にコミュニケーションをはかれます。ところが片方が病気になると、元気な人と同じような方法ではうまくコミュニケーションができません。情報の一方的な発信者と、一方的な受けとり手という固定された役割に陥ってしまうのです。
この事実を、多くの医師や看護師は知らずにいます。ですから、ケアする人になろうとする私たちは、援助を必要とする人との双方向的なコミュニケーションの方法を、あらかじめ学んでおく必要があるのです。
優しさを持っていても、表現できていない
病院や施設で、優しさと愛を届けるためのコミュニケーションが充分にはおこなわれていない―そう感じた私は、その事実を客観視するために、あらためてコミュニケーションの量を測定してみることにしました。
すると驚く結果が出ました。看護師や医師が寝たきりの人に直接話しかけていた時間は、1日24 時間のうち2分しかありませんでした。相手の目をしっかり見てアイコンタクトをとるのは、1日のうち10 回。また、相手を大切にした優しさを伝える触れ方はゼロでした。この事実を、私は入院患者さんへのケアを観察してはじめて知ることになったのです。
私が日本を訪れ、最初に見学した東京の病院では、そこで働く看護師さんたち個々人が充分に優しいというのはすぐに見てとれました。けれども相手の目を見て話すことはなく、伝える言葉も仕事の内容に関する宣言が主でした。職務を次々にこなし、てきぱきと仕事をしていますが、その触れ方が優しさを伝えているとは言い難く、互いを尊重し合うという観点のコミュニケーションは欠落していました。
その看護師さんたちも、みなさんと同じように優しい心をもち、優しさと愛という価値を大切にしています。しかし、それをうまく表現できていない。ここに大きな落とし穴があります。
【単行本好評発売中!】
この本を購入する