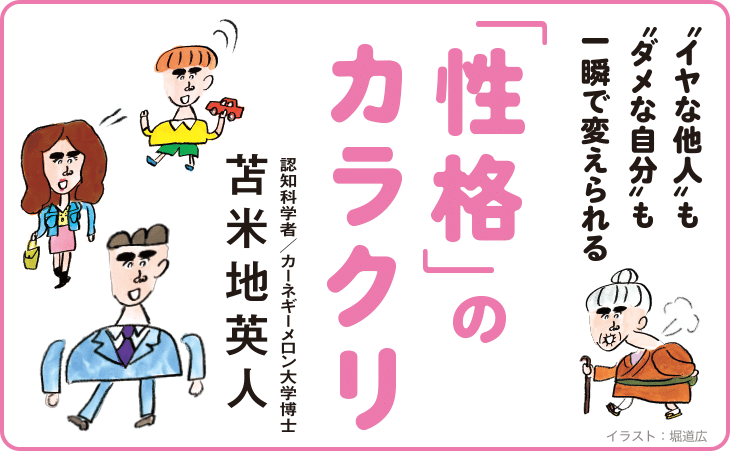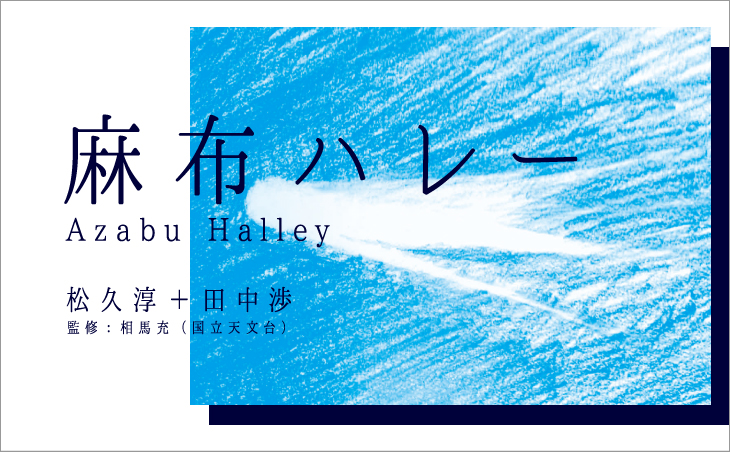第6回
「性格」や「心」に悩んだり振り回されたりするのはナンセンス
2019.03.14更新
臆病、意地っ張り、せっかち…。あなたは自分の「性格」に苦労していませんか? 性格は変えられないというのはじつはウソ。性格とは、人が生きていく上で身に付けた「対人戦略」なのです。気鋭の認知科学者である苫米地英人博士が、性格の成り立ちや仕組み、変え方などを詳しく解説します。
「目次」はこちら
少々話がそれてしまいましたが、「性格」という実体のないものを「存在する」と信じ込むことは、まさに「空なるものに実体を求める」ことにほかなりません。
そしてそれは、さまざまな弊害をもたらします。
まず、「性格」という概念が、問題の解決を妨げることがあります。
たとえば、あるスポーツ選手が、「どうしても、いざというときに力を発揮できないのは、自分の性格が弱いからだ」と悩んでいたとします。
このような場合、本当の原因は、その人が持つ自己イメージや自己評価、ブリーフシステムにあることが多く、問題を解決するためには、それらを変える必要があります。
ところが、そこに思いが至らず、「原因は性格の弱さにある」などと信じ込んでいては、解決は遠のくばかりです。
また、みなさんは日々の生活の中で、「あの人は性格がいいから、みんなに好かれる」「あの人は性格が悪いから、恋人もできないし、仕事もうまくいかない」「あの人は性格が暗いから、一緒にいたくない」といった言葉を耳にしたことはありませんか?
あるいは、企業の人事採用担当者などが「性格が明るい人を採用したい」と語っているのを目にしたことはありませんか?
「性格」という概念は、このように、他者にレッテルを貼り、「良い」「悪い」の評価を下す際に用いられがちです。
性格診断占いや性格診断テストの結果を、あくまでもカジュアルな話のネタとして楽しむ分にはいいのですが、「性格」について本気で論じたり、それによって人間を分類したりすることは、差別につながりかねません。
この世の中には、絶対的に「良い」ことも、絶対的に「悪い」ことも存在しないのです。
もちろん、法律や倫理、道徳によって「良い」「悪い」とされていることはあります。
しかし、法的には犯罪にあたらなくても、倫理的、道徳的には「悪」にあたる行為はたくさんありますし、逆に、法的に犯罪とされていても、倫理的、道徳的には「善」にあたる行為もあります。
そもそも、時代や場所が変われば、法律や倫理、道徳といったものも変わります。
殺人や盗みなどは、多くの国、多くの時代で「してはならないこと」「犯罪」とされていますが、ひとたび戦争が起これば、逆に敵を殺すこと、敵のものを略奪することは英雄的な行為であるとみなされます。
人にさまざまな側面があるように、世の中の事象には、必ず功罪の両面があります。
体に害を及ぼす菌や異常な細胞を攻撃する薬が、体にとって必要な菌や正常な細胞まで攻撃してしまうこともあれば、自然を破壊して作った施設が、過疎に苦しむ地元の人たちの生活を支えることもあります。
職場の中で全員から嫌われている人の存在が、実は職場の団結力を高めるうえで一役買っていた、ということもあるでしょう。
この世界において、何が「良い」ことで何が「悪い」ことなのかを厳格に区別し、判断することは、本当は誰にもできないのです。
「性格」に関しても同様です。
すでにお話ししたように、そもそも「明るい」「暗い」「真面目」「不真面目」などは相対的な評価であり、それらを判断する絶対的・客観的な基準は存在しません。
さらに、ある人からは「明るく快活で、誰とでも仲良くなれる人」と思われている人が、別の人からは「暑苦しくて遠慮がなく、何の深みもない」と思われているかもしれませんし、「ちょっとしたことでくよくよ悩んでしまう人」は、裏を返せば、「慎重で内省的な人」ととらえることもできます。
ただでさえ実体がなく、定義があいまいな「性格」というものを、これまた区別が難しい「良い」「悪い」といった基準で判断する。
それがいかに無意味なことか、みなさんにはおわかりいただけるのではないかと思います。
ちなみに、「人にはそれぞれ、生まれ持った性格がある」という考えをベースに「性格」という概念を生み出し、「性格学」を発展させたのは、西洋の医師や心理学者たちです。
その源となったのは、古代ギリシャ時代の医師・ヒポクラテスが提唱し、古代ローマ時代の医師・ガレノスが継承・発展させた「四体液説」です。
四体液説は、「病気は、血液、粘液、黄胆汁、黒胆汁の4種類の体液のバランスが崩れたときに生じる」というもので、古代ギリシャ・ローマでは、それぞれの体液の過少と人の気質には関係があると考えられており、さらに中世ヨーロッパでは四体液説は、占星術とも結びつけられるようになりました。
病理解剖学が誕生した19世紀以降、徐々に四体液説自体は顧みられなくなっていきましたが、個人を気質や性格によってとらえたり分類したりするという考え方は、その後も西洋社会に受け継がれ、ドイツの精神科医エルンスト・クレッチマー、スイスの精神科医カール・グスタフ・ユング、オーストリアの精神科医ジークムント・フロイトなどが、研究を行っています。
1960年代には、行動特性に応じて人間の性格を9つのタイプに分類する「エニアグラム」という性格論が作られ、1970年代以降、アメリカの精神医学や心理学の研究者が注目するようになり、やがて世界各国に広がっていきました。
アプローチの仕方はそれぞれ異なりますが、「性格」というあいまいなものを、観察者側の一方的な基準によって分類したり、「こういうタイプの人間の○%は、こういう考え方をし、こういう行動をとる」といったデータを示したりすることにあまり意味はないと、私は思っています。
なお、「性格」と同じように「目に見えず、実体もないのに、まるであるかのように語られている」ものに、「心」があります。
私たちはよく「心が温かい」「心が冷たい」「心が安らぐ」などと口にしますが、実際には、「心」などというものは、どこにもありません。
たとえば、「心が弾む」「心を躍らせる」といった表現があります。
たしかに、嬉しいことがあったときや恋をしたときなど、心臓がどきどきしたり、体が熱くなったりしますが、これも、起こった出来事を情報として脳が処理した結果、自律神経が優位になり、アドレナリンなどが放出されて、体が興奮状態になり、心臓の動きが活発化したりするだけのことです。
感情を揺さぶられたとき、心臓周辺に変化が表れやすいことから、私たちはなんとなく、胸のあたりに「心」があるような錯覚を抱いていますが、あるのは、脳の中で行われる情報処理現象と、それに伴う身体反応のみなのです。
もちろん、「心で感じる」「心で思う」などということも一切ありません。
人が考えたことはすべて、脳の中で行われた情報処理現象の結果にすぎません。
みなさんの中には、もしかしたら「自分が~なのは、心が弱いからだ」と考えたり、「私は心が汚い」と悩んだりしている人がいるかもしれませんが、そのような考えは、今すぐ捨ててしまいましょう。
繰り返しますが、「性格」「心」などというものは存在しません。
存在しないものに振り回されたり縛られたりするのは、時間とエネルギーの無駄でしかないといえるでしょう。
■ ポイント
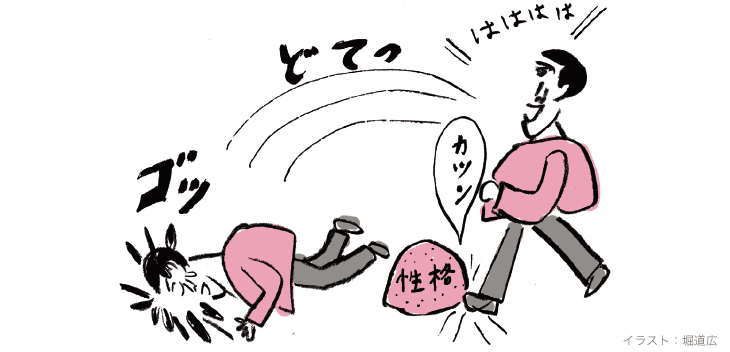
・「性格」という概念が、人生の問題解決を妨げる。
・世の中に「良い」「悪い」を判断する絶対的・客観的な基準は存在しない。
・自分や他者の性格、心で悩むのはエネルギーの無駄。
【単行本予約受付中!】
この本を購入する