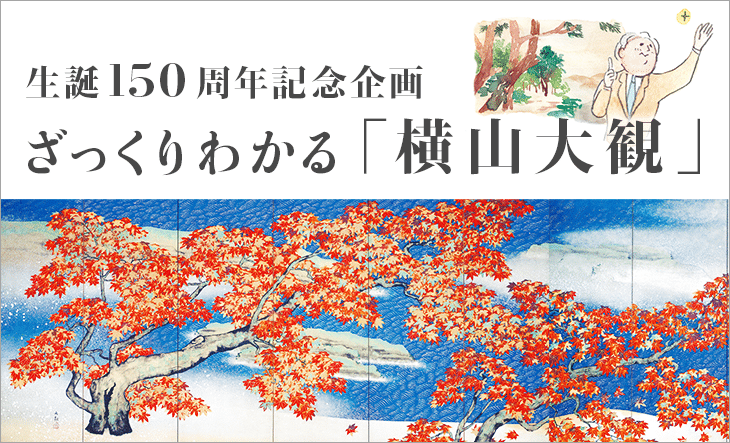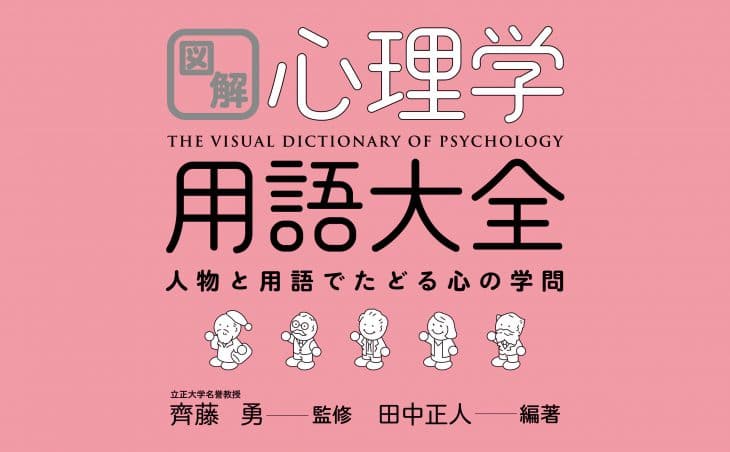第18回
三島由紀夫――「軍隊に希ったものが死だけだというのは偽りだ」(第5回)
2023.07.28更新
『文豪の死に様』がパワーアップして帰ってきました。よりディープに、より生々しく。死に方を考えることは生き方を考えること。文豪たちの生き方と作品を、その「死」から遠近法的に見ていきます。
「目次」はこちら
昭和19年(1944)、大日本帝国の無条件降伏という大惨敗を翌年に控えた10月、三島は東京帝国大学法学部法律学科に入学した。文学部ではなく法学部に入ったのは父の意向をうけてのことだ。
自分の願いより、父の望みを優先させる。
忤(さか)うること無きを宗とせよ。
親の庇護下にいるしかなかった三島少年に他の道はなかっただろう。
だが、忤(さから)わなかった理由はそれだけではない。「どっちにしたって将来は戦争で死ぬだけ」と思っていたから固執しなかったのだ。
有無を言わさぬ父の強制で、専門は法律を選ばされた。しかし遠からず私も兵隊にとられて戦死し、私の一家も空襲で一人残らず死んでくれるものと確信していたので、大して苦にはならなかった。(『仮面の告白』より)
軍国教育を受けた当時の十代は、兵士になって死ぬのが当たり前と思っていた、そうだ。そう教えられていたし、実際の戦局も悪化する一方だった。日本本土への空襲が始まったのは昭和17年で、主要都市への無差別な絨毯爆撃が始まったのは19年11月だ。敗色は日々濃厚になっていた。どう転んでも、日本に勝ち目はなかった。
余談だが、私はかつて、二十代半ばで敗戦の日を迎えた我が祖母に尋ねたことがある。
本当に玉音放送を聞くまで日本は勝つと信じていたのか、と。
答えは否、だった。
祖母はこの戦争はもう無理、絶対負けると思っていたし、いつ死んでもいいとも思っていた、と言った。ただし、この「いつ死んでもいい」は「お国のためなら」の文脈ではない。焼夷弾がばら撒かれ、街が瞬く間に炎に包まれる空襲のすさまじさを真近に見、また広島や長崎に落ちた「新型爆弾」の噂も耳にしたことで、祖母は消極的諦観に包まれていったのだ。
祖母が大阪空襲の光景を語ってくれた時の言葉は今でも忘れられない。
「玉造の砲兵工廠(注1)が空襲で焼けた時は、空が真っ赤に染まってなあ。それはもう綺麗やったで。それ見てたら、『このまま死ぬんやったらそれはそれでええわ。もうええわ』と思たんや」
幸い祖母は生き残ったから今の私がいるわけだが、祖母が死を受け入れる心境に至った過程を思うと言葉もない。
大阪の一庶民である祖母ですらこうだった。まして三島のように物理的にも階級的にも知性的にも限りなく“日本の中央”に近い場所にいた人間が、輝かしい日本の勝利、など信じていたはずがなかろう。
処女作『花ざかりの森』を出版し、四千部がほんの一週間で売り切れたのを見届けた三島は「これで私は、いつ死んでもよいことになったのである」(「私の遍歴時代」)と思ったそうだが、これは我が祖母の「いつ死んでもよい」とは大いに異なる。ロマンの香りに満ちている。
そのころ私は大学に進学しており、いつ赤紙が来るかわからない状態にあった。
私一人の生死が占いがたいばかりか、日本の明日の運命が占いがたいその一時期は、自分一個の終末観と、時代と社会全部の終末観とが、完全に適合一致した、まれに見る時代であったといえる。私はスキーをやったことがないが、急滑降のふしぎな快感は、おそらくああいう感情に一等似ているのではあるまいか。
少年期と青年期の境のナルシシズムは、自分のために何をでも利用する。(「私の遍歴時代」より)
三島のナルシシズムは戦死をもきらびやかな装飾品に見立てた。
二十歳の私は、自分を何とでも夢想することができた。薄命の天才とも。日本の美的伝統の最後の若者とも。デカダン中のデカダン、頽唐期の最後の皇帝とも。それから、美の特攻隊とも。
若き日のロマンティシズムがタナトスと結びつくのは何も珍しいことではない。まして戦中である。若者の死は「美しい悲劇」であり、「あってはならぬこと」ではなかった。戦争末期の若い男女にとって、戦死は今の交通事故死よりも“身近な最期”だったのだろう。むしろ永らえて天寿を全うする未来の方がピンとこなかったのかもしれない。
父がどれだけ期待をかけようと、母がどれほど溺愛しようと、自分は死ぬ。
死んで初めて自分は他者から干渉されない純粋な自分になれる。
家庭でも学校でも強い抑圧を受けて生きてきた鋭敏な少年にとって、それはむしろ救いとすら感じられたのかもしれない。
「戦争がすんだら、不良少年の親分になりたい」
しかし、それならばなぜ自ら志願して軍隊に入らなかったのか。
当時、帝大生は特別幹部候補生として志願できた。幹部候補生なら普通の入隊と違い、最初から将校への道が約束されている。
その疑問に対して、三島は一兵卒として応召するつもりだったからだ、と答えている。そして、傍証になる証言もある。
昭和十九年(一九四四年)の初秋、入隊のため私は上野駅へ行った。(中略)ところで、あの広々とした上野駅頭にあらわれた際、三島は確かに少しはにかんでいた。(中略)
彼が初秋の駅で、一寸恥ずかしそうにしていたのは、皆と違って入隊せず、彼一人大学に入り、引続き学生生活をするからではなかった。(中略)将校になる道をとらず、一兵卒として軍隊に入ることについては、彼は十分考慮を重ねて、すでに決心をしていたのである。召集されぬかも知れぬという万一の僥倖を頼みに社会に残るわけでは決してない。当時の三島の敵愾心は本当に烈しいものがあった。ただ晩年の彼とは違い、敵と戦うに文の道をもってしたかっただけである。(三谷信『級友 三島由紀夫』より)
これを書いた三谷信氏は、学習院初等科から高等科まで同級生で三島の親友だった人だ。第二回で引用した学友たちよりよほど近い関係にあった。学校生活での三島の顔を一番よく知っている人物といってよいだろう。その人は、三島の言葉を信じていた。
けれど、実際のところはどうだったろう。
明治大正の頃なら官公立学校や一部私学に在学中の学生生徒は徴兵が猶予されたが、昭和に入ると特権は徐々に縮小され、三島が入学した月には19歳以上の文系学生は学徒出陣の対象者になった。よって、徴兵逃れが目的でなかった、という点はその通りのはずだ。
また、三谷氏は“しらっこ”(氏はもうひとつのあだ名「青白」の方を採用しているが)が軍隊に入ったところでどうせ役に立たないとみなされていたので、さほど白眼視もされなかった、としているが、三島にとってそう見なされる空気自体が屈辱だったに違いない。よって、三島に入隊を待ち望む気持ちは確かにあったのだろう。まして、軍への入隊はホモソーシャル社会への再挑戦を意味していたはずだ。
けれども、彼が本当に一兵卒としての参入を望んでいたかは少々疑問だ。というのも、彼は心を許した友に対し、こんな稚気に満ちたことを言っているのだ。
その晩、私の家で彼は、又こうもいった。「戦争がすんだら、不良少年の親分になりたい」と。戦争がすんだら、と条件つきの話とはいっても、当時、つまり昭和十九年の夏といえば、不良生活を楽しむ社会とは、真反対の世相であり、又、彼は所謂「青白」であり、どこまで本気なのか、私は、彼の真意が、計りかねていた。すると、大きな瞳を輝かせて、その言葉をくり返した。「何故かい?」と聞くと、彼は「そりゃ君面白いよ、あいつに、これをやって来い、といい、こいつにはこれをやらせたりして、とっても面白いと思うよ」とだけいった。(三谷信『級友 三島由紀夫』より)
なんというお山の大将願望! ホモソへの単純な憧れ、ここに極まれり、である。不良グループ(とその発展形のヤクザ)こそ、ホモソの究極系だ。それに憧れる三島に、軍幹部への憧れがなかったとは思えない。あるいは、彼の根底にあるマゾヒスティックな側面が一兵卒を選ばせたのかもしれないが、もっと現実的な話として、志願は父が止めていたのではないか、という気がする。この点については後ほど触れる。
それにしても、言うに事欠いて「不良少年の親分になりたい」とは。この、19歳にしてはあまりに幼稚な願いは、前回紹介した「『日本少年』や『少年倶楽部』の純粋な美学を通しただけ」という美輪明宏氏の見解に通ずる。三島にとって「スクールカースト的ホモソーシャルの上位にいる自分」は何よりも価値があったのだろう。得られなかったものは、常に一番輝いて見えるものだ。
そう考えると、『仮面の告白』では幼きリビドーの発露のように書かれている「汚穢屋」や「練兵から帰るさの軍隊」や「神輿の担ぎ手」もはたしてエロスの象徴と素直に受け取ってよいものか。さらにいえば、己の同性愛的傾向について告白する部分も真に受けていいのか、少々疑問が出てくる。
三島の性的指向について、美輪氏はゲイではなくバイだとしている。けれど、肉体的な性指向はストレートだったような気がしてならない。この点についてはここではあまり深入りしないが、美輪氏は三島が己が女性に対して不能でなかったことを素朴に喜んでいたと証言している。それは長年の不安感が払拭されたことでの安堵だったようだが、女性と性交できることが彼にとっては“喜び”だったわけで、ならば少なくともゲイではないのではないか。このあたりの心理、当事者でない私にはわかりかねる部分もあるのだが。
なんにせよ、三島が同性愛的傾向を示したのは、単にまわりに恋愛対象となる女性が少なかったから、とも考えられる。男子校ではよくある話だ。『仮面の告白』で疑似恋愛の相手となる園子のモデルは三谷氏の妹とされている。親友の妹をモデルにするあたり、手駒の少なさが伝わってくるではないか。さらに言うなら、男性への眼差しはエロスではなく、もっと単純なホモソーシャルへの渇望ではなかったか、という気がするのだ。
簡単にいうなら、スクールカースト上位タイプのキラキラ男子への憧れ、がその正体ではないか、と。三島の時代のキラキラと今のそれはかなり違うだろうが、キラキラへの憧れそのものはいつの時代もある。そして、その憧れには二種類ある。
ひとつは、キラキラした他者の特別な存在になりたいという恋的願望。
もうひとつは、「自分があれになりたい」という願望だ。
三島の憧れは後者だった。
学級のような同質性の高い狭い社会のてっぺんに立つ存在になってみたい。
それが三島の本質的な願望のように思えて仕方ない。
そして、その願望が二十代では「文壇での地位の確立」に向かい、それが成し遂げられた三十代で「肉体改造」になり、名声と肉体を得た四十代になって勇躍子供時代の欠損を埋める方向に動き出した。
けれども、最高のホモソーシャル=軍隊は最後の最後で彼を再び拒否した。その光景を前に、やはり欠損の回復は不可能と悟った瞬間、死を選ぶしかなくなったのではないだろうか。
再び閉まった扉の前で
おっと、少々筆が先走ってしまった。
少し話を戻そう。
19歳の三島にとって、軍隊に入ることはホモソーシャルで“あらまほしき地位”を築くセカンド・チャンスだったはずだ。さらに“夢想”を現実にできるチャンスでもあった。
しかし、それは叶わなかった。
入隊検査で不合格になったからだ。
風邪をひいていたのを肺浸潤と誤診された、のだそうである。
入隊検査当日は発熱しており、どうやらそれを利用してオーバーに病状を言い立てた上、病理検査の結果も悪かったのが原因だそうだが、外見も誤診を招いた一因だろう。「しらっこ」が命を救った。
家族は大いに喜んだ。「お国のために死ぬ」建前はどこへやら、検査会場に同行していた父は会場から出るやいなや、息子の手をとらんばかりに、逃げるように走り去ったと自ら告白している。なお、三島は東京ではなく本籍地である兵庫県で徴兵検査を受けているが、これも「東京はひよわな男も珍しくないが、農村だとまわりが頑強な男ばかりだからハネられるかもしれない」と考えた父の画策だったそうだ。三島が志願しなかったのは父の意向でないかと思うのは、こういう経緯があるからだ。十代の三島は、決して父には忤わなかった。
失格を聞いた祖母と母は狂喜した。保守的な官僚一家がこの体たらくである。とはいえ、彼らが特殊だったわけではない。上流階級の人々が遺した戦中の手記や日記などには、我が子の徴兵や徴用をなんとかして逃れようと画策した逸話がたびたび出てくる。支配階級の“愛国心”など、所詮この程度なのだ。
まあそれはいいとして、三島自身もあれだけ死に憧れていたにもかかわらず、いざ入隊となると怖気づいて「出たらめの病状報告」をした。
この、ある意味己を裏切ったような行為について、三島は東京へ帰る電車の中で自省し、ある結論に達したと『仮面の告白』には書かれている。
私は理会(ママ)した。私が軍隊に希ったものが死だけだというのは偽りだと。私は軍隊生活に何か官能的な期待を抱いていたのだと。
さて、お立会い。
ここで彼は「官能」を持ち出しているのだが、果たしてそうなのだろうか。
『仮面の告白』の体裁は自伝小説ではあるが、あくまで“仮面”である。
仮面とは、素顔を隠すものである以上に、他人に見てもらうための顔である。
幼さゆえの単純さを隠すならば、年相応の性的苦悩はもってこいの素材だ。下手に哲学的なことを言うより、大人たちはよっぽど納得してくれる。
辞書では官能を「肉体的快感、特に性的感覚を享受する働き」と定義する。つまり、三島は、「自分のホモセクシャル要素が軍隊を求めさせた」というのを外向きの宣伝に選んだ。
けれども、彼が「ホモセクシャル」と言い換えたものは実は「ホモソーシャルへの帰属願望(できれば上位)」だったとしたら。つまり、軍へのあこがれがsexualityではなくbelongingnessに由来したものだったとしたら。
その後の、自刃を含む一切の行動を貫く一本の筋が見えてくるのだ。
次回は、そこから話を始めたい。
注1
玉造の砲兵工廠
大阪砲兵工廠のこと。東京砲兵工廠とともに陸軍の官営兵器製造所の中心であり、主に火砲とその素材を製造していた。昭和20年8月14日、B-29による集中爆撃で破壊された。
←戻る