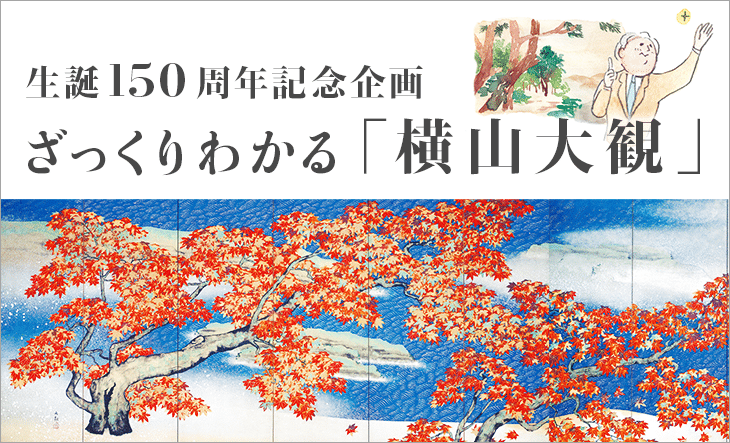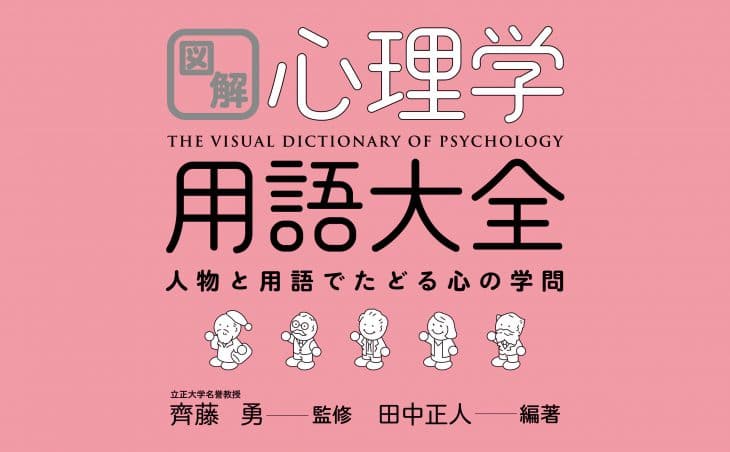第21回
三島由紀夫――英霊になるしかなかった男(第8回)
2023.10.13更新
『文豪の死に様』がパワーアップして帰ってきました。よりディープに、より生々しく。死に方を考えることは生き方を考えること。文豪たちの生き方と作品を、その「死」から遠近法的に見ていきます。
「目次」はこちら
昭和42年(1967)4月、三島は自衛隊に体験入隊した。自衛隊にしてみればよい宣伝材料程度の感覚だっただろう。だが、三島は真剣だった。真剣に兵士体験を求めた。
世間はこれを嘲った。作家が軍隊に入ったらそりゃあ笑われるだろう。右傾化と見て唾吐く者も少なくなかった。特に左がスタンダードだった文化人サークルからは白眼視された。
天皇主義者を標榜すれば、それは確かに右翼ではある。だが、彼の天皇主義は政治的主張ではなかった。軍隊=ホモソーシャルで象徴的テッペンを取るために必要な神具「英霊」というカードを得るための下地に過ぎなかった。つまり、三島の天皇主義はあくまで「自己実現のための手段」なのだ。以前の回で、三島ほど天皇に不敬な人は実はいないのではないかと書いたが、まさにこれが理由だ。
彼は兵隊ごっこがしたかったわけではない。
兵士として死んでいきたかったのだ。国のために死んでみたかったのだ。
そうすれば「英霊になれなかった過去」を回収できるはずだから。
私にとって、時が回収可能だということは、直ちに、かつて遂げられなかった美しい死が可能になったということを意味していた。あまつさえ私はこの十年間に、力を学び、受苦を学び、戦いを学び、克己を学び、それらすべてを喜びを以て受け入れる勇気を学んでいた。
私は戦士としての能力を夢みはじめていたのである。(「太陽と鉄」)
前述した通り「太陽と鉄」は40歳になってから書かれたものである。「戦士としての能力」とか言い始める40代を、あなたはどう思うだろうか。ここでの“戦士”は企業戦士とかそういう感じの比喩ではない。フィールドで肉弾戦をするリアル・ウォーリアーだ。どう考えても幼稚である。だが、三島はその幼稚性を肯定的に捉えていたようだ。
どうしても自分の中には理性で統御できないものがある、と認めざるを得なくなった。つまり一度は否定したロマンティシズムをふたたび復興せざるを得なくなった。ひとたび自分の本質がロマンティークだとわかると、どうしてもハイムケール(帰郷)するわけですね。ハイムケールすると、十代にいっちゃうのです。十代にいっちゃうと、いろんなものが、パンドラの箱みたいに、ワーッと出てくるんです。(「三島由紀夫 最後の言葉」)
実に正直だ。
十代のいろんなものが未解決のままだと告白しているのだから。
だから、ぼくはもし誠実というものがあるとすれば、人にどんなに笑われようと、またどんなに悪口を言われようと、このハイムケールする自己に忠実である以外にないんじゃないか、と思うようになりました。(「三島由紀夫 最後の言葉」)
十代の欠損を取り戻すために、自衛隊に入ったものの、そこでも客分扱いであり、どれだけ真面目に取り組もうが「訓練」以上のことはできない。もし戦争になったとしても、彼が戦場に呼ばれることはない。英霊には絶対になれない。
だから、民兵組織である「楯の会」を作った。
しかし、平和な世の中でいくら私兵を作ったところで、だから何? って話である。おもちゃの兵隊と嘲られても仕方ない。
だから、日本を戦争ができる国にする必要があった。だが、米国がある限り、日本の体制を戦前のそれにすることは不可能である。
ならばクーデター、しかなかった。
最後までホモソに拒否されて
昭和45年(1970)11月25日。
三島由紀夫は、楯の会のメンバー5人を引き連れ、東京・市ヶ谷にある自衛隊の駐屯地に出向き、総監と面会した。この面会は予約されていたものだった。
旧知の間柄である総監と最初はなごやかに話をしていた三島だったが、かねてからの打ち合わせ通り、行動をおこした。
総監を人質に取り、本館前に自衛隊員を集めることを要求。
そして、バルコニーで演説をした。
三島は真剣だった。
この時、すでに彼は恋い焦がれていたホモソーシャルのバカバカしさには気づいていたことだろう。自前のホモソ集団を持って、余計に実感することがあったかもしれない。若い男ばかりの世界は、清さより嫉妬と諂媚(てんび)が目立った。だが、そこは無視することにしたのだろう。どれほどバカバカしくとも、ハイムケール先は他になかったのだから。
自衛隊が呼応しないこともわかっていただろう。でも、ワンチャンスぐらいは期待していたのかもしれない。
用意してきた声明文を、声を限りに読み上げた。だが、誰もまともに聞こうとしなかった。
「男一匹が命をかけて諸君に訴えているんだぞ」
そんな言葉も、虚しく怒号とヤジに消された。
ホモソーシャルは、最後の最後まで、三島由紀夫を拒否した。
どうやっても、過去に勝てなかった。
夢破れた彼に残された道は、ロマンティストとしての自分をまっとうすることだけだった。
平岡公威を諫死(かんし)の英霊にする。
それに賭けて、腹を切った。
これが、市ヶ谷事件の本質ではなかったかと私は思っている。
世界を自分サイズに作り変える
最初、この結論に達した時、私は「でも、そんなやついるか?」と思った。
自分の夢想に現実を合わせようとするなんて、あまりにもバカバカしくないか、と。
でも、気づいた。
そう、いるじゃないか。
自分の欠損を埋めるために世界を作り替えようとした人物が。
「エヴァンゲリオン」のクソ迷惑親父こと、碇ゲンドウだ。
は? なんでアニメキャラ? と思ったあなた。
確かに彼は庵野秀明監督という一個人によって生み出されたキャラクターではある。だが、作品が社会現象になるほど人気を博すには、碇ゲンドウ的モチベーションが一定程度理解され、支持されなければならなかった。つまりそれは「自分サイズに世界を作り変える」欲望を持つ人間が、それほど少なくないことを意味している。
ただ、凡人は夢想するだけだ。
優れた才能があれば庵野監督のように作品にできるだろう。
だが、三島はその斜め上をいける人だった。
現実世界で、本当にやってしまったのである。今生きている人間だと、ロシアのプーチンからも同じ臭いがする。
これを正気と見るか、狂気と見るか。
病という意味では、三島はまったく正気の人だった。どこまでもクリアな人だった。
けれども、もし思い詰めた末に突破してしまった先の世界を狂気と呼ぶならば、彼はやはり狂気の世界に足を踏み入れてしまったのだろう。
彼は、自分の欠損を埋めて、まったき超人になるために、英霊にならねばならなかった。
というより、勝つための最後の手段だった。
英霊になるためには、大義の下に死ななければならない。英雄を英雄たらしめるのは、国を侵そうとする強大な敵だけだ。
最善手は敵により無惨に殺されることだ(マゾヒスティックなエロティシズムとしてもこれが最上級のはずだ)。だが、彼を殺す敵はもはや米帝の犬に等しい日本国政府の手下である官憲ではいけない。また、自衛隊であってもいけない。自衛隊は清き天皇の軍なのだから、大義のためならともかく、私用してはいけない。彼を殺すにふさわしい敵は、平和国家のどこにもいなかった。
ならば次善の策を取るしか無い。
国を目覚めさせるための自死である。
昭和36年(1961)に『憂国』を出す前から、三島は二・二六事件ではからずも賊軍となった青年将校たちに傾倒しつつあった。彼らは純粋だった。その純粋さは、少年誌的ストロング&ピュアボーイの末路にふさわしかった。
いつの時代も、純粋すぎる英雄は時代に殺される。
これでいい。いや、これがいい。
ロールモデルを得たら、あとは道筋に目鼻をつけるだけだ。勝新が喝破した「ないものねだりをするヒト。そしてその結果それをカクトクしてゆくヒト」を最後まで生ききったのである。
三島が最初から自死する覚悟だったのは数々の証言から明らかになっている。
さらに、用意周到にも遺作『豊穣の海』で過去の自分の化身たる登場人物たちに「理想の死」を経験させていった。
「春の海」では、ロマンティーク・ティーンエイジャーの松枝清顕を恋に殉死させた。
「奔馬」では、彼があこがれた武のロマンティークである飯沼勲にハラキリさせた。
「暁の寺」では異国の姫に幼い頃に発揮していた女性性と少年時代の月の子を閉じ込め、コブラに殺させた。
みんな20歳で死んだ。
“理想の平岡公威”はそうなるはずだったから。
過去を封じ込めた三人の人物に理想の死を体現させる一方、掉尾を飾る「天人五衰」の安永透には、自決しないまま生きながらえた場合の自身をシミュレーションさせた。ゆえに透は20歳を過ぎても死なず、狂気の世界に沈む“ニセモノ”として描かれた。これ以上生きていたら、自分はおかしくなるだけだ、とでも言うように。
つまり、『豊饒の海』四部作は平岡公威が三島由紀夫という作家の仮面で韜晦に韜晦を重ねた自叙伝であり、さらには五衰した自分をも想定した「あってほしくない未来記」でもあった。文学的にはパーフェクトに近い形で始末をつけていたのだ。
やはり彼は武人ではなく、文人だったのである。
老残と欺瞞と諦観と
三島の最期を政治的思想的行動と見る人には、あまりにも卑小化した結論に感じられるかもしれない。
しかし、三島は繰り返し「自分は政治的な人間ではない」と述べていた。彼は韜晦はしても嘘はつかない。嘘は理想とする“少年”のもっとも憎むべきところだからだ。
また、30代も後半に入った頃から、老残への恐れと、若者への共感を繰り返し表明している。三島を仮想敵とした全共闘の若者たちに三島が寄せたシンパシーを見るにつけ、少なくとも「怒れる若者」は三島にとっては好ましいものであり、だからこそ全共闘との討論会で「つまり天皇を天皇と諸君が一言言ってくれれば、私は喜んで諸君と手をつなぐのに、言ってくれないからいつまでたっても殺す殺すと言ってるだけのことさ」と吐露したのだろう。
これもまた、三島が脳筋的右翼ではなかったことの証左であると同時に、彼のハイムケール先が“過去の欠損が回収された世界”しかなかったことを示していると思しい。
いずれにせよ、三島の自死は、本人の意図はさておき、日本人に「天皇とはなにか」、ひいては「日本とはなにか」を考えさせる最後の機会になるはずだった。
GHQが共産主義より敗残の帝国主義の方が御し易いと判断し、天皇制を温存すると決めた時点で、日本は本当の意味で戦争を総括する機会を失った。
国民は戦争を選んだ臣民から、帝国主義の被害者として設定しなおされた。加害性を糊塗されたことで内省の時間を奪われた。誰もが己を無法な侵略者とは考えたくはない。だからむしろ喜んで「軍部に騙されていた」というナラティブに飛びつき、そのせいで国民国家として成熟するチャンスをみすみす逃した。
三島は戦後民主主義を欺瞞の塊とみた。戦中の欺瞞を熟知していたからこそ、新たな欺瞞に乗ることはできなかったのだろう。『英霊の聲』で昭和天皇を「などてすめろぎは人間となりたまいし」となじったのは、率先して欺瞞に乗った“神”への恨みだったように思う。
何をやっても社会は動かない。社会を動かせないという意味では、全共闘も自分も同じだ。諦めがあの馬鹿馬鹿しい行為の引き金になったように思う。
だが、最後はそれさえもうどうでもよかったのかもしれない。
彼にとってはなによりも大事なことがあった。
“The Lost Self”を取り戻すことだ。
あの最期は、彼にとって「自己回復の最善策」だったのか。それとも「負け続け人生のダメ押し」だったのか。
こればかりは本人の中にしか正解はないし、それを聞く術は永遠にない。
稀代の文学者・三島由紀夫は45歳で自決した。
歴史はこの事実を年表に留めるばかりである。