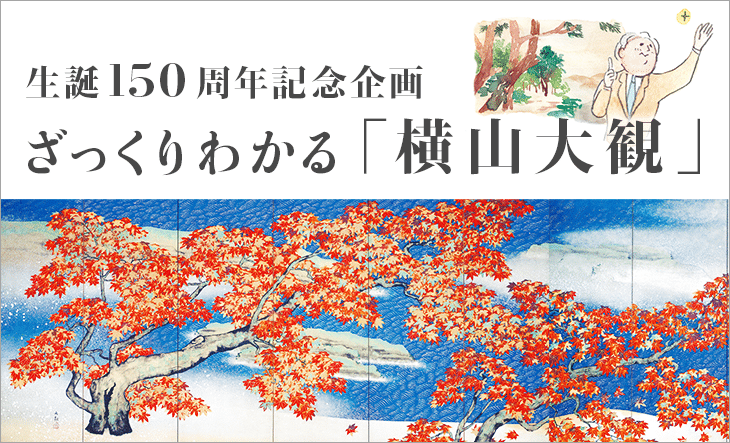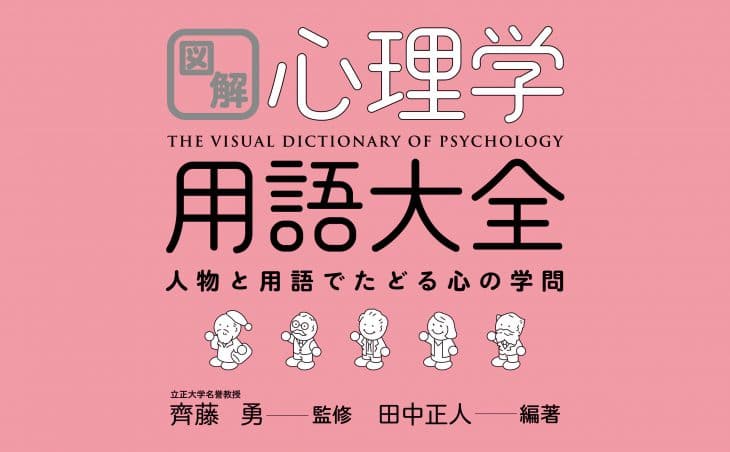第11回
尾崎翠――内なる兄と内なる妹(後篇その2)
2022.07.29更新
『文豪の死に様』がパワーアップして帰ってきました。よりディープに、より生々しく。死に方を考えることは生き方を考えること。文豪たちの生き方と作品を、その「死」から遠近法的に見ていきます。
「目次」はこちら
解離性同一性障害。
あまり聞き慣れない言葉かもしれない。以前、この病は「多重人格」と呼ばれていた。しかし、現在の正式名称は解離性同一性障害。こちらの方がより端的に病の実情を表しているからだ。
一人の中に、複数の人格が存在する。
そんなミステリアスな病態は人々の好奇心を刺激し、ドキュメンタリーからエンターテインメントまで幅広く取り上げられてきた。
最も有名な作品はダニエル・キイスが書いたノンフィクション『24人のビリー・ミリガン』だろう。ビリー・ミリガンは、1977年、米国オハイオ州で連続強盗/強姦犯として逮捕された人物だ。犯罪の記憶がないと供述する彼の不可解な言動に疑問を持った弁護士が、精神科医に分析を求めたところ、ビリーはオリジナルの他に複数の人格を身の内に宿す「多重人格者」だと診断されたのだ。
とはいえ、ビリーが医学的に認識された初めての「多重人格者」だったわけではない。18世紀にはすでに解離性同一性障害と思しき症状が記録されているし、19世紀には精神分析の俎上に乗っている。スティーブンソンが『ジギル博士とハイド氏』を発表したのは1886年のことだ。
しかし、米国でこの症状が注目されるようになったのは、1973年に精神医学ジャーナリストのフローラ・シュライバーが、16の人格を持つと診断されたシビル・イザベル・ドーセットについてレポートした『Sybil』(邦題『失われた私』)を出版してからのことである。シビルは幼い女の子から屈強な大工まで16人の人格を持っている、という触れ込みだった。あまりに衝撃的な内容ゆえ大ベストセラーとなり、良くも悪くも「多重人格者」を世間に強く印象付ける結果となった。
『24人のビリー・ミリガン』と『Sybil』はセンセーショナルな書きっぷりで共通している。何も知識を持たないまま読めば、それぞれの人格――交代人格と呼ばれるのだが――は、本人とはまったく無関係な別人格が神秘的な力によって外側からやってきて憑依したようにも読めてしまう。
たとえば、ビリー・ミリガンの交代人格は本来なら習得できるはずもない外国語を操ったとされているし、シビルの交代人格の中で主格だったのは現実のシビルとは程遠い優雅なフランス人女性だったと強調されているのだ。年齢や性別のみならず国籍まで異なるのだから、まったく赤の他人が取り付いたように思われても無理はない。ゆえに、やたらミステリアスなオカルトめいた病と認識されるようになってしまった。
こうした流れを受け、創作エンターテインメント作品では、神秘性や特殊性がさらに強調されることになった。主にホラーやスリラーのキャラクター設定として用いられたため、世間ではモンスター的なイメージを含む極めて特殊な症例と受け止められてしまったのである。
だが、実際の解離性同一性障害はそこまで劇的なものではない。交代人格はその人に内在する性質が強調されて浮き出たに過ぎないし、本人の潜在能力を超えるものではない。さらに言うなら、誰もがなりうる精神疾患の一形態に過ぎない。読んで字の如し、だが、解離が原因となって人格の同一性に障害が出ている病だからだ。
こうした病態は、かつてヒステリーと呼ばれていた。「ヒステリー」も俗化して誤ったイメージが流通してしまった言葉だが、解離性同一性障害もそれに近い誤解を受けているといっていいだろう。
そして、前提となる「解離」に至っては、さらに特別なものではない。健康的な精神を持つ人でもなりうる一種の「精神状態」だ。
たとえば、誰もが一度は「視線を感じて振り向いたら、自分を見ている人がいた」という経験があるはずだ。また、お風呂で髪を洗っていたら急に後ろに誰かがいるような気がして怖くなった、なんてこともそう珍しくはないだろう。そして、こうした体験を人に話したところで、特に変人扱いはされず、「ああ、そんなことってあるよね」と頷き合って終わることになるはずだ。
ところが、幽体離脱や予知夢となると話が変わってくる。場合によっては変人扱いされるかもしれない。でも、まだまだ「私もそういう体験あるよ!」と話が盛り上がる場合だってある。けれども、ここからさらに一歩進み、自分の中に他人がいる、というような話になったら、これはもう完全に正気を疑われるだろう。
だが、実はこれらはすべて「解離」の線上にある現象なのだ。意識や記憶、自己同一性、周辺環境の知覚といった情報を統合する機能が混乱しているだけだ。
色に濃淡のグラデーションがあるように、解離にもグラデーションがある。ごくごく淡い桜色と血のような真紅、双方まったく違う色調であってもどちらも赤系統として並べられるように、解離に含まれる症状のどこからが正常でどこから異常なのか、明確な境界線はない。
さらに、解離性障害は同一性ばかりを損ねるわけではない。同一性障害は障害究極の一側面に過ぎない。
自分の存在に現実感を失い、まるで映画を見ているような感覚に陥る離人症や、無気力、対人恐怖、幻聴、幻覚といった、他の精神疾患と共通する症状も現れる。また、頭痛やてんかん発作に似た身体的症状も出る。患者のうち、典型的な症状を示す人が半数にも満たないため、なかなか診断が難しいのだという。
また、もう一点、解離性障害(同一性障害を含む)で大きく誤解されているのが発症の原因だ。「多重人格者」ものの創作物やビリー・ミリガンのドキュメンタリーなどで顕著なのだが、主に幼い頃に受けた激しい虐待や尋常ならざるショックのトラウマが引き金になって解離が始まり、他人格を獲得するように描かれることが多い。ゆえに、そうした過去が発病の必須条件のように思われがちなのだが、現実には特殊な生育/生活環境になくとも発症する例はいくらでもあるそうだ。
一時的な「解離」は、日常的な過労やストレスでも発生する。ものすごく疲れた時、仕事をしながらも体と意識がリンクしないような、肉体は動いているけど意識はそれについていっていないような、妙な気分になることはないだろうか。その状態が「解離」である。多くの場合、それが「一時的」であるに過ぎない。だが、なんらかの要因で症状が持続すると、それは徐々に解離性障害として固定されていく。これは日常的に、誰にでも、起こりうる。
要するに、解離性障害=特殊な人の特殊な病気ではない、というのをまずは理解してもらいたい。
尾崎翠の場合、父を早くに亡くしたとはいえ、生育環境はごく普通だし、家族との関係も良好である。なんらかの特殊なトラウマがあったとは到底思えない。
しかし、三十代の翠は、強いストレスにさらされていた。
解離性障害を発症しやすい人は、想像力が豊かだったり、同調性が高かったりすることが多いという。同調性とはいわゆる「空気を読む」ことで、これが過剰になると無意識に自分を抑えすぎて、それが強いストレスになる。
翠は己の道を歩みたい人だったし、自負もあった。かといって同時代の文士に多く見られるようなエゴイズムとは無縁だ。社会的な常識も持ち合わせていた。さらに自己を客観視する能力に長けていた。
そんな彼女が、当時の慣習を無視して三十代でもまだ結婚せず、内縁の夫のような存在もなく、経済的に自立できないまま「売れない作家」に甘んじていた。
そんな自分をどれだけストレスを感じていたことか。
お母さん、私のような娘をお持ちになったことはあなたの生涯中の駄作です。チャップリンに恋をして二杯の苦い珈琲で耳鳴りを呼び、そしてまた金の御無心です。しかし明日電報が舞い込んでも病気だと思わないで下さい。いつもの貧乏です。私が毎夜作る紙反故はお金になりません。私は枯れかかった貧乏な苔です。(「木犀」より)
「木犀」は心境小説であると同時に、後期諸作品の特徴である奇妙な浮遊感――私はこれを“離人感”と勝手に呼んでいるのだが――を発揮した画期的作品だが、己を「枯れかかった貧乏な苔」と喩えている点に、単なる自虐を超える心情が感じられる。
けれども、そうした苦しさは日常生活中で表面に出されることはなかったようだ。
彼女が人に弱みを見せない自律的かつ抑制的な人間であったことは、作品からはもちろん、後年に発表された親族の手記や談話でも明らかである。どれだけ苦しくとも隠し通す。こうした人がストレスをためやすいのは言うまでもない。
愛別離苦と求不得苦
また、愛する肉親や友人との別れもまた大きなストレス要因になるが、その意味で1928年から1929年が翠にとってひとつの大きな曲がり角だったように思う。
1928年には親友にして最大の理解者であった松下文子がとうとう結婚し、旭川に帰ってしまっている。それによって二人が疎遠になったかというとそうでもなく、その後もちょくちょく会いはしている。しかし、やはり身近にいない寂しさは一入だっただろう。翠のような大家族で育った人は、おおむね孤独に弱い。
さらに、翌1929年には次兄の哲朗が亡くなった。これも、翠の世界を揺るがす一大事だったと考えられる。
僧侶だった兄の発病はこれより4年前の1925年のことで、どうやら脳梗塞やそれに類する病だったようである。この時もまた、翠は献身的な看護をしていたという。
翠の作品世界で「兄」に象徴されるのは保護者であり、憧れであり、規範であり、時には恋人的役割すら果たしている。これはおそらく、翠が上三人男の下に生まれた初めての女の子だったことが影響しているのだと思う。
上が兄ばかりの環境で育った女の子は、男の子の遊び方しかしらないからなんとかそれについていこうとするが、だいたいは邪魔にされ、味噌っかす扱いされる。これは子供心にも大きな不満になるが、裏を返せば「特別扱い」であって、女の子ゆえの特権を使えることもある。被保護感と疎外感の微妙なコラボは、絶好のブラコン培養地だ。
文壇に翠を意識させる大きなきっかけとなった「アップルパイの午後」は1929年の作品だが、ここで描かれる兄妹の他愛ないやり取りには兄の妹への親密な干渉と、妹の兄への甘やかな反発と依存がともに忍び込ませてある。
兄 いったいお前は何しに東京まで来たんだ。
妹 勉強しに来たんですよ。兄さんに打たれるためじゃありません。
兄 (ペンを奪う)莫迦。何が勉強なんだ、兄に反抗することばかり覚えて。いったいお前くらい男に似た女はないぞ。
こうした一見仲が悪そうで、その実良好な関係にある兄妹のじゃれあいの風景が、そのまま現実の兄と妹との間で交わされたとは限らないが、似たようなことがあってもおかしくはない(実際、哲朗の翠に対するものと思しき説教が記された文書が残っている)。
けれども、作品内で何度も妹を打ち、女らしくないと糾弾し、変態よばわりする兄は、彼女のブラザーコンプレックスが生んだ「内なる兄」だ。
同時に、妙におんなおんなした妹は、「内なる妹」として庇護者と、相愛の対象を求める人格である。
友と家族、二つの基盤が薄れていく一方で、新たな足場となりうる配偶者的存在とは出会えない中、内なる兄と内なる妹は、現実の翠の中で大きく分裂し、それぞれが育っていったのではないか。
次はその過程を、作品に沿って見ていきたい。