第5回
長谷川時雨――おやっちゃん、家族に揉まれて作家の種を育てる(中篇)
2022.03.11更新
『文豪の死に様』がパワーアップして帰ってきました。よりディープに、より生々しく。死に方を考えることは生き方を考えること。文豪たちの生き方と作品を、その「死」から遠近法的に見ていきます。
「目次」はこちら
長谷川時雨が戦前の文化人サークルにおいて大きな役割を果たし得たのは、本人の才に拠るところが大なわけだが、生まれ育ちがまったく影響していないわけではない。
長谷川家は江戸日本橋、つまり江戸のど真ん中で御用呉服店を営む、裕福な商家だった。だが、時雨の父、長谷川深造は、典型的な幕末の混乱期に生きた若者で、家業を嫌って北辰一刀流の流祖・千葉周作の剣道場に入門した。やっとうを修めた後は江戸城警護の役目を請け負ったりしているうちに維新を迎え、そのまま明治政府の刑部省(現在の法務省)に紛れ込む。そしてそこで輸入したてほやほやの“近代法”と出合い、日本初の官許代言人、今でいう弁護士の道を歩むことになったのだ。
江戸町人の華麗なる転身である。
生活は万事ハイカラ好みで、早々にザンバラ髪にし、普段も洋装で通した。新しい女ならぬ、新しい男だったのだ。
ただし、自宅はそのまま日本橋に置いた。維新前後で日本橋の住人も大きく入れ替わったが(中島敦の祖父が日本橋から去ったのもこの時期だ)、長谷川家は江戸期からの旧住人として幅を利かせ、地元の名士、地域の顔役になっていった。だが、名利には恬淡、つまり名誉や金儲けには興味がないタイプだった……と書くとなにやら石部金吉氏のようだが、実態は真逆で洒脱な文化人だったようだ。
大の歌舞伎好きで、名士として役者とも交流があった。その影響で時雨も幼い頃から芝居をよく見ていたし、梨園の人々と触れ合う機会を得た。これが、劇作家としてデビューした後のキャリアに大いにプラスになるのだが、当時はそんなことになるとは知る由もなく、芝居をただただ楽しんでいたことだろう。しかし、彼女の感性と驚くほどの記憶力の良さが、この時期の観劇を作品の種に変えたことは間違いない。
また、深造は俳句や絵もよくした。特に絵は歌川國輝(注1)や歌川国芳(注2)から手ほどきを受けており、才能を見込まれて養子にと望まれたことさえあったというから、相当の腕前だったのだろう。
だからといっておっとり雅びやかタイプかというとさにあらず、山の手出身の人々を「のての奴ら」と呼んで対抗意識を燃やす、ちゃきちゃきの下町オヤジでもあった。時雨の芸術的才能と一本気な江戸っ子気質はこの父から受け継いだと思しい。
母・多喜は没落士族の娘で、苦労人だった。父は江戸詰めの仙台藩藩士だったが、直参、つまり徳川家直属の家来という身分にあこがれて御家人株を買ったものの、間もなく幕府が瓦解した。樋口一葉家と同じパターンである。
文無しなった家族は静岡県御前崎に移り住み、塩田を作って生計をたてた。頑強な肉体を持っていた多喜は、女性ながらも労働力として当てにされ、学問は手習い程度。武家の娘の嗜みである諸芸を修める機会を失った。ただし頭はよかったようで、夫亡き後は実業家として成功を収めることなるのだが、それは後々の話。若い頃は、体だけは丈夫だが他は何も知らない無学な働き者、それが多喜のすべてだった。
長谷川家に後妻として入ってからは一家の主婦として日がな一日独楽鼠のように動き回り、万事完璧でないと気がすまない姑に仕えながら懸命に采配を振ったそうだ。時雨はそんな母の姿から骨惜しみせず働くことの尊さを学んだようである。
だが、父母以上に時雨の人格形成に影響を与えたであろう人物がいる。
父方の祖母の小りんだ。
この小りんさん、とにかくめっぽう面白い女傑で、時雨はたびたび祖母の追想を愛情たっぷりに書いている。
実家は伊勢朝長の大庄家、つまり裕福な農家だったわけだが、お嬢様としてしずしずしていたわけではない。男の子たちを家来にして、竹の棒を振り回して遊ぶとんでもないやんちゃ姫だった。
長じては美貌が近所の噂になる小町娘となったが、嫁入り前に疱瘡を患ってしまい、顔に薄い痘痕が残った。それを理由に幼い頃から決まっていた許婚との約束を辞退し、兄を頼って単身江戸に出てきたそうだ。
江戸時代の娘がこんな決断をするなんて、なんだかちょっとしたドラマがあったんじゃないかと邪推するが、今となっては藪の中。ただ、小りんが家の中でおとなしくかしこまっているようなタマでなかったことだけはよくわかる。
学問はなく、文盲だったそうだが、故郷で行儀見習いとして伊勢領主藤堂家の腰元に上がった際に、当時の女性に求められる嗜みを一通り身につけた。御殿女中であったことは、終生彼女の誇りだったという。
江戸に出てからは兄の紹介で実直な商人と夫婦になった。そして、内助外助に腕をふるい、夫を一代で日本橋の蔵持商人に仕立て上げた。スーパー妻である。深造は「僕のおふくろは、男だったら大臣にでもなっていただろう」と言っていたそうだ。
息子が家業を廃し、自身は隠居の身となっても、小りんは家内最高権力者であり続けた。
金持ちになってからも自ら先頭きって働き、無駄なお金は使わない倹約家の顔で家内に睨みをきかせる一方、日髪日風呂(注3)を欠かさないお洒落っぷりで、身だしなみの大切さを家族に教えた。奢侈に傾くことはないが、天保期にお上から理不尽な贅沢禁止令が出ても平気で無視する反骨心の持ち主でもあった。
また、大変な同情家で、身分の上下、内外の区別なく、困っている人には大いに手を差し伸べたそうだ。
こうした「小りんばあちゃんすごいエピソード」は時雨の代表作である「旧聞日本橋」にいくらでも出てくるので、興味を持った方はぜひ原文を読んでほしいのだが(青空文庫に入っています)、そんな中に、ちょっと気になる部分がある。
小りんについて語りながら、時雨はこんなことを言っているのだ。
子供を理解しない親――それはこの現代にもざらにありすぎる。男性的の気象をもったものにも赤い襟をかけ、島田髷に結わせ、箱入りの人形のように玩器物として造りあげようとする一方、白粉をつけて、しなしなしたがるような女性的稟質男子を、鉄砲をかつがせたり調練をさせたりして、此子はなんでも陸軍大将にすると力んでいるのもある。
その子の気質に関係なく、性別の枠に無理やり押し込んでしまう親や世間。
わざわざ読みほぐす必要もなく、明らかなジェンダーロール批判である。
さらに、こんなことも述べている。
昔の町人の考えでは、大胆でも、機智があっても、女らしくない女としたものと見える。メソメソ、グズグズ、ブツブツ、ウジウジしているのが女らしい女としたのであろう。女の人のすべてが低下したのは(祖父をわるくいってはすまないが)、こういう男に、扶養されなければならない位置に長く長くおかれたからであろう。そしてそういう善人といっていいか、グズ男といっていいか、ともかくそんな男どもの好みにあった女をつくり、その女が、そういう男の子を生んできたのだと思うと、うちの子はどうしてこう低能なんだ、なぞと、学校の試験や親の思う通りにならなかった場合に、そんな勝手なことはいえないはずだ。
これを初めて読んだ時、時雨ってすごいな、と素直に思った。
今に通ずるジェンダーの問題や女性抑圧の仕組みを、しっかりと把握しているからだ。
ここで、ごくごく簡単に近代フェミニズムの歴史を振り返っておきたい。
フェミニズム――最近あまり使われないが女権拡張主義や女性尊重主義と訳される思想が生まれたのは、18世紀末の欧州である。フランス革命で被支配層である「人民の権利」が高く謳われ、貴族平民を問わず普遍的な人権を持つとする思想が広まった。だが、これには大きな欠陥があった。身分の上下はないけれども、男女の別があったのだ。
当時の女性には参政権はいうに及ばず、財産権や親権、離婚の権利もなかった。誰もが普遍的な人権を持つと確認されたはずなのに、世の半分いる女が排除されるなんておかしいではないか。
女性たちがキレたのも当然であろう。
1792年に英国のメアリ・ウルストンクラーフト(注4)が『女性の権利の擁護』、1791年に仏のオランプ・ド・グージュ(注5)が『女性の権利宣言』、1792年に独のテオドール・ゴットリーブ・フォン・ヒッペル(注6)が『結婚について』を相次いで出版し、ここに近代フェミニズムの基礎が築かれる。ただし、学問として体系だって発展していったわけではなく、組織的な動きも19世紀半ばになるまで見られなかった。女性が自律的に動くのは難しかったからだ。
1850年代のフェミニズム運動は、上層中流階級の女性たちのうち、数少ない職業婦人だったガヴァネス、つまり上流階級の子供たちを教える家庭教師が中心になっていた。メリー・ポピンズやジェーン・エアがやっていたあのお仕事である。余談だが、私が原案を務めた波津彬子先生のコミック『お嬢様のお気に入り』にはガヴァネスを登場させている。アドリエンヌ・クレーヴと名付けた彼女はフランス革命でイギリスに落ち延びた没落貴族の子孫と設定していたのだが、そういう階層の女性がつける唯一のまっとうな職業だった。明治維新の女性教師と同じだ。
また、家庭の主婦からはもっと切実な声が上がっていた。DVからの保護である。今なお解決できていない問題だが、財産権も親権もなかった女性が夫の肉体的・精神的・経済的暴力にどれほど苦しめられていたかはわざわざ言及するまでもないだろう。
19世紀のフェミニズムはリベラリズム色が強かった。だが、20世紀に入ると、運動方法の違いから徐々に分派していき、一部は勃興してきた新思想、アナーキズムやマルキシズムなどに影響を受けていく。時雨がフェミニズムに触れたのはちょうどこの時期で、入り口になったのは、彼女の元に集まってきていた女性運動家たちだった。
だから、時雨のフェミニズムに対する知識は断片的というか、感覚的なものだっただろうと推察される。フェミニズムは、まだ学問としての骨組みが完成していなかった。けれども、前述したような基礎理論はあった。それを時雨が原著から独学できたとは思えない。
それでも、フェミニズムの要点は間違わずに掴み取っている。
時々いるのだ。
こういう“野生の学者”みたいな人が。
前回ちらっと書いたが、時雨は一度も公教育を受けていない。まして高等教育など望む術もなかった。
彼女が通っていたのは明治時代の一時期、公教育体制が整うまで小学校の代用にされた私塾で、教師も教える内容も江戸時代の寺子屋のままだった。だから、いわゆる修身道徳以上の難しいことは一切教わっていない。のちに英語と唱歌がカリキュラムに付け加えられたものの、多喜が学ぶことを禁じた。
実は、時雨がまともな教育を受けられなかった原因は、多喜にある。
母と娘の図書戦争
多喜は女性が文字に触れることを、異常なまでに嫌った。とにかく物語が好き……というより、文字中毒の気がある時雨に、読書を徹底的に禁じたのだ。時には激しい折檻を加えてまでも。
「おやっちゃんを、学問しなくっちゃならぬような子には生んでいません」というのがその言い分だったそうだ。
要するに学問はそれで食べていかなければならないような身分の人たちがするもので、良家の女性には必要ない、という理屈なのだろう。
五体満足で容姿が十人並みなら嫁に行ける。そして嫁ぎ先で男の子を産んで家庭の主婦としての地位を安泰にする。
それが、それだけが女の幸せ。
これが当時の平均的な女性観だった。そして、残念ながら、この価値観は日本を含めた世界のいたるところに残存している。
だが、多喜の行動は、時代性を勘案してもちょっと常軌を逸している。
娘が禁を破って本を読んでいたからといって、目の前でビリビリに破り、燃やし、激しく殴打し、蔵に閉じ込める。どこの継母だって話だが、実母だ。
だが、学問をさせない、十代のうちに嫁に出す、という以外のところでは、ごく普通の母としての愛情を注いでいる。
そこで、おかしいのは、母は、なんでそんなに厳しくしたかといえば、出来もしないことにふけって、なま半可な女ものになるのを、ばかに怖れたのではないかと思う。だから、あたしが、書いたり、読んだりするのは気に入らないが、ほかのことで、皆とひとなみに、楽しみとして見聞きすることは許さないではないから、あたしがずっと小さいころ、書生が幻燈会をして近所のものに見せたりするのを、共に楽しんで見ていたように、友達たちで、三味線などひいて芝居ごっこなどしても、それは遊びとして大目に見ていた。そして、あたしどもが、幾分、新知識を得ようとするとき、玄関の大火鉢の廻りや、紫檀の大机のもとに集まって、高等学校から来る大先生に、西洋ものの小説や劇の話をきくのも、それも許した。(「渡りきらぬ橋」より)
大先生といっても、出入りの一高生だが、耳学問がつくのは問題なかったらしい。
とにかく、本さえ読まなければいいのだ。
つまり多喜は「女の読書」を憎んでいた。そして、それはルサンチマンによるものだったと分析するのは、時雨の評伝を書いた岩橋邦枝だ。
<祖母への不服、父への不満>もあったらしい、と時雨は私小説風な「御奉公」のなかで思いやっている。娘の足を引っ張る嫉妬まじりの対抗心も、母の仕打ちに潜在していたように私には感じられる。(岩橋邦枝『評伝 長谷川時雨』より)
祖母への不服とは、家内において絶対的権限を握って渡さない姑への主婦としての不服。
父への不満とは、金儲けより政治活動などに熱心なことや、外に女を作って遊び回ることへの不満。
そんなところらしい。要するに自分が逆らえない相手への不満を、自分に逆らえない相手にぶつけたのではないかというのだ。
小りんは、武家の娘なら当たり前の教養や嗜みを多喜が持っていないことをたびたび小馬鹿にし、見下したそうだ。深造は幼い時雨を浮気相手の家に連れて行くことがあった。多喜は時雨に女の居場所を明かすように迫ったが、時雨は大好きな父への義理立てから決して口を割らなかった。それに対し、多喜が制裁として加えた折檻は半端ではなかったというので、岩橋氏の分析は正しいと思う。
ただ、私には、それに加えて自身が“理不尽な抑圧を受ける女”であると感じながらもそれを言語化できず、理不尽に迎合するしか生きるすべがなかった“時代の女”の苛立ちが見える。
多喜への評価は「屈強な体を持ち、子を何人も産み育てることができ、家事を取り仕切る程度の頭はある働き者」というだけ。なにせ、後妻に選ばれた理由は「顔とか頭とかはほどほどでいいから、とにかく丈夫な女」だったのだ。
前妻は姑もお気に入りの美しい女だったが、子供を二人生んでその後亡くなってしまった。だから、とにかく丈夫であればいい、それが深造の望みだったそうである。失礼千万だが、家父長制における妻の役割とは、家事労働に従事しながら子供を産む機械だ。ある意味、他の付加価値を求めない深造だったからこそ成立した結婚ともいえる。
ところが、娘のヤスは、体こそ弱いものの、祖母ゆずりの見目麗しさに伸びやかな感性、そしてあくなき好奇心と向学心を持っていた。そして、親と本人さえその気になればいくらでも本を通して古今の文化に浸れる環境があった。つまり、多喜なぞ想像もできない付加価値を持ち得る娘だったのだ。そして、実際にそうなった。
けれども、“自分が理解できない付加価値”を認めるのは、多喜にとっては大きな苦痛を伴ったのではないか。
武家の娘なのに、時勢のせいで何一つ身分にふさわしい嗜みを身につけることはできなかった。野人のように塩を汲まされながら、少女時代を送った。
でも、働けば人に褒められた。孝行娘として褒状を授けられたほどである。
だから、彼女のアイデンティティはそこに固着した。
女は家庭に入って子を生み家内を取り仕切れば、それが一番立派なのだ。
学問も行儀作法も何するものぞ。
時雨がいうところの「男どもの好みにあった女」に自らを嵌め込み、それをやってのけることでしか自己を確立する術を持たなかったのではないか、と思うのだ。
それなのに、姑も夫も、文化的素養を彼女に見せびらかす。態度の端々に「無教養な女」と下に見ていることがわかる。
この上、娘にまでそう見られるようになっては、溜まったものではない。
せっかく築き上げた「自分」が崩れてしまう。
もし、多喜に想いを言語化できるほどの教育があれば、あれほど娘に当たらなかったのではないかと思う。ただ、この仮定は、当時ではまず実現不可能、今でも結構厳しい。
自分のモヤモヤを言葉にするのは、実はもっとも難しい行為だと私は思う。
だから人は日記を書くなどして己を客観的に見つめようとするのだが、そんな習慣を身につける機会さえ奪われた多喜には、モヤモヤを晴らす術は暴力しかなかったのだ。幸い、親の暴力は「しつけ」の美名に転換される。
一方、時雨の聡明さは表に出るものではなかった。家での愛称が「アンポンタン」だったぐらい、おっとりした娘だったらしい。時雨は後年、幼児の自分を振り返って総領の甚六と表現している。今ではほぼ死語となったこの言葉、長男や長女は大事に育てられるので、弟や妹に比べるとのんきでお人好し、という意味だ。
だが、アンポンタンは、どれだけ禁じられても読書を諦めない粘り強さをうちに宿していた。
そして、母と違い、受けている理不尽を言葉で表現する力を持っていた。むしろ、母の抑圧が、時雨を「考え、表現する女」に育てた部分がある。
旧幕時代そのままの物堅い商家の空気を色濃く残す家庭で、長女として強く抑圧されたことが、巷間の一女性・ヤスを“時雨”という稀な個性に窯変させた。
結果、野生のフェミニストが生まれたのだ。
とはいえ、大きな花を咲かせるまでにはまだまだ試練が待ち受けていた。
時雨の上流階級体験
小学校の過程が終わると、上の学校には進めず、各種習い事だけ許された。でも、本を読むことは諦めなかった。そこで、多喜は妙案を思いつく。
そこで、いよいよ懲らしめのため、も一つには行儀見習い、他人の御飯を頂かないものは我儘で、将来人が使えないという、立派な条件を言いたてに、母が大好きで、自分が、旧幕時代の大名奉公というもの、御殿女中というものにあこがれていた夢を、時代の違った時になって、娘によって実現して見ることにきめてしまった。 (「渡りきらぬ橋」より)
時雨は、旧岡山藩主池田侯爵の家に老侯夫妻のお小姓、つまり小間使いとして奉公に上がることになった。時に14歳。母は念入りにも、奉公中は決して本を読まさぬよう、たとえ新聞たりとて目に入らぬよう計らってくれと頼み込んでいた。この執念、もはや恐ろしい。
ところが娘もさるもので、給料が出るのをいいことに、屋敷の小使いに頼んで本を買ってきてもらった。母が母なら娘も娘。どっちも絶対に引かないのである。
こうして抜け道を見出し、肩身の狭いお屋敷奉公をなんとか乗り切ろうとした時雨だったが、無理がたたって肋膜炎を発症し、宿下がりすることになる。小康状態を得ると再度奉公に出たものの、快癒することなく、17歳で奉公を終えることになった。
この経験を通じ、時雨は上流階級の実態を知った。また、年寄りだけでなく、同じ世代にも旧幕時代から一歩も出ない価値観に生きる女たちがいることを知った。
それは後年、「近代美人伝」など一連の美人伝シリーズを執筆する際の知識として役立った。また、近代女性の対照として置くべき「旧き女たち」の行動/思考パターンを熟知したことで、考察に一層の深みがでたと思う。時代についていけない一群の人々を等閑視しなかったのは美点に数えてよい。
とにかく、転んでもただでは起きないのが時雨の時雨たる所以だ。
実家に戻った後は、ほんのひと時、楽しく安らぎに満ちた日々を過ごすことになる。
著名な歌人で国文学者の佐佐木信綱が主宰する「竹柏園」で源氏物語や万葉集の古典を学ぶことを許されたのだ。学問を禁じられた樋口一葉が下田歌子の私塾には通わせてもらえたのと同じである。
とはいえ、どうやら正式な入門ではなかったらしい。小遣いからいくばくか払っていたようだが、おそらく月謝の額には足らなかっただろう。結局、父と仲の良かった佐佐木が特別に目をかけてくれた、ということらしい。とはいえ、ただのお友達向け特別サービスではない。佐佐木は時雨の才に注目していた。ただのお嬢さんとは思っていなかったのだ。
良家の令嬢が出入りするサロンのような場所への出入りには、多喜も片目をつぶった。
だが、片方の目は虎視眈々と狙っていた。
なにを?
もちろん、娘の縁談を。
彼女にしてみれば、もう嫁に出すにはギリギリのタイミングだった。
ヤスを行かず後家にするわけにはいかない。
その焦りが、時雨にとっても、長谷川家にとっても、最悪のカードを引かせてしまうことになる。
注1:歌川国輝(1830−1874)
幕末から明治時代初期にかけて活躍した浮世絵師。三代歌川豊国の門人で、開化絵を得意とした。
←戻る
注2:歌川国芳(1798*−1861)
江戸時代末期の浮世絵師。初代歌川豊国の門人で、武者絵の国芳として名を馳せるとともに、洋風の画法をとりいれた風景画を手掛けた。月岡芳年など多くの弟子を育て、江戸末期の浮世絵界に名を残した。
←戻る
注3:日髪日風呂
江戸時代の人にとって、風呂も髪結も毎日するものではなかった。よほど財力があり、かつ身だしなみに気をつけている人でないと毎日髪を結い直したり、お風呂に入ったりすることはなかったのである。
←戻る
注4:メアリ・ウルストンクラーフト Mary Wollstonecraft(1759-1797)
著述家、運動家。裕福な農家の生まれだったが、家が没落し、家庭教師などを務めたあと,執筆活動を開始した。『女性の権利の擁護』(A Vindication of the Rights of Woman)で有名になった後、アメリカ軍商ギルバート・イムレーとの間に娘をもうけたが破局。ゴドウィンと結婚し,一女を生んだが産褥熱で死亡した。遺された娘は『フランケンシュタイン』を書いたメアリー・シェリー。
←戻る
注5:オランプ・ド・グージュ Olympe de Gouges(1748―1793)
フランス革命期にパリで活躍したフェミニスト。劇作家、俳優。庶民の出で文字は読めなかったが、劇作の才能に溢れていた。1789年公布「人権宣言」が女性の権利を無視していることに怒り、17条の「女権宣言」をマリー・アントワネットに奉呈した。フランス革命後、ロベスピエールによってギロチン刑に処された。
←戻る
注6:テオドール・ゴットリーブ・フォン・ヒッペル Theodor Gottlieb von Hippel(1741-1796)
啓蒙主義の文筆家。行政官として成功し、ケーニヒスベルク(現ロシア カリーニングラード)の市長を務める。独身主義者である一方、女性の権利に深い理解を示し、『結婚論』や『女性論』を書いた。哲学者のカントと交流があった。
←戻る







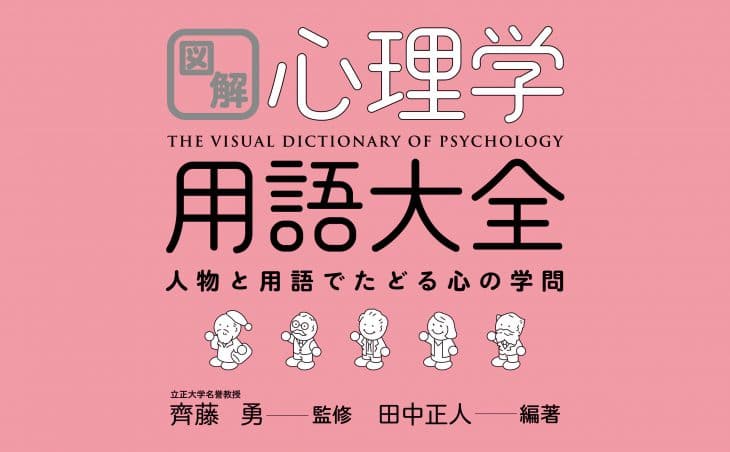
林 健志
2024.04.09
ふとした縁で長谷川時雨に関心を持ち、「旧聞日本橋」を買って読み始めたのですが、時雨の文章の小気味よいキレのよさに打たれていたところ、本サイトに出会いました。
2話を一気に読んでしまいました。まるで目の前で話されているような文体で、書かれていることがどんどん浸み込んでくるような気がしました。また、時雨だけでなく、彼女を取り巻く人々のことや当時の事情が分かりやすく紹介されていたことで、理解度が大いに上がりました。
時雨の一生のうち、晩年の行動はよく理解できなかったのですが、それもすっきりしました。読みながら笑ったり胸を詰まらせたりして、楽しませてもいただきました。ありがとうございます。ちょっと時間をおいて、再度読み直したいとおもいます。
また、他の話にも関心のあるものもありますので、そちらも読んでみたいと思っています。