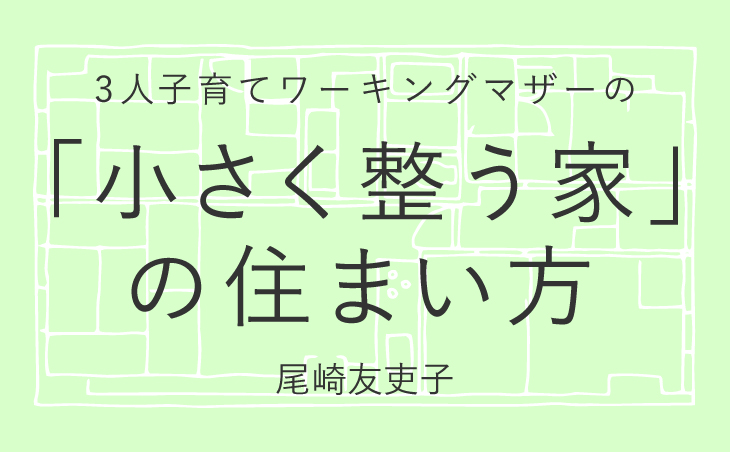第15回
【老衰死・平穏死の本】原爆の記憶
2018.03.01更新
まもなく多死社会を迎える日本において、親や配偶者をどう看取るか。「平穏死」提唱者・石飛幸三医師の著作『「平穏死」を受け入れるレッスン』期間限定で全文連載いたします。
「目次」はこちら
本を「聞く」という楽しみ方。
この本の著者、石飛幸三医師本人による朗読をお楽しみください。
■原爆の記憶
私は昭和一〇(一九三五)年生まれです。戦争が終わったのは、一〇歳、国民学校四年生のときでした。八月を迎えると、いまもあの日のことを思い出します。
昭和二〇年八月六日午前八時一五分、暑い夏の朝、私たちが目にしたのは虹色のキノコ雲でした。
私が生まれ育った広島県高田郡吉田町(現・安芸高田市)は、広島市から北に四〇キロほどのところにあります。その朝、私たちは国民学校の校庭にいました。夏休み返上でやっていたのは授業ではなく、草鞋(わらじ)編みでした。食料不足を解消するためには、畑を増やす必要があります。その開墾作業のときに履く草鞋を編んでいたのです。
脚を前に投げ出して座り、藁を縒り合わせて縄状にしたものを両足の親指に引っかけてこれを縦糸とし、もう一本の縄を横糸にしてくぐらせ結びながら編み込んでいくのです。
校庭に座ってうつむいて作業をしていたとき、突然、強烈な光で目の前が真っ白になりました。何事かと思って顔を上げると、空は真っ白く、南の方向の空が赤みを帯びているように見えました。広島の方角です。その南の山の上に、大きな赤い火の球のようなものが消えていきました。
続いて激しい地響きがあり、校舎の窓ガラスが割れんばかりに揺れました。経験したことのない爆発のようでした。
頭の上を、北に向かってB29が一機、重い音を残して飛び去っていきました。間もなく広島の方角の山の上から白い雲が湧き上がり、どんどん上に延びてある高さから横に広がって、さらに一段上に延びてまた広がって、二段構えの巨大なキノコ雲になりました。それは白一色ではなく、全体が虹色を呈していたのです。
呆然と奇妙なキノコ雲を見ていた私たちに、先生の叱咤の声が飛びました。
「何をぼんやりしとるんか。はよう、防空壕に退避せい」
その声に、みんなはっと我に返りました。
防空壕といっても校舎の裏山に掘っておいたほら穴にすぎないのですが、遅ればせながらあわててその穴に身を潜めました。どれくらい穴にいたのか、ずいぶん長い時間が過ぎたように思いましたが、その後は何も起こりませんでした。
町は大騒動になっていました。広島市街がとんでもない状況になっているらしいことが伝わってきて、次々と負傷者が運ばれてきました。
私の家の向かいに、町で唯一の医療機関である病院がありましたが、そこはたちまち負傷者であふれ返りました。私の家は呉服屋をしており、古い商家造りの倣いで間口は狭いのですが奥に長く、部屋数がたくさんあったので、急遽、臨時の入院病棟として使ってもらうことになりました。
それからしばらくの間、家族の居間以外の使える部屋はすべて、広島市内から来た負傷した人たちの臥せるところとなりました。水ぶくれになり、むくんで、次々と亡くなっていきました。不幸な最期を迎えられた方たちの記憶が、いまも私の脳裏に焼き付いています。
国民学校の校舎も、負傷者の収容施設になりました。
そして、学校の裏山からたちのぼる煙が絶えませんでした。亡くなった方の臨時の火葬場となったのです。
■「いのちの重さ」を考える
広島に続いて、長崎にも原爆が投下されました。非戦闘員である市井の人々を突然襲った惨劇により、多くの人のいのちが奪われました。
そして戦争は終わりました。
日中戦争から太平洋戦争までの日本人の戦死者は、軍人・軍属が二三〇万人、民間人が八〇万人、三一〇万人のいのちが無残に失われたとみられています。
戦争は、人間の狂気の所業です。
私は六人きょうだいで、一番上の兄は昭和二〇年四月にフィリピンで戦死しました。死を知らせる通知のあと、白木の箱が届きました。その中に入っていたのは石ころ一つ。遺品の一つも、遺髪の一本も還ってはきませんでした。
両親の深い嘆きを、末っ子である私は間近でじっと見ていました。父は、せめて供養だけはしっかりしてやりたいと、自分の郷里の出雲に兄のためにそれは立派な墓を建てました。
広島市内の女学校の生徒だった二番目の姉は、たまたま原爆の一週間前に吉田に疎開してきていたため、死を免れました。原爆の三日後から救援隊として広島に入りましたが、そこで目の当たりにしたのはどれだけ悲惨な光景だったでしょうか。
戦争の時代が終わり、日本は戦後復興の道を歩みはじめました。憲法で基本的人権が保障され、生存の権利をむやみに脅かされることはなくなりました。
昭和二三年、死刑の是非を論ずる最高裁の判決文の中で、「生命は尊貴である。一人の生命は、全地球よりも重い」という表現が使われました。
そして、戦後の日本社会には「人のいのちはかけがえのないもの、大切にされなければならない」「いのちは重い」という考え方が浸透していきます。
少し前まで「お国のために死ね」という方針だったのが、一転して「人のいのちはかけがえのないもの」と変わったわけです。いのちの価値の急転に、子どもながら戸惑った記憶があります。
この本を購入する